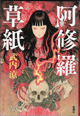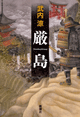| 1. | |
|
「阿修羅草紙」 ★☆ 大藪春彦賞 |
|
|
2024年01月
|
時代は足利将軍・義政の時代。 主人公は、比叡山を守る忍び=八瀬童子のくノ一であるすがる。 比叡山延暦寺の宝物が何者かによって奪われます。 しかも、すがるの父で熟練の忍びでもあった般若丸を含む8人の守部を殺害したうえで。 中ノ頭に任命されたすがるに、盗まれた宝物の奪回、盗んだ者への処罰が命じられます。助っ人は雇われた伊賀者2名。 本作はそこから始まる、熾烈な忍び同士の戦いを描く忍者もの長編時代小説。 しかし、何時の間にか、何のために宝物を奪い返すのかという目的は薄まり、忍び同士の、お互いに潰し合うかのような闘いが延々と続けられます。正直なところ、悲哀ばかりが増していく、といった展開。 ・八瀬童子=忍びといえば、隆慶一郎「花と火の帝」。もっとも時代も異なれば、仕える先も異なり(本作は延暦寺、隆作品は帝)ますが、後者には伝奇小説としての面白さがありました。 ・また、忍び同士の殺し合いというと、山田風太郎「忍法八犬伝」を思い出しますが、伝奇小説だけにカラッとした明るさがありました。 両作に比べ、明るさはなく、陰惨さばかり感じるストーリィと言って良いでしょう。 ・なお、ストーリィ中には将軍義政、ならびにその側女であった今参局のことが出てきますが、ちょうど奥山景布子「浄土双六」で読んだばかりのことだったので、理解がし易かったです。 忍びの技という面では読み応えたっぷりですが、本作を読み終えた時には悲哀ばかりが強く残った、という感じです。 |