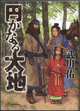| 「かすてぼうろ−越前台所衆 於くらの覚書−」 ★★ | |
|
|
百姓の娘が城の台所に奉公に上がり、やがて台所衆、包丁人となってその料理をもって時代をも動かしていく、という時代ストーリィ。 展開が現実離れしているが故に、言わば、女性料理人を主人公としたファンタジー的な時代歴史&少女の成長物語、という処でしょうか。 でも料理が人の心を動かしていくという処は、楽しいという一言に尽きます。 於くら、13歳になって越前府中城の炊飯場へ下女として働きに出ます。その働き先で於くらは、台所衆の男たちから年中蹴られたり散々な扱いばかり。 ところが、夜半つまみ食いに台所にやってきた茂助と名乗る初老の男に簡単な食べ物を提供して親しくなったところ、何とそれが新しい領主である堀尾吉晴。 その吉晴の要望に応えようと懸命に尽くすうち、於くらも成長。 しかし、関ヶ原の戦い後、堀尾家は松江に転封となり、代わって結城秀康が越前68万石の領主となり、於くらは府中城から北ノ庄城へと移ります。 新領主の秀康も気さくな人物。於くらが身を寄せた城外の煮売茶屋「哉屋」に身分を隠してふらりと現れ、於くらと親しみ、城内においても於くらに次々と注文を出し、於くらはそれに応えていきます。 そしてついには、歴史を動かく重大な現場にも立ち会うこととなり・・・。 於くらが課題を与えられる度に工夫を巡らし料理人として成長していくストーリィに、当時の料理に関する歴史考証の一文が挿入されていることを合わせて、料理ストーリィ好きな人間としては楽しい限りです。 美味しい料理は大事な場面で人を動かすこともある、というのは事実かもしれませんね。 かすてぼうろ/里芋田楽/越前蕎麦/一番鰤/甘う握り飯/本膳料理 |