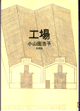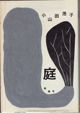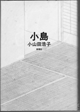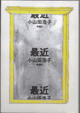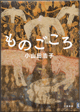| �u�H ���v�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���V�l�܁E�D�c��V���� | |
|
2018�N09��
|
�\����u�H��v�́A����ȍH��Ō_��Ј��A���Ј��A�h���Ј��Ƃ�������œ����n�߂��R�l����l���ɂ�����i�B �u�f�B�X�J�X���v�͂����ƓǂݏI����Ă��܂����тł����A���R�̂͂����蔻��Ȃ��s�C�����E�E�E����B �u�����ڂ�̂ނ��v�́A��Г��A���q�Ј������̃��C���C�K���K���Ƃ��Ă������`�����сB�����ł͒N�����A�����瓦����Ȃ����A���̗ւ̈���Ƃ����ǂ��p���Ȃ���ΓI�ƂȂ邱�Ƃ�������Ȃ��B �H��^�f�B�X�J�X���^�����ڂ�̂ނ� |