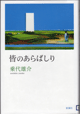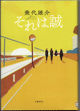| 1. | |
|
「十七八より」 ★★ 群像新人文学賞 |
|
|
2022年01月
|
デビュー作。 芥川賞候補となった「二十四五」の前にあった作品。 同作を読んだ時、主人公と亡叔母の関係が判らないままだったのが気になり、読んでおこうと思った次第です。 主人公の阿佐美景子は高校生。 男性体育教師から執拗につきまとわれる等、他の生徒とはちょっと違う処があるのかもしれない。 一方、叔母の阿佐美ゆき江は、実父が経営する眼科病院<あさみクリニック>で看護助手や医療事務を担っている。美人でもなく背も低く、老けて見えるゆき江は、外見面で主人公とは対照的ですが、文学には通暁しているらしい。 何かと難しい性格のこの主人公、叔母にだけは本音を曝け出しているようです。 語り手によって主人公は「あの少女」と表現されていますが、その語り手が誰なのかといえば、成長した後の主人公本人であるらしい。 つまり、高校生当時の自分と叔母との関わり様を、後日になって客観的に見直している、という設定。 当時と語り時点、叔母と主人公との間には様々な思いが行き合っていたのではないか、と想像されます。 敢えて文章にしないその辺りが本作の興味どころ、と感じます。 |