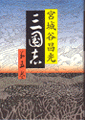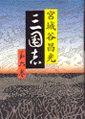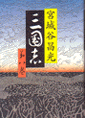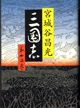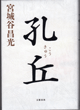|
|
21.三国志・第5巻 22.三国志・第6巻 23.三国志・第7巻 24.三国志・第8巻 25.三国志・第9巻 26.三国志・第10巻 27.三国志・第11巻 28.三国志・第12巻 29.孔丘 |
【作家歴】、重耳、晏子、孟嘗君、楽毅、星雲はるかに、太公望、華栄の丘、子産、沙中の回廊 |
|
|
| 公孫龍(巻一)、公孫龍(巻二)、公孫龍(巻三)、公孫龍(巻四) |
|
●「三国志・第5巻」● ★☆ |
|
|
2010年10月
|
第五巻。本巻も引続き曹操が中心です。 宮城谷さんは単なる英雄像を描こうとした訳ではないのでそうなるのでしょうけれど、では何を描こうとしているのか。 優れた能力をもち主に忠実であってもその主から正当に扱われるとは限らない。群雄が多数争う激動の時代だけに、その違いは臣下にとっても大きいのですが、だからといって自由に主を選択できた訳でもありません。 孫策/素志/新都/張繍/僭号/高山/下邳/逐勝/密詔/対決/官渡/鄴県 |
|
●「三国志・第6巻」● ★★ |
|
|
2010年10月
|
群雄割拠していた状況が収斂していき、三国鼎立の時代に至る過渡期を描いた巻。 袁氏を滅ぼし曹操が勢力を拡大していく姿と並行して、様々な有為の人物たちの生き様が描かれます(高幹、田疇、甘寧、魯粛等)。まるで曹操、劉備、孫権の3人より、そうした人々の方が本巻の主役であるような印象さえ受けます。 その一方で民たちは何を思っていたのか、とふと考えました。 北方版三国志のような英雄譚ではありません。それ故に、孔明が劉備に組したのは他の2人に組したくなかったという消極的な選択が初めにあり、関羽・張飛と諸葛との折り合いは余り良くないと描かれる辺りに、北方版三国志とは別の味わい、面白さがあります。 袁譚/高幹/田疇/三顧/甘寧/長阪/魯粛/水戦/赤壁/江陵/合肥/巡靖 |
|
●「三国志・第7巻」● ★★ |
|
|
2011年10月
|
本巻では、荊州四郡を支配下に置いたことにより劉備がいよいよ立ち、才ある人物らは曹操、孫権、劉備のいずれに付くか、という選択を迫られることになります。 好き嫌いではなく、相性という面から見ると面白い。 ところで本巻における肝心のストーリィはといえば、曹操においては馬超との争ってこれを追い払い、劉備においては益州へ進出し、劉璋配下の良将たちの支持を得てついに益州を得る。 四郡/養虎/寵統/潼関/雨矢/馬超/法正/劉璋/成都/天府/張遼/魏国 |
|
●「三国志・第8巻」● ★ |
|
|
2012年10月
|
関羽、曹操、張飛、劉備が相次いで死し、「三国志」の大きな節目となる巻であると同時に、曹操・劉備の臣下にとって混乱尽きない巻。 一方、曹丕は後漢の献帝から禅譲を受け魏帝となり、それに対抗して劉備も帝を名乗ったことから2帝+1王(呉)となる。これでまさしく三国時代となった、というのが宮城谷さんの弁。 三国志の英雄は疑いもなく、曹操・劉備・孫権の3人。 兄弟/霖雨/関羽/徐晃/曹操/新制/禅譲/報復/白帝/劉備/使者/南中 |
|
●「三国志・第9巻」● ★☆ |
|
|
2013年10月
|
前巻の感想の最後に、これからの巻が面白くなるかどうかは諸葛孔明次第と書いたのですが、まさしくその通り。そしてその結果はというと、期待外れ、でした。 まずは魏。臣下の諫言を嫌う曹丕は、王位を継承して僅か7年で死去。その子である曹叡22歳が皇帝位を継承します。この曹叡がかなり英邁であった、ということらしく、魏は曹丕の頃よりむしろ安定、盤石ぶりを見せます。 相変わらず数多くの人物が登場します。良臣・良将もいればそうでもない臣・将もいますし、赤心をもって主に諫言する臣もいれば、自分の身が第一という臣もいる。 曹丕/猛達/箕谷/街亭/曹休/陳倉/三帝/曹真/天水/悪風/遼東/張昭 |
|
●「三国志・第10巻」● ★☆ |
|
|
2014年04月
|
まず前半、蜀の重鎮である諸葛孔明が戦場にて病死します。 一方の魏では、曹操-曹丕から帝位を継いだ曹叡が中々の戦略眼を備えた人物であり、その配下にあって司馬懿が魏の支柱として頭角を現し、ますます魏は興隆の途にあるといった様相です。 残る呉では、策を好むだけで軍事的才能がなく、臣下を育てることもなかった孫権が引き続きトップに坐り続けており、国の勢威は低調という感じ。 英雄たちが舞台を去った後の、小粒になった三国情勢を描いた巻という印象です。 流馬/満寵/秋風/孔明/増築/燕王/長雨/曹叡/浮華/赤烏/蒋琬/駱谷 |
| 27. | |
|
●「三国志・第11巻」● ★☆ |
|
|
2014年10月
|
第11巻はまず、老いた孫権が君臨する呉の様相から。 一方魏では幼い養子が帝位を継いだことから、大将軍の曹爽が権力を握るや専横の傾向を露わにしていきます。それを周到な計略により司馬懿が曹爽を打倒しますが、その後の司馬懿の動きを見るに専横を振るう人物がただ入れ替わっただけという観を強くします。 本巻は呉と魏が主体で、蜀については殆ど語られません。一応劉禅という皇位継承者がきちんと存在し、国の体制も一応安定しているからでしょう。 悶死/曹爽/非常/霹靂/王淩/老衰/交代/晩光/太傅/敗残/大政/掃除 |
| 28. | |
|
●「三国志・第12巻」● ★★ |
|
|
2015年04月
|
毎年1巻ずつ、12年に亘って書き続けられてきた長大な宮城谷昌光版三国志の完結編。 本巻では、魏において司馬懿の息子である司馬師~弟の司馬昭によって帝の実権は奪われ、呉においても孫峻~孫綝が実権を取り戻そうとした若い帝を排斥し殺害するに至るという下剋上の実態が描かれます。それでも魏の勢力が衰えるということには繋がらず。一方、諸葛孔明の後を担った将軍=姜維の人物不足と宦官の専横によって国力を低下させた蜀ではついに劉禅が魏に降伏し、三国時代は終わりを告げます。魏に対する同盟国を失った呉もやがて魏の軍門に下るだろうことは最早明白となり、魏もまたその後に司馬昭の子である司馬炎が魏最後の帝から禅譲を受け晋が建国されるという経緯が付されます。 ある意味、自身にも蜀という国についてもその現実を見極め、時を過たずさっさと魏への降伏を決めて無用に臣下・人民を死なせることはなかった劉禅の出処進退は、見事なものではなかったかと感じられます(三国の中で劉禅のみが二代皇帝、52歳と年配)。 作者の宮城谷さんにお疲れ様でしたと言うのは勿論ですが、読者としてやっと12巻全てを読み終えホッとしている、というのもまた正直なところです。 |
| 29. | |
|
「孔 丘(こうきゅう)」 ★☆ |
|
|
|
孔子と言えば“儒教”=「論語」、というのがすぐ思い浮かぶこと。逆に言えば、それしか思い浮かばない、というのが私の浅学なところでもあります。 釈迦、キリスト、ソクラテスと並んぶ<四聖人>の一人。 題名が、一般的な「孔子」ではなく「孔丘」であるのは、孔子は尊称であって、本名は孔丘(名・諱)であるから。 即ち、神格化された<孔子>ではなく、生の人間としての<孔丘>を描く、というのが本作の狙いだからのようです。 母の葬儀から始まり、孔丘の歩んだ道のりが、宮城谷さんらしい恬淡とした口調で語られていきます。 当然ながら、弟子が増えようと雌伏の時が長く、ようやく評価されても陽虎の謀叛や、権力争いの煽りで亡命生活を送る、というようなことの繰り返し。 だからこそ歴史に名を残した、と言えないこともないような。 元々の趣向がそうだからと言えますが、読了後、孔丘とはどういう人物だったのかと振り返ると、偉人でもなく英雄でもない、ただ学ぶことと教えることが好きだった人、という印象です。 また、孔丘の言う“礼”とは何だったのかというと、“秩序”というところでしょうか。 孔丘を徹底して生身の人間として描いたせいか、いつも物足りなさばかり抱えていた人物のように思えて、あまり面白くない。 むしろ、弟子であった漆雕啓(しつちょうけい)、仲由(仲季路)らの方が肉感的で面白いと感じられます。 ということで、宮城谷さんには申し訳ありませんが、★☆評価。 ※なお、斉で晏嬰が登場したと思ったら、どうも孔子とは反目し合ったようです。 盛り土/喪中の光明/陽虎/礼と法/郯君の来朝/詩と書/儒冠と儒服/水と舟/上卿の憂鬱/下の剣士/王子朝の乱/季孫氏の驕り/琴の音/魯国の苦難/成周へ/周都の老子/留学の日々/老子の教え/それぞれの帰国/去来する人々/兄弟問答/陽虎の乱/魯の実権/迫る牙爪/公山不狃の誘い/虎と苛政/天命を知る/中都の宰/司寇/兵術くらべ/道の興亡/衛国の事情/歳月の力/受難の旅/天に問う/大いなる休息 |
宮城谷昌光作品のページ №1 へ 宮城谷昌光作品のページ №2 へ