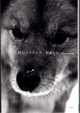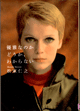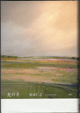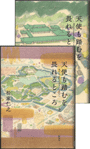| 1. | |
| 「火山のふもとで」 ★★★ 読売文学賞 | |
|
2025年02月
|
地味な作風だが評価の高い建築家=村井俊輔(70代半ば)の事務所に運よく入ることができた新人建築士の坂西徹。 何よりも魅力なのは、小説を読む喜び、そのストーリィの中に浸る楽しさが豊かに味わえること。 また、本ストーリィは建築設計事務所を舞台にしているだけあって作品そのものにも、彼らが設計する建物のようなきめ細かさ、確かな設計があり、ちょうど建物の周りをぐるっと回って初めてその建物の美しさを実感するような素晴らしさを感じます。 本作品がデビュー作というのは全くの驚き。小説を読む楽しさをじっくり味わいたいという方に、是非お薦めしたい逸品です。 |