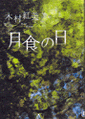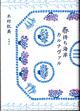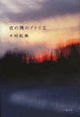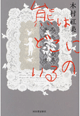|
「イギリス海岸−イーハトーヴ短篇集−」 ★★ |
|
|
|
副題「イーハトーヴ」は、もちろん宮沢賢治が故郷=岩手県を呼んだ名前(エスペラント語)。そして表題作「イギリス海岸」は、やはり宮澤賢治が花巻の川岸を英国の海岸になぞらえて呼んだ名前。 題名が示すとおり、本書は宮沢賢治の存在を抜きにしては語れません。本書に惹かれたのも洒落た感じの表紙と、宮沢賢治故ですから。 本書は直接宮澤賢治に絡むストーリィではありませんが、それでも、そこかしこに賢治のイメージが浮かびます。 宮沢賢治は理想を追い、そして夢をみることのできた人でしょう。本書を読んでいると、そんな賢治の雰囲気にそっと寄り添っているような気分になります。 それが本ストーリィの世界を楽しく、豊かにしているのは間違いない。 本書ストーリィは双子の姉妹、翠と梢を交互に主人公として語られていきます。 ごくあっさりとしたストーリィを連ねた短篇集。イーハトーヴを偲びながら雰囲気を楽しむ、それだけで充分楽しい一冊です。 福田パン/イギリス海岸/中庭/ソフトクリーム日和/帰郷/クリスマスの音楽会 |