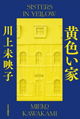|
●「乳と卵(ちちとらん)」● ★★ 芥川賞 |
|
|
2010年09月
|
作品そのものより、作家である川上未映子さん自身が話題となった観のある芥川受賞作。 あまり芥川賞作品は読まないのですが、ミーハー的な気分で読んでみました。 豊胸手術を受けるのだといって、娘の緑子を連れて大阪から上京してきた姉=巻子39歳。母子2人と未婚の「わたし」が三ノ輪のアパートで過ごす3日間を描いた作品。 久しぶりに会った姉はやせ衰えた感じで、それなのに何故豊胸手術を受けようとするのか。緑子は何故かこのところずっと言葉を発せず、ノートでの筆談ばかり。 乳と卵/あなたたちの恋愛は瀕死 |