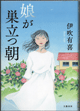| 「娘が巣立つ朝」 ★☆ | |
|
|
伊吹有喜さん初の、新聞連載小説だそうです。その単行本化。 主婦業の傍ら、着物着付け教室の講師等をしている智子(53歳)。 最近気になっていることは、夫の健一(54歳)がいつも不機嫌そうにしていて、ため息ばかりついていること。 その高梨夫婦の元に、就職して家を出ていた娘の真奈(26歳)が、渡辺優吾という青年を紹介したいと連れてきます。 予想どおり、結婚の申し込み。加えて、結婚までの間、実家に戻ってきたいとの申し出。 それから明らかになっていくのは、優吾の両親が共に有名なインフルエンサー=「カンカン」と「マルコ」という変わり種であるうえに、高梨家と渡辺家の歴然とした経済的格差。 また、真奈と優吾の結婚生活観も食い違っているのが明らかになっていく。 一方、健一と智子の夫婦間の軋みも大きくなっていき・・・。 ストーリーは、交互に智子、健一、真奈、それぞれの視点から描かれていきます。 新しく夫婦になろうとする真奈と優吾、長く夫婦を続けてきた健一と智子、その2組を描きながら、夫婦とは何か、を考えようとした作品だろうと思います。 よくあるだろう問題と感じますが、伊吹さんのストーリー運びが上手い。 様々な登場人物を配しながら、そこには様々な要素、問題点があることを浮かび上がらせています。 ただ、もう一つ気持ちが踏み込めず、残念だったという気持ちが残ります。それぞれの登場人物への共感が今一歩だったからでしょうか。 1.一月/2.二月/3.三月~四月/4.四月~五月/5.六月/エピローグ |