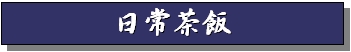
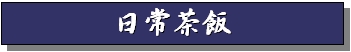
|
まあだかい? まあだだよ。 内田百閒は、長生きした部類になるだろう。 百閒は還暦をきっかけに、毎年誕生日になると教え子たちが摩阿陀会(まあだかい)を開いて祝ってもらった。 (死ぬのは)まあだかいと聞かれて、まあだだよと返事する。 まあだかいは、毎年欠かさず二十一回続いたという。 だからその間、教え子達も二十一年老けたことになる。 それでも、何用あってこの世に生きているのか、怪しいところがあるのが百閒である。 百閒が四十代の時の随筆を引く。 生きているのは退儀である。しかし死ぬのは少少怖い。 死んだ後の事はかまわないけれど、死ぬ時の様子が、どうも面白くない。 妙な顔をしたり、変な声を出したりするのは感心しない。 ただ、そこの所だけ通り越してしまえば、その後は、矢っ張り死んだ方がとくだと思う。 先日本屋で、「一日一文」(岩波書店)を眺めた。 先人たちの言葉を一年分毎日並べたものである。 「人生に潤いや生きる勇気を与えてくれます」と口上してある。 近頃こういうのが多いな。 某月某日のページにあるのが、上に引いた百閒の章句である。 印象を受ける文だが、これだけを切り抜くと何のことだか分らない。 借金の話である。 浮き世から少し離れた姿が可笑しくて、それでいて悲哀を感じるのである。 こんな事を云うと、百閒先生「何を云うか。わかっとる」と云いそうでまた可笑しい。 |
|
|
セキュリティホール再び 鶴亀メールの以前のバージョンに、セキュリティホールが見つかったと聞いて、 そうかと思った。 「バッファオーバーラン」のバグがありそれを悪用すると、 メールを表示しただけで任意のマシンコードが実行できることが判明したという。 ネットに常時接続した状態で作業をするのが普通になった今日では、 一般のアプリケーション・ソフトにもセキュリティホールが存在する可能性がある。 IPA(情報処理推進機構)のセキュリティセンターのページには、 ソフトウェア開発者向けの、セキュリティホールをもたないような プログラミング・テクニックの解説がある。 連絡先のページに、IPAのリンクを張っています。 |
|
|
肩が凝る NHK「ためしてガッテン」で、はじめて「肩が凝(こ)る」という表現をしたのは夏目漱石で、 「門」の中にあるといっていた。 また、この言葉が一般に使われるようになったのは昭和になってからだという。 昔の人は、肩が凝らなかったのかねえ。 昔より今の方が、肩の凝りやすい不自然な姿勢や動作が多いのだろう。 現に肩こりに悩む人は多い。 キーボードをたたいてディスプレイと睨めっこしていると、肩が凝る。 それに比べて、文机(ふづくえ)で巻紙に筆でサラサラと文字を綴るのは、 いかにも優雅で、肩が凝りそうにはみえない。そんな気がする。 しかし、今は滅びて昔あった、お裁縫、針仕事は肩が凝りそうである。 社会全体の生活習慣が、姿勢や身体の動きを規定するという説がある。 江戸時代以前の一般の日本人は、走ることが出来なかった。 走るのは専門職で、その一つに飛脚がいた。 以前時代劇で、本上まなみ主演の「人情とどけます~江戸・娘飛脚」というのをやっていたが、 「飛脚走り」という走り方は現代のとはまるで違う。 武士も走ることが出来たが、腕と足を交互に動かすのではなく、 腕は刀を操(あやつ)るため足とは別の動きをした。 日本人が現在のように走るようになったのは、 幕末から明治にかけて軍隊を西洋方式に変えて以後のことだと思う。 肩こりになるのは、現代社会の生活習慣に関係があるのかもしれない。 |
|
|
新古書店を見てきた 数年前から、新手の商売"新古書店"が繁盛しているという。 これが、出版業界を脅かしている。 著者は、危機感を募らせていると新聞にあった。 古本屋と違い、中身よりも見かけ重視だという。 読んですぐの新品同然なら高値で買ってくれる。 書き込みがあるのは、引き取ってくれない。 本の目利きは不要なので、査定は簡単で早くアルバイトにもできる。 テレビでもコマーシャルを流している。 過日、その"新古書店"を見に行った。 店内は明るく広く、古本屋というより普通の書店のようである。 立ち読みする客もいるし、BGMが流れていた。 書棚を埋める文庫本も真新しく、これも普通の書店の如しだ。 ただし、一つ普通の書店と違うところがある。 ここには、多く並べられる作家と、そうでない作家がある。 多く並べられるのは、読者に捨てられた作家である。 五十音順に並べられたはじめの棚を見れば、赤川次郎の本は多くある。 池波正太郎のは比較的少ない。『鬼平犯科帳』は文庫で二十四巻ある。 まとめて売ればさぞや清々するだろうが、池波フアンはしないと分る。 『鬼平犯科帳』が面白ければ、『剣客商売』も面白いに違いない。 全部読めば大冊になるが、捨てないのだろう。 出版文化を脅かすというが、なあんだぽい捨てられる作家と捨てられない作家に分かれただけである。 コミックだって同じである。よいものは所有して、何度も繰り返し読むもので、 その度に新しい発見があるのが良い作品である。 |
|
|
ひゃっけんと読む 昨日(きのう)一昨日(おととい)と書いたものに、一つだけ但し書きする。 内田百閒の百閒は " ひゃっけん " と読む。 " 閒 " は門に月と書く。 長年来、百聞(ひゃくぶん)と読んでいた人を知っているが、 これは気の毒な勘違いもしくは読み間違いである。 当用漢字略字体を制定し漢字を減らしたためで、 お陰で " 閒 " は漢字から追い出されてしまったのである。 これには、JIS規格も絡んでくる。 PCで百閒を入力すると、かな漢字変換時に<機種依存文字:閒> と文句を云ってくる。 ブラウザによっては文字化けする。 意味不明に化けてくれれば我慢もするが、別の漢字に化けられると迷惑する。 テキストベースのブラウザ Linx では、百閒は " 百訷 " と表示される。 それでわざと " 百間 " と書く人がいる。 月を日と書いても似て非なるものだから、 「我が敬愛する内田百間先生」とホームページに書かれているのを見るとギョッとする。 目ん玉をひんむいて驚いたような内田百閒の顔が目に浮かぶのである。 |
|
|
いやだから、いやだ 「いやだから、いやだ」は、内田百閒が芸術院会員に推薦を受けるが辞退したときの名文句である。 「百鬼園随筆」の解説に川上弘美さんが、その経緯を叙述した多田基:「『イヤダカラ、イヤダ』のお使いをして」を引いて書いている。 辞退は百閒自身ではなく、お弟子で当時法政大学教授だった多田基氏が代理したそうで、 百閒はその理由をたずねられたらメモ通りに答えてくれと、辞退の口上メモを多田氏に渡した。 思わず微笑んでしまった、そのメモを引用する。 ただし現代仮名書きに変えている。また、元もとのメモは縦書きである。 ○格別の御計らい誠に有難うございます ○皆さんの投票による御選定の由にて特に忝(かたじけ)なく存じます されども ○御辞退申したい なぜか ○芸術院という会に入るのがいやなのです なぜいやか ○気が進まないから なぜ気が進まないのか ○いやだから 右(ここは上と読み替える)の範囲内の繰り返しだけでおすませ下さい |
|
|
パロディー(替え歌) 世の中に 人の来るこそ うるさけれ とはいうものの お前ではなし (蜀山人) 世の中に 人の来るこそ うれしけれ とはいうものの お前ではなし (百鬼園) 蜀山人は、大田南畝(1749~1823)の別号であり、百鬼園とは、内田百閒(1889~1971)の別号である。 百閒はこの二首を玄関脇の柱に貼っていたと書いている。 分るように、ふたりは百年を隔てているが、その歌は共鳴して可笑しくもある。 古人のものを読むとは、その人と対話することだという。 だから、私達は五百年前の人だろうが千年の前の人だろうが、 知り合いになることができる。 今日は部屋の本を整理していて偶然に、内田百閒の本を手に取り、蜀山人に出会うことができた。 |
|
|
一寸先は闇 福田康夫官房長官が今日辞任した。年金を未納した引責辞任だという。 これで窮地に追い込まれるのが、菅直人民主党代表だそうで、 「未納三兄弟」と舌鋒鋭く口撃するもつかの間、自らも「未納兄弟」の仲間入りしたのだから、 代表の地位も危ういという。 確かに、この辞任には政治的な意図もあるような気もする。 気の早い人は、未納の閣僚が全員辞めたら大政局になる。 圧勝が予想された7月の参院選の行方にも暗雲が云々(うんぬん)と言っておられるが。 ちょっと待っておくれ。 そもそも、この未納の事実は何処から漏れたのか。 マスコミが暴いたのではない。 ジャーナリズムの役割に、権力を監視するというものがあって、そのような報道を調査報道というが、 これは久しくない。 リークしたのは役所の役人であって、今回は厚生労働省である。 鈴木宗男、辻元清美や田中真紀子のときと似ているじゃない。 タイミングをはかって情報はリークされる。 そしてマスコミは、大々的に発表する。 これを発表ジャーナリズムという。 つまりわが国の社会は、このようにして管理、コントロールされているのではないのだろうか。 だったら、役人とマスコミはグルである。ただし、躓(つまず)く人と交す人とがあるのは、 芸人のスキャンダルと同じである。 「犬も歩けば棒に当たる」という。江戸の犬棒かるたである。 京かるたの「い」は、「一寸先は闇」である。 |
|
|
黄金週間終わる 今年の大型連休が終わった。まずまずの黄金週間だった。 NHKによれば、連休中に起きた交通事故は、1万2602件で、死者は141人。 そんなに多いのかと思ったが、それでも死者は去年より3人少なくなっています、と言っていた。 NHKニュースはテレビではなく、ホームページのビデオクリップを見ている。 PCのディスプレイの中にマッチ箱程度の枠に表示される小さな画面だが、 すきなときに選んで見ることができて便利である。 |
|
|
ウィルスメールの読み方 今ではウィルスメールは差出人を詐称するのが普通になった。 亜種が多いということであろう。 Netskyはアルファベットを一巡して、Netsky.AB が現れている。 ウィルスメールが差出人を詐称することは広く知られているが、 具体的なことは知られていないようなので、実例をお見せする。 まずメールのヘッダーを表示する。Outlook Express では、メールを選択しマウス右クリックでプロパティの詳細を開けばよい。下に示すのは、何日か前に送られてきたウィルスメールのヘッダーである。 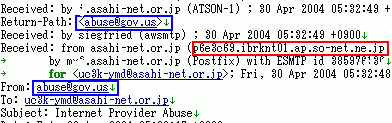
青色で囲った部分が、ウィルスが勝手に書いた差出人のアドレスで、この部分を詐称する。 下の From: は差出人アドレスで、上の Return-Path: は受け取ったメールの返信アドレスである。 詐称するアドレスは、感染したPC内から収集したアドレスを使うが、 この例の abuse@gov.us はたぶん実在しない。ドメイン名の国名 us は米国のことだろうが、 米国のドメイン名には国名が無い。これはウィルスプログラムの作者が考えた拙(つたな)い冗談だろう。 さて、肝心なのはウィルスに感染したPCを所有する実際の送り主である。 その情報が、赤で囲った部分でリモートホストである。 実際はこの後ろにIPアドレスがカギ括弧で記録されている。 ご覧のようにSo-netから送られたもので、アクセスポイントは茨城県だろう。 つまり、So-netのアクセスポイントを通してASAHIネットへ送られて私のところへ来たのである。 これで、茨城県在住のSo-net の会員からのものと分る。 以前に私はHPのトップページに記述していた私のメールアドレスを別のところに引っ込めた。 ウィルスメールが減ってくれればと、はじめは気休め程度の措置であった。 それが功を奏してか激減した。日に百何十通と来ていたのが来なくなった。 もちろん来るのだが、日を追うごとに減った。 そしてようやく、たった一人にまで減った。その最後の人が、上に紹介したウィルスメールの送り主である。 一ヶ月近く送られてくる。どういう規則性で送るのか分らないが、毎日ではないがやって来る。 多いときで日に十何通だから困るほどのものではない。 送られてくるウィルスメールに怒ってみても詮(せん)無きことだと思う。これは以前にも書いた。 だけれども一ヶ月近く感染に気づかないのはどうかと思うし、旅先まで追っかけて来るのには少し迷惑した。 それでこの小文を書いてみたのだが、咎(とが)める気はない。 笑いにしようと一計を案じてみたのである。 書いて果たして送られてこなくなれば、それだけで私は完爾(かんじ)とするであろう。 |
|
|
何と言葉は不自由になった 昨日は、向田邦子の「あ・うん」(新装版)を買って飛行機に乗る。 昭和10年代を描いた唯一の長編小説で 確か、向田邦子が台湾で飛行機事故で亡くなる少し前に出版されたと記憶する。 本の奥付のひとつ前のページに、編集部の注意書きがある。 「この作品の中に、今日からみると差別的表現ととられかねない箇所があります。 しかし、故向田氏の意図は決して差別を容認、助長するものではありませんでした。 また、作品の時代的背景及び著者が既に故人であるという事情にも鑑み、 あえて発表時のままの表記といたしました」 何処に差別用語があるのだろうか。読んでみたが何処にもない。 「あ・うん」ははじめてではない、以前に2度3度読んでいる。おそらく、前に読んだときも 何処にも見あたらなかっただろう。 読む方も差別表現があるなどとは思ってもみないので、見つからないのである。 差別用語のレッテルを貼る人達は違う読み方をするのではなかろうか。 読まずに文字だけを探すのだろう。 してみると、20年前には当たり前に使われた言葉が、今は禁止されるか憚れるということである。 僅か20年で、何と言葉は不自由になったのだろう。 言葉を禁ずれば、差別はなくなるとでも思っているのだろうか。 禁じたおかげで、20年前より差別は減ったか。 キレイな言葉だけではなく時にはキタナイ言葉も必要で、それらが一揃いあって始めて 一流の文明国の言葉であると思うのだが。 文春編集部は、断り書き一つを付けて本文を改竄することなく重版したのは偉い。 これですむのである。 「ハリー・ポッター」の邦訳版は指摘を受けて書き改めたと以前に聞いた。 |
|
Copyright(c) 2004 Yamada, K