99.08.10
子どもの詩
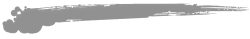
丸谷才一氏の『日本語のために』を新潮文庫で読んだのは中学2年の時と記憶します。その冒頭に「国語教科書批判」と題された章がありました。「中学生に恋愛詩を(読ませよ)」とか、「子供の文章は(手本として)のせるな」とか、僕が毎日授業で聞いてくる内容をことごとく論難してありました。中学生の僕としてもひどく痛快で、それ以来、丸谷説にかなり傾倒しました。
ところで、この本の中で理解に苦しんだのは、小学生の「詩」を大人が改作した実例を挙げて、「これは詩ではない」と喝破した部分です。
牛が水を飲んでいる。
大きな顔を
バケツの中につっこんで、
ごくごく、
がぶがぶ、
でっかいはらを波打たせて、
ひと息に飲んでしまった。
『牛』といふ「詩」がこれでよくなつたつもりらしいが、果してさうなのか。わたしの見たところでは、改作前も改作後もどちらも詩ではないし、単なる文章としては(別にどうと言ふことはない代物だけれど)、手を入れないうちのほうが数等すぐれてゐる。(p.12-13)
とあるのですが、これが「詩ではない」とは、意外でしたね。
単に下手だ、との説明なら納得できるが、改行もしてあるし、一応は詩ではないのかな……?
要するに、そのころの僕の理解では、「詩」とは(1)こまめに改行がしてあり(2)美しい場面とか子どもらしい感想とかを詠み込んである文章、であればいいのでした。ところが、それは誤りらしい。
詩と詩でないものとの見分け方については、筆者の言及はありませんでした。テーマがそれるのを避けるためかもしれませんが、詩の何たるかを知らぬ中学生としては途方に暮れる。
そこで、一つの「判別法」を自分なりに考案しました。それは、
「とにかく改行をなくして一文をつなげてみて、ふつうの文章と区別が付かなくなるものは詩でないと考える」
という方法です。これは、わりと有効な判別法でした。
現在書店にある問題集から、一つ例を出します。
あたたかいえんがわ。
ぽかぽかした日が、
わたしを、
ふくらますように照る。
ざぶとんの綿も、
ふわり、
うきそうに軽い。
ふくらんだざぶとんに乗ったら、
ふわふわとおどっているようだ。
(鷺書房『国語の勉強 小学6年』p.45)
これを改行せずにつなげると、
「あたたかいえんがわ。ぽかぽかした日が、わたしを、ふくらますように照る。ざぶとんの綿も、ふわり、うきそうに軽い。ふくらんだざぶとんに乗ったら、ふわふわとおどっているようだ。」
となります。「わたしを、ふくらますように照る」の部分にかすかに詩情が感じられないでもないけれど、全体として、まあ凡庸な、修飾語過剰の文章ですかね。「ふわふわ」などとオノマトペで飾り立てれば詩になるわけでもない。
ついでに、僕自身の文章をお目に掛けます。文中にある「バレン」(馬楝)は版画で紙をこするのに使用する道具です。
バレン
三年三組 飯間浩明
ここに、図工のとき使った、一つのバレンがある。
ふと、うらを見ると、
青いえのぐが、一めんにうすくついている。
こんなについてて、かわいそうだなあ。
赤いえのぐも、ちょっぴりついている。
ないているみたいだ。
ここに、図工のとき使った、一つのバレンがある。
おもてを見ると、
竹のかわに、茶色いなみだのあとがある。
おもてに、えのぐがついている。
竹のかわのむすびめが、ぼくをにらんでいる。
「こら、やったな。」と、
おこっているみたいだ。
(太田南小学校『つくし』創刊号 p.79 1977.03)
書き写しながら、顔から火が出ますな。「〜ているみたいだ」と直喩でまとめるところなんぞは、先ほどの「ふわふわ」の詩もどきとそっくりだ。
なぜ各連の1行目が欧文直訳体ふうなのか、なぜ無理矢理バレンを泣かせたいのか、今ではまるで分かりませんが、詩でないことは確かであります。
▼関連文章=「駄文か? 金田一氏の文章」
|