99.05.17
人をばかり
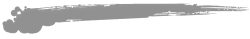
昔、服部四郎という言語学者が、「ことばの間に〈切れ目〉があるかどうかは、ひっくり返してみれば分かる」といったようなことを言いました(「附属語と附属形式」『言語学の方法』 p.461〜)。
たとえば、「人ばかりを」「どこかへ」は「人をばかり」「どこへか」と言えるので、「人|ばかり|を」、「どこ|か|へ」は別々の単語だと。
ところが、このことを聞いた人が、「『人をばかり』なんて言わない、『どこへか』なんて言わない」と異議を立てました。たしかに、若い世代では使わないのでしょうね。僕も、使用語彙ではないかもしれない(聞けば分かるけれど)。
でも、ときどきは目にします。
でたらめ言うなよ! 昨日までほとんど意識不明でうわごとをばかり言っていたくせに……(米川正夫訳『罪と罰』新潮文庫)
井戸の水も浴びずに、すぐ身体を拭いて着物を着て、さっさとどこへか行ってしまった。(夏目漱石『こころ』新潮文庫)
のように。ただし、ちょっと古い言い方です。
昔の(明治期の)小説などを見ると、今とは違った順番で助詞が並んでいることがあります。たとえば二葉亭四迷「浮雲」からいくつか引きますと、
〔……〕其のお政の半面を文三は畏らしい顔をして佶と睨付け何事をか言はんとしたが……(『浮雲』上篇 p.110)
「〔……〕去りとはまた苦々しい」ト何処{どこ}のか隠居が菊細工を観ながら愚痴を滴したと思食せ(『浮雲』二篇 p.10)
などは、今では「何事かを」「どこかの隠居」のように言うと思います。
そのほか「浮雲」第三篇に「本田さんが何とか思ひなさらアね」(今なら「何かと」)、「けれども、お勢は手にだも触れず、」(今なら「手だにも触れず」)のように言っている個所もあります。
若松賤子訳「小公子」(明治20年代に雑誌連載)の初めのほうを読んでいたら、「いつもになく」なんてことばが出てきました。
ホッブスは丁度新聞を読んでゐた処でしたが、セドリツクはいつもになくまじめ顔に側へ寄りました。(「女学雑誌」第229号 p.17)
ここは、「いつにもなく」でないところが当時らしいわけです。
▼関連文章=「役割をしかもたない」
|