98.08.01
女にしてみたい
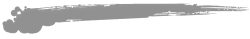
岩波文庫版のスタンダール作『赤と黒』(桑原武夫・生島遼一訳)を読んでいたら、主人公ジュリアンにレナール夫人が初めてほのかな恋心を抱く場面で、こういう文章に出会いました。
子供たちに対する不安がまったく消え去ったこの時になって初めて、レナール夫人はジュリアンの無類の美貌に打たれたのだった。女にもして見たいようなみめかたちや、おずおずした様子も、自分自身極端に臆病な女にとっては、ちょっともおかしくは見えなかった。(『赤と黒(上)』岩波文庫 p.60)
ジュリアン青年が「女にもして見たい」ほど美しかったということで、なんとなく倒錯的な表現だ。これは別の訳(小林正・新潮文庫)をみても「女にしたいような顔だち」とあるので、意訳ではなく原文にそうあるんでしょう(追記参照)。
ところで、これに似た表現が、古典の「源氏物語」にあります。光源氏が、ある雨の日に友だちと集まって雑談をしていた。ラフな格好で、衣服の紐も結ばずに、物に寄りかかって横になっている。灯に照らされた彼の様子がこう描れている。
御灯影{ほかげ}いとめでたく、女にて見たてまつらまほし。(帚木巻)
「女にて見たてまつらまほし」というのは、「源氏物語」によく出てくる表現です。機械的に訳すと、「女で拝見したい」。ちょっとこれでは分かりにくいので、いろいろ説が分かれています。
小説家の訳では、「女の身になってお見上げ申したらいっそうそのあでやかさに恍惚とすることであろう」(円地文子訳)という。また一方、「用例からみると、源氏を女性にしての意」と解する説(日本古典文学全集)もある。説が割れているんですね。
こういうとき、冒頭の桑原・生島訳のような文章に接すると、後の説のほうがいいような気がしてくる。「自分(見る側)が女になる」というのは、どうも不自然な感じがします。「源氏物語」でも、自分ではなく相手を女にしてみたい、と言っているんでしょう。要するに「男にしておくのはもったいない」というわけです。
「女にもしてみたい」というのは、『赤と黒』の翻訳文にかぎらず、現代語ではときどき使われる表現です。それが「源氏物語」のころから存在したのだと考えたいと思います。
追記 原文にあると考えていたところ、実は「女にもして見たいようなみめかたち」の原文は“La forme presque feminine de ses traits”(ほとんど女性的といっていい彼の顔の形)であるとのご指摘をいただきました。古代・現代の日本語だけでなく、フランス語にもあるのだろうと推測しましたが、それは無理だったようです。(1998.11.03)
追記2 ところで、次のような例をみると、僕にもまた迷いが生じます。
「兵部卿宮ぞいといみじうおはするや。女にて馴れ仕うまつらばや、となんおぼえはべる」(手習巻)
これは紀伊守が匂兵部卿を評して言ったことばですが、「こちらが女となってお仕えしたい」としか解せません。日本古典文学全集など、他の個所では「相手を女にして」と解する説も、ここだけは「こちらが女となって」の意に解しています。(1999.06.02)
|