02.09.26
高円寺あたり
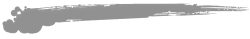
題名に引かれて、西谷祥子著の漫画『高円寺あたり』第1巻(双葉文庫名作シリーズ、2002.04)を買いました。中野・高円寺あたりは僕の近所であり、なじみのある街並が出てくるのではないかと興味がわいたからです。
東京の大学に入ろうと、仙台から上京しておばさんの一家に居候しながら高校に通う少女の話。「うんと勉強してすてきなOLになって自立」したい主人公と、意外に保守的な友だちや周りの人々との生活を明るい色調で描いています。
「名作シリーズ」と銘打たれている以上は、むかしの作品だろうと思われました。絵柄からも、ちょっと前の漫画という印象を受けます。もともと漫画をあまり読まない僕には、この作品は記憶にありませんでした。
文庫の後ろのほうを見ても、いつの作品かということは書いてありませんでした。よくあることですが、このようないい加減な編集は困ります。
それならば、読みながら、これがいつの作品か推理してやろうと思いました。とりわけ、ことば遣いをヒントにして当てることができれば面白いと思いました。
たとえば、こんな個所です(ふきだしの代わりにかぎ括弧を用います)。
「あーあ/大失敗!!
お母さんに/こってり/おこられる」(p.19。おばさんの娘のせりふ)
「うふ/10年も/昔じゃね―――
てんで/むりよ!」(p.23。主人公のせりふ)
「こってり」は、今の若者でもふつうに使うでしょうが、「こってりした(脂っこい)ラーメン」のような使い方が多く、「こってり怒られる」という言い方はあまりしないだろうと思います。やはり漫画の『ドラえもん』で、のび太くんが「こってりおこられた」と言っていたのが記憶にありますが、ちょっと古風という気がしますね。
「てんで」も、「てんで話にならない」などという言い方は、一定以上の年齢の人のものではないでしょうか。「てんで しけてんだ」というのは、宮城まり子の歌「ガード下の靴みがき」(作詞・宮川哲夫、1955年)の間奏でのせりふです。
作者は何年の生まれだろうと思って、うしろの作者紹介を見ると、「1965年、「春子のみた夢」でデビュー」としか書いておらず、あまり参考になりません。ただ、この漫画が1965年以降のものであることは分かりました。
ほかにも、今ならあまり言わないだろうと思われる女の人のことばが拾われました。
「そうよー
あっちも/ハンサムさん/だけど」(p.38。主人公のせりふ)
「徹――っ/ごはん/だってば」
「うるっせー/くいたく/ないんだ/よ――っ」
「オンス/かしら」(p.117。おばさんのせりふ)
「ハンサムさん」は、手塚治虫の初期の漫画で目にした記憶があります。また、「オンス」は辞書にありませんが、もちろん「メンス」の男性版ということでしょう。
どうも、もうひとつ決め手がありません。ところが、この作品では主人公が何度も隣町である中野を訪れ、街の風景が描かれます。「中野ブロードウェイ」(1966年開館)、「サンプラザ」(1973年)なども登場します。
「サンプラザ」のところでは、道行く人が「あれが有名なサンプラザよ」「知ってる! ヒロミやヒデキが公演するとこでしょー」と話し合っています。
ことば遣いよりも、このような世相にかかわる徴証から、漠然と、1970年代後半の物語ではないかと考えました。そのころに書かれたとすれば、「女性の自立」をテーマにしたこの漫画はきわめて先駆的な作品ということができるのではないでしょうか。
最後にインターネットで調べてみると、実際はどうやら1980-81年の作品というのが正解のようです。ことばから推理しようという僕の試みは失敗に終わりました。「ことば探偵」はなかなかむずかしいようです。
|