01.04.01
「あめつち」を作る
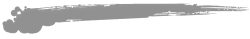
いろは歌……と言っても、今や若年層の人は全部唱えることができないようです。かくいう僕の世代もすでにそうらしい。高校時代だったか、「いろは」を全部言えるかどうかを何の気なしに友人に聞いてみたところ、「いろはにほへと」まではいいとして、そこから先はどうもおぼつかない人が多かったように記憶します。
僕自身は、「いろは」は小さいころから言えました。というと自慢をするようですが、「いろは」はそれこそ「いろはの『い』」で、日本語を話す以上は当然基礎になるものと思っていました。むしろ友人が知らないことが衝撃でした。
今は「いろはの『い』」という言い方さえもなくなり、そういうときには「基本の『き』」と言うようです。この言い方はいつから?
それはともかく、この「いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせす」という歌はすでに11世紀の文献にも見えています。「いろは」が成立する以前にも、「たゐに」の歌や、「あめつち」の詞といったものがありました。
「あめつち」は、平安時代の初めごろ、世俗によく唱えられた詞のようです。
|
あめ つち ほし そら
やま かは みね たに
くも きり むろ こけ
ひと いぬ うへ すゑ
ゆわ さる おふせよ
えのえを なれゐて
|
(天 地 星 空)
(山 川 峰 谷)
(雲 霧 室 苔)
(人 犬 上 末)
(硫黄 猿)
|
初めのほうは、「天・地・星・空」と、意味のつながりがありそうですが、だんだんあやしくなってきて、最後の方の「おふせよえのえをなれゐて」のあたりはどういう意味だか、研究者の意見は必ずしも一致していません。まあ、大した意味はないようです。
何でこんな中途半端なものが広まったのでしょうか。
意味のある2音のことばを、音に重複がないように列挙していって、どうしても余った音を適当に並べておく、というようなことは、だれでも簡単に出来そうです。こんなものが「うまく作ったなあ」と思われ、人々に喜ばれたんでしょうか? 当時の人々は、それほどレベルが低かった?
「あめつち」を作るためには、どういう苦労があるのか体験しようと、僕も実際に作ってみました。
気をつけるべきことが1つ。「あめつち」の詞は、「えのえを」とあるように、ア行の「え」と、ヤ行の「江」を区別しているらしい。これが作られた当時の音韻を反映しているのでしょう。ですから、僕もア行の「え」とヤ行の「江」を区別して作りました。
出来上がったのは次のような文句です。
|
くろ しほ あゐ なみ
おき はて えひ つり
むら さと をか たけ
にれ その ぬま わせ
いへ やね うす もち
ふえ こゑ よる ゆめ
|
(黒 潮 藍 波)
(沖 果 海鷂魚 釣)
(村 里 丘 岳)
(楡 園 沼 早稲)
(家 屋根 臼 黐)
(笛 声 夜 夢)
|
初めは「はる・なつ・あき・ふゆ……」などと並べて行ったのですが、やっぱり最後の方が意味不明の文字の羅列になってしまいます。「はる」はだめだな、「よる」ならどうかな……というふうに、1字ずつ変えて行くうちに、いつしかこのような形にフィクスしました。
だいたい次のような意味を込めたつもりです。
「黒潮の流れる沖では魚のエイを釣っている。一方、村里には楡の園があって、沼のほとりでは早稲が稔っている。家々では餅つきをし、笛を吹いたり歌ったりしている。夜には疲れ果てて、夢を見ながら眠るのであった……」
「えひ」(海鷂魚)の「え」はア行かヤ行か分からないのですが、強引にア行と見なしておきました。こういう点にはちょっと苦労しましたが、全体を作る所要時間として、まあ1時間ちょっとというところでしょうか。僕は喫茶店でお茶を飲みながら、紙ナプキンの上で文字を書いたり消したりしながら作りました(怪しい客ですな)。
「あめつち」の詞では、後半に意味の通らない部分がありますが、僕の「くろしほ」の詞(?)は、一応、最後まで2字の清音の名詞で通しています。
たしかにそれほど簡単ではなかったけれど、何日もうんうん唸って作るほどのものでもありませんでした。まあ、おそらくだれでもちょっと時間をかければユニークなものが作れるのではないでしょうか。
「あめつち」は、ことば遊びの作品としてだけ考えると、どうしてこのような不完全なものが社会的に流通したのか分かりません。おそらく作者は、ことば遊びを目的とはしていなかったのでしょう。彼の目的は、「これ以外に日本語に音はない」ということを示すことにあったのでしょう。周りの人を集めて、
「ここに並べてある以外の日本語の音を探してごらんなさい」
「えーと……、そういえば、見つかりませんね。すごいなあ」
などという会話を交わしていたかもしれません。
今ならば、五十音図があるため、ちっともすごいと思わないわけですが、当時は日本語の音図のたぐいはなかったと考えます。何もないところから「あめつち……」を作り出したのが素晴らしいのです。
仮に、その当時に音図があれば、それを目の前に置き、いくらでも凝ったことば遊びの作品を作ることができるはずです、ちょうど僕がやったように。
亀井孝氏は、「あめつち」の作者は「音図を知っていただろう」ということを書いており(「「あめつち」の誕生のはなし」)、僕の想像と整合しません。しかし、実際に音図を前に置いて「くろしほ」の詞を作った経験からすると、もし音図があれば「あめつち」よりは良いものができたはずだと思うのです。
●この文章は、大幅に加筆訂正して拙著『遊ぶ日本語 不思議な日本語』(岩波アクティブ新書 2003.06)に収録しました。そちらもどうぞご覧ください。
|