00.11.29
待望の第2版を手に取る
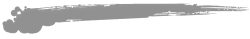
『日本国語大辞典』(小学館)第2版の第1巻目「あ―いろこ」が28日に発売されました。書店から連絡を受け、さっそく17万いくらをたずさえて参上、全巻分の代金一括払いを済ませました。当分は、倹約して生活しなければなりません。
喫茶店に入り、待望の第1巻をぱらぱらとめくりました。そこでいくつか気のついたことを……。
★装丁
ビニールのカバーのサイズがゆるいのが気になる。これは、年月とともにビニールが縮むことを見越してのことでしょうか。紙がたいへん薄いのも、初版20巻本の紙質に慣れている僕はややとまどいを覚える。何度も引くうちに破れやせんかな。内容を凝縮して1巻に収めているから、こうなるのでしょう。
★あき【安芸・安芸】
広島県の昔の地名。同じ漢字表記を2回繰り返して記しているので、どういうことかと不審でした。家に帰ってから初版を見ると「【安芸・安藝】」と書いてあります。「芸・藝」は、常用漢字表では同じ字ということになっているので、初版の漢字表記自体重複しているのですが、第2版では、旧漢字をコンピュータで一括して新漢字に変換したか何かで、「安芸・安芸」という無意味な繰り返しになったのでしょう。
★あじ-あ・う【味】
初版よりもさらに古い使用例が載っています。初版では1656年の書物に載っていた例が挙げてありますが、第2版では鎌倉末期の書物の例が出ていて、一挙に300年以上も初出がさかのぼりました。大江健三郎の例については以前挙げました。
★あじゃぱあ
新しく載ったことばの例。「俳優、伴淳三郎のつくった昭和二〇年代の流行語」。井上友一郎の1953年の小説の例が添えてあります。初版で載せることは時期的に可能だったはずですが、初版では流行語のたぐいは無視したのでしょうか。
ちなみに、「いけてる」は第2版でも載っていません。まあ、当然か。
★あつまり-つど・う【集集】
「増鏡」にあることば。初版にも載っていますが、第2版では漢字表記が添えられました。そこで、このことばが重言であることが一目で分かるようになりました。
★あんぴん-もち【餡餅餅】
これは、初版では「あんびん-もち【餡餅】」で、方言語彙としてしか出ていませんでした。今回は雑俳から用例を採り、見出しも「あんぴんもち」の形にしてあります。
漢字表記から分かるとおり、「ぴん」も「もち」も餅のこと。これもやはり重言の例でありましょう。
ついでに、同部首3連続の例でもあります。
★いまいち【今一】
第2版で新しく載った俗語の例。以前書いたとおり、僕は、「1970年代末〜80年代初め」にできたことばだと思っていましたが、第2版では中島梓「にんげん動物園」(1981年)の例を出してあります。1981年ならば、僕の感じとぴったり合います。1980年に初めて聞いたという証言をもらったこともありますが、探してみれば、1981年より古い例が見つかるかもしれません。
しかし、中島梓「にんげん動物園」とは。このような作品からも広く用例を採っているんだなあ。この本、僕も持っていましたよ。山藤章二氏の文章入りイラストレーションが添えられた楽しいエッセー集でした。部屋が狭くなったので、実家に送ってしまいましたが、たとえ部屋が狭くなろうとも、本というものは簡単に手放すべきものではありませんね。
部屋が狭いといえば、全部で13巻になるこの辞典、いったいどこに置けばいいんでしょう。はっきり言って、そんなのを置く余地はないんです。
追記 新潮社の小駒勝美氏より、オイチョカブの用語として「いまいち」を1970年ごろに聞いたとの証言をいただきました。次の札が欲しいときには「いまいち」、もういらないときは「いらじ」と教わったということです。「いまひとつ」の意味で「いまいち」と言われているのを聞いたとき(いつごろかははっきりしない)、「オイチョカブ用語の応用だな」とお思いになったそうです。(2000.12.02)
|