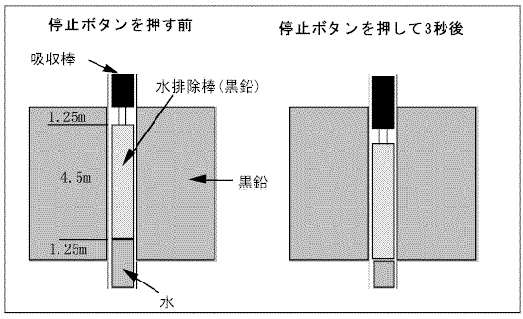
イメージデータベース 5
90/7/29 作成
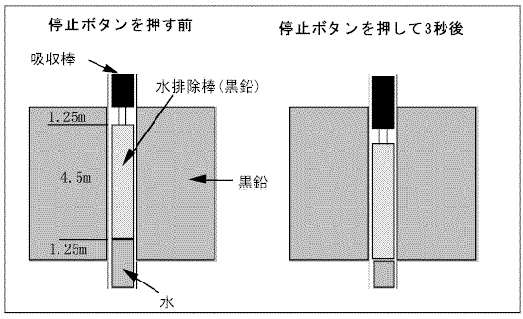
●チェルノブイリ型原子炉は黒鉛減速チャンネル型炉といわれるもので黒鉛のブロックが積み重ねそのなかに1,600本の圧力チャンネル管(燃料棒集合体を中心に周囲を冷却水が流れる管)と 中性子を吸収する制御棒が差し込まれる構造になっている。制御棒は全部で211本、長さは6.2m。吸収棒はホウ素。その下に黒鉛棒をぶら下げて運転中の中性子減速を促進させる設計になっていた。
●制御棒の構造上、黒鉛製の水排除棒が1.25メートル短いため、緊急停止ボタンを押して制御棒の一斉投入をすると中性子を良く吸収する水が押しだされるため、下部でかえって核反応が増える結果となる。この結果ボイドが 増して正のボイド効果のためますます核反応が進み、破局的な出力激増をまねいた。これを「ポジティブ・スクラム効果」という。
●1,600本の圧力チャンネル管でも核反応増えて水蒸気の気泡が増えると中性子を良く吸収する水が押しだされ、核反応は暴走を始める仕掛けになっていた。これを「正のボイド効果」という
●1986年4月26日発電所外部からの電源が切られた場合に緊急ディーゼル発電装置が起動するまでの間、発電主タービ
ンの慣性で発電を継続し、これで緊急炉心冷却装置のポンプが動かせるか確認実験をしている間にの事故は生じた。運転員の勘違いで緊急炉心冷却装置のポンプ
の自動起動を解除し、手動で低負荷運転をしていた。キセノンによる中性子吸収効果があることに気が付かず、制御棒を引き上げすぎて炉内にある制御棒の本数
が少なくなっていた。 実験に入って炉内の水循環量が極端に減ったときに急な出力上昇があった。これに気がついた運転員が200本の制御棒を一斉におとした直後に暴走は始まったのである。
実験に入って炉内の水循環量が極端に減ったときに急な出力上昇があった。これに気がついた運転員が200本の制御棒を一斉におとした直後に暴走は始まったのである。
以上は国際原子力機関(IAEA)に報告されている。
事故を起こしたチェルノブイリ原発(B)はキエフ市北方100kmのロシアとの国境線近くのウクライナにある。Google Mapで見ると原発周辺の放棄されたプリチャピ市(C)、チェルノブイリ村(E)のゴーストタウン、および汚染された「赤い森」(D)が見える。 原発の右下に見える細長い池は冷却水を自然蒸発で冷やす放熱池である。池の真ん中には仕切り土手があり、放流水と取水が交じり合わないように設計されております。事故後もこの水は環境と隔離されたままです。
長期間放置されていたため、破壊された原子炉を覆う放熱池の中仕切り土手には鳥の糞から発芽した樹木が生長しています。
事故を起こした最新の4号炉は左端にあり、破壊された炉を覆うコフィンは老朽化し、崩壊の懸念があるといわれますが。この航空写真撮影時はまだ手付かずのままのようです。
スリーマイル島原発事故に関してはメモ1084参照。
Rev. July 3, 2014