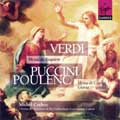
Virgin Classics
7243 5 62322 2 8
Messa da Requiem/Verdi, Messa di Gloria/Puccini, Gloria/Poulenc //Michel Corboz
さぁ、初っ端から期待を外そう。3大レクイエムの一つ、ヴェルディ(Giuseppe Verdi:1813-1901)の「レクイエム」に、プッチーニ(Giacomo Puccini:1858-1924)、プーラン(Francis Poulenc:1899-1963)の「グロリア」を加えたカップリング2CD。
ただの一度もまともに経験したことはないが、ミサの平常時の一般的な構造は次のようなものであるらしい。
1:Kyrie(キリエ) 哀れみの賛歌
2:Gloria(グロリア) 栄光の賛歌
3:Creado(クレド) 信仰宣言
4:Sanctus(サンクトゥス) 感謝の賛歌
5:Agnus Dei(アニュス・デイ) 平和の賛歌
レクイエム・ミサにはグロリアが含まれず、代わりにDies Irae(ディエス・イラエ:怒りの日)やLacrimosa(ラクリモーザ:涙の日)が加わるらしい。おお、なるほど。
ルネサンス以降、一人の作曲家が通しで一つの楽曲にまとめ、自らの作品として発表するようになった。その場合の引用は一部であったり、全部であったり、膨れていたりといろいろ。近代に入ってからは式典曲としての機能は失われ、純粋に作品として独立したものも存在するようだ。
ヴェルディといえば「椿姫」や「アイーダ」などのオペラ作曲家として極めて著名かつ第一人者であるわけだが、イタリア語わからんからもどかしい。その点、レクイエムはラテン語だし、どうせ歌っている内容は決まりきった典礼文だから、“愛読書が聖書です”という人以外には正直どうでもよいもの。レクイエムとしては劇的でオペラが本業たる作曲家の本領発揮、ディエス・イラエの弩迫力の太鼓の連打が極めて著名で、CMからアニメまであちこちに引用されているのを聞くことができる。独唱を含めて歌唱が全体として非常に艶やかなので最初は面食らいますが、刷り込まれた固定観念を打ち破る良い例でもある。初演は1874年、作家マンゾーニの一周忌にベネツィアのサン・マルコ教会で。
ダイナミックレンジが広いので、CDで聴くよりもライブで聴くべきなのだろうが、なかなか機会はないな。
プッチーニは同じくイタリアのオペラ作曲家として「マノン・レスコー」「トスカ」あたりで有名。「Messa di Gloria」は1880年初演のグロリアを中心にした45分ほどのグロリア・ミサ曲一揃え。ヴェルディほどオペラチックではないが、やはり歌中心。
プーランクはフランスの現音作曲家。晩年に若干の宗教曲を残している。時代の差もあるだろうが上記に比べて遥かにエレガントでクール。同じラテンでも差は顕著である。
まぁ、プッチーニやプーランクはいずれ別項で。そのうち、法要における読経、微妙な世俗化が気になるが、例えば比叡山の根本中堂を揺るがすあの凄い声明なども取り上げねばなるまいな。

IGLOO+
IGLO152
Le pavillion des passions humaines/Julverne
ワロン・ベルギーの室内楽団、1999年録音のジュルベルヌの近作、『人間的情熱の館』。主宰者ジュノー・ジリ(Jeannot Gillis)による解説にもある通り、タイトルはとあるレリーフ作品を指している。ジャケ絵にもなっているレリーフはフランスの彫刻家ランボー(Jef Lambeaux:1852-1908)が製作し、ブルュッセルのサンカントネール公園にあるビクトル・オルタ設計の新古典主義の寺院に収蔵されたもの。1899年、死、戦争、自滅を象徴した裸体が当時としては淫らに絡み合う大理石の彫刻は、アカデミーの酷評を受け二日後には建物もろとも封印されて公開停止に至ったという曰くつきの逸品。ライナーではそれ以来公開されていないと記されていますが、つい最近ようやく見れるようになったらしい。
ユニヴェール・ゼロのディルク・デッシェーメカー(Dirk Descheemaeker:クラリネット)とミシェル・ベルクモン(Michel Berckmans:バスーン、ホルン、オーボエ)を加えピアノ+管弦楽の10人編成(女性3人)とほぼ固定化された陣容で、典雅とアヴァン・ガルドの共存した室内楽を奏でる。最長7分ほどの全12曲。さり気ない変拍子の組み合わせ、技巧的にも難易度の高い楽曲を生楽器のみで優美にかつ上品に演ずる。冷たい香気のような抑制されたノスタルジー、惚けた滑稽趣味が最大の持ち味。
プッチーニのオペラ「トスカ」の一部編曲に加え、ラストはルドルフ・ジーツィンスキー(Rudolf Sieczinski:1879-1952)の「Wien, Wien, nur du allein(ヴィーン、ヴィーン、君こそ…)(日本題は“ウイーン、我が夢の街”)」のカバー。
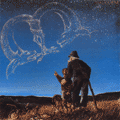
Hexagone
GRI191282
Nous sommes chanteurs de sornettes/Malicorne
フランス西部の急進派民謡、マリコルヌ四作目。1,2,4作目は正式には『Malicorne』がアルバムタイトルであるが、それでは区別がつかない。ということで通称『星』。CD屋などでは一曲目の曲名で特定することもあるようだ。その場合のタイトルは『我等はしがない歌謡い』。
電気ベース専任が加わってアンサンブルは分厚く技巧的になった。歌詞の多くはシャンソン(中世のフランス語世俗歌曲を指す)から取られたもの。一曲、ビクトル・ユゴーが紛れておる。各曲に歌詞と共に簡単な出自の記載があるのだが、楽曲もトラディスィヨン・ポピュレール(民間伝承)のアレンジが5割ほどを占める。もっとも古楽器による演奏がいきなりダイナミックに電化され明解なリズムを叩き出す展開をもつ長曲や、オルグ・ポズィティフ(Orgue Positif)といわれる古式オルガンとストリングズ系シンセの絶妙なアンサンブルが光る現代的なクールさが売りであることは間違いないだろう。滴り溢れる冷たい情感と洗練された風土性が見事に絡み合っている。

ユニバーサル
/Decca UCCD-7115
2002
Water Music, Royal Fire Works, etc/Händel //George Szell
1727年にイングランドに帰化したドイツ・バロックの名匠ゲオルク・フリードリッヒ・ヘンデル(Georg Friedrich Händel:1685-1759)の代表作ともいえる管弦楽曲。「水上の音楽」は多分誰でも聞いたことのあるメロディだろう。イングランド王ジョージ一世のテムズ川での舟遊びのために作曲された20分弱の佳曲。初演も実際に川上だったらしい。
後半「王宮の花火の音楽」も“あぁ、これこれ”レベルの、あちこちでイージーリスニング化されている著名曲。その他、本業であるオラトリオ、オペラの抜粋がまとめられた国産廉価盤。
とにかく優美で晴れやか、気持ち良い滑らかなメロディで紡ぎ出された典型的なバロック音楽。元々、バロックは“いびつな真珠”の意で、中世末期やルネサンスの楽理的均整から逸脱した破格を意味する。ヨーロッパ文明の最初の爛熟期とも重なって、情緒的な感情表現がもてはやされた時代でもある。
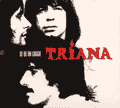
Gong
5046761792
Sé de un lugar/Triana
さて、古典ばかり取り上げていると客がいなくなりそうだ。そこでロック・アンダルシアですよ、お客さん。2003年の6枚組BOXセットに続き、今度はリマスター・コンピ2CDにDVDの三枚セット。DVDは74年から81年ごろの音楽番組への出演映像をまとめたTVドキュメンタリーとして製作されたようだ。55分。ライブ、スタジオ、TV出演時の演奏場面に加え、プロデューサの回顧、同業者の賛辞、セビージャのバル(Bar)でくつろぐお三方、ヘスス・デ・ラ・ロサの交通事故死を伝える新聞まで盛りだくさんな内容です。
う~ん、まいった。
トリアナってアンダルシアでは人気あったのだねぇ。トップ・スターの扱いでっせ。
基本はトリオ編成。曲によってはサポート的に電気ギター+電気ベースが加わる。大半の曲はヘスス・デ・ラ・ロサによるもの。
Jesús de la Rosa Luque ; teclados y voz(鍵盤と歌)
Eduardo Rodriguez Rodway ; Guitarra española(フラメンコ・ギター)
Juan José Palacios Orihuela "Tele" ; batería y percusión(ドラムと打楽器)
ベースがいないのが気になるが、フラメンコ・ギターの低音弦が通奏低音の役割を果たしているよう。悪役面のロドリゲスさん、足でタップしながらギターを弾いております。二拍子+三拍子系の(フラメンコ)リズムを叩くフアン・ホセ・パラシオスの太鼓もタイトでいながら小技が効いている。サポートのアントニオ・ペレス(Antonio Perez)を含め、テクニックは上々、癖のあるロサの歌は完全にフラメンコのカンテですが、非常に説得力のある力強さと独特の哀愁が入り混じった努めて風土性に溢れたもの。非常に巧いと思います。
タイトルは『お馴染みの場所』 全編スペイン語のみ。プロデューサーの長広舌ぐらい英語の字幕入れてくれよぅ。
DVDはPAL、リージョン2なのでプレーヤーによっては見れない(私はPAL対応のYAMAHA DVD-S540を使用)かも。パソコンなら(私ので見れるくらいだから)普通OKのはず。
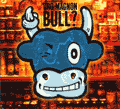
Lowlands
Low 008
Bull?/Cro Magnon
ベルギーの現代室内楽団、クロマニョンの2ndアルバム。ドラムレスでベースx2、管楽器1、弦楽器3(うち1は電気ギター、鍵盤兼任)というこれまた編成の妙を尽くしたけったいな計6名編成だ。ゲストでドラム、ホルン、チェロ、金管、マリンバ、歌などあり。ドラムといってもいわゆるポップロック調のドラムスではなくて太鼓。複数の弦楽器のピチカート奏法で複雑怪奇なリズムを作り出し、ノスタルジックなメロディが被さる。
奏でられる艶やかな弦楽器の重奏と妙なファンクベース、迷宮のような12音メロディを捏ね繰り回すサックス、ジャズなのか正調美麗室内楽なのか、はたまた土着舞踏民謡なのか、謎だ。極めて経験のない音楽であるが非常によく出来ている。偏執的なまでの執着と突っ込みと凝りよう、静と動のバランス、諧謔とお茶らけ、軽妙でいて華麗、ミニマル傾向は明らかだが+αの不思議な滋味も加わって、最後まで引っ張られてしまう。
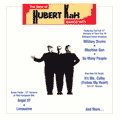
Curb
D2-77260
Dance hits/Hubert Kah
かつてのヒット曲の数々の、拡張舞踏版、12吋シングル版で構成された米盤格安コンピレーション。「Angel 07」の拡張版は前半が英語版で後半にドイツ語版が接続されております。「So many people」などもなかなか絶望的で政治的な歌詞なのに、こういうので踊れるというのもある意味凄いな。
「So many people」
とても多くの人が死んでいる
かつては太陽の下で皆が生きていけるという夢を持っていた
とても多くの人々に
明らかにするには時間がなさ過ぎる
とても多くの人が死んでいる
かつては太陽の下で皆が生きていけるという夢を持っていた
とても多くの人々に
自らが為したことを明らかにするにはもう時間がない
時限爆弾にキスをしながらの
個人的な戦争
1988年10月26日のヘッドラインです
チャド内戦で新しい動き
300人以上が死亡しました
IRAは警官による殺人を申し立てました
些細なことだ
ぼくにとっては
とても多くの人が戦争に行き
とても多くの人が承服できない犯罪に手を染める
でも、ぼくは最終的には勝利を得るだろう
あの新聞売りの少年を知っているか
街路の寸詰まりで店を構えていた
そりゃ、思い出せないか
彼はロープの末端に舞台を得た
勇敢で一人前の兵士のように吊るされて
ヨハネスブルグ発:
火曜日、催涙ガスと警棒で武装した警官隊が暴徒と化して、
水曜に予定されている人種隔離政策議会の国政選挙に反対する学生と衝突しました
些細なことだ
ぼくにとっては
とても多くの人が戦争に行く
歌詞は英語。ドイツ語は英語の親戚ですが、ドイツ人は英語があまり得意ではない。おかげでどの程度まで慣用句を使っているのか判断するのが難しい。まぁ、端的に言ってしまえば、ドイツ語に代表されるゲルマン語とノルウェイあたりのバイキングが使っていたノルド語にフランス語やラテン語を取り入れて、徹底的に文法や動詞変化、慣用句を簡略化したのが英語であって、おかげで前後関係や筆者の人成り、ジェスチャーや顔色、イントネーションや発音といった境界条件で同じ文でも意味が変わってしまうという、極めて御都合主義的な言語が出来上がったわけだ。と、前口上を述べた上で、意味がどうも取り難いのでほぼ直訳しています。
90年代に一人ユニットで復活したケムラー氏、5月末に新作『Seelentaucher(う~ん、“心の奥底に潜り込む潜水夫”といったところか)』をリリースされたようです。
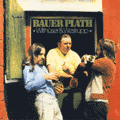
OHR
70035-2
Bauer Plath/Witthüser & Westrupp
三作目。ジャケ中央の人が『呑百姓プラート』なのでしょうか? ちがうなぁ、葉巻吸ってるし、カイザー社長ですかな? ユルゲン・ドラーゼ、ハラルド・グロスコプフ、ギーレ・レトマン、もちろんエンジニアのディーター・ディエルク等総出演によるドイツ語田園メロトロン・フォーク。もっともおそらく基本はハーモニカとアコギの四畳半フォーク風歌ものなのだが、多彩なゲストが寄ってたかって繰り出す、ブラス音、ストリングズ音、フルート音のメロトロン、ピアノ、オルガン、リズム隊の作り出す荘重な音場ですっかり別物が出来てしまったかのような予定外の新鮮さがおもしろい。当人達は“こんなはずではなかった”と思っているかも知れないが、なんとも垢抜けない田舎臭さとノスタルジックな叙情、訳のわからぬ高揚感が相まって、理想主義的田園コミューン音楽がここに完成した。
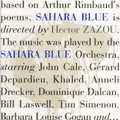
Crammed Disc
MTM 32
Sahara Blue/Hector Zazou
ZNRの末裔、エクトル・ザズーの何作目かよくわからんソロ。
アルテュール・ランボー(Arthur Rimbaud:1854-1891)の詩をテクストにした没後100年奉げものアルバム。もっとも、ランボーが詩作をしたのはフランスにいた16-19歳の三年間で、(男同士だけど)痴話喧嘩の果てにヴェルレーヌに撃たれ、放浪に出てアフリカ(エチオピア)に居ついて商人として成功するのは後半生である。だから、ランボーの作品には砂漠を詠ったものはない、というのが味噌なのだが、せっかくのロマンをぶち壊すのも野暮というものか。水と太陽の詩人といわれる辺りからの表象なのだろうか。ZNRに比してシニカルな諧謔味は薄れてずっと直截的で、狙っているのは言わずもがな。
「L'Éternité」
……
Elle est retrouvée.
Quoi? - L'Eternité.
C'est la mer allée
Avec le soleil.
う~む、これは是非原文で読みたい。この韻。
「永遠」
……
また見つかった。
何がって?-永遠。
それは行ってしまった海
太陽といっしょに。
ランボーのいちばん? 著名な「酔いどれ船」のなかでも有名な一節。太陽と海が象徴するものが、サハラとブリュなのだろうか。
ベルギーのクラムド・ディスクということで、アクサク・マブルのシャント、バーバラ・ゴーガン(Barbara Louise Gogan)、ミニマル・コンパクトのマルカ・シュピーゲル、デッド・カン・ダンス、デビッド・シルビアンから坂本龍一まで、毎度お馴染みの豪華ゲストの数々。ダンス・チューンからサティばりのアンビエントまで百花繚乱の音の蜃気楼。
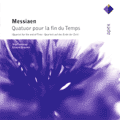
Apex
0927 48749 2
2002
Quatuor pour la fin du Temps/Messiaen, Olivier //Eduard Brunner, Trio Fontenay
メシアン(1908-1992)である。『時の終りのための四重奏曲』はWW2の戦時捕虜としてゲルリッツ(Görlitz)の収容所で作曲、初演されたもの。フランス降伏後、パリに戻りコンセルヴァトワールの教授、後の門下生にシュトックハウゼン、クセナキス等がいる。本盤は91年のデジタル録音、2002年の再発廉価盤です。
かつて法王がいた街、アビニヨンの出身で、60年に渡ってパリ、サン・トリニテ教会のオルガニストを努めている。一方で、いわゆるトータル・セリーの提唱者でもあり、宗教曲から電子音楽まで、はたまた鳥の鳴き声に獲りつかれたアンビエント音楽の創始者といっても過言ではないだろう。
表題曲は8つのパートに分かれた43分ほどの長曲。四重奏はクラリネットにピアノ、ヴァイオリン、チェロを指す。「時」ではなくて「この世」を指すという解釈もあるようですが取敢えず迷ったら直訳。各パートにはそれぞれ副題がつけられている。
1;Liturgie de cristal(水晶の典礼) 2:28
2;Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps(発声、時の終わりを告げる天使のために) 4:34
3;Abîme des oiseaux(鳥達の深淵) 6:18
4;Intermède(間奏曲) 1:39
5;Louange à l'Eternité de Jésus(永遠のイエスへの賛歌) 7:43
6;Danse de la fureur, pour les sept trompettes(恍惚の舞踏、七つのトランペットのために) 6:03
7;Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps(虹の乱舞、時の終わりを告げる天使のために) 6:55
8;Louange à l'immortalité de Jésus(不滅のイエスへの賛歌) 7:41
“七つのトランペット”に示されるように黙示録との関連は避けて通れない。12音の使用と不協和音が奏でる、緩急と変化に富みながらも全体を穏やかで冷たい空気が包み込む非常に現代的な室内楽。研ぎ澄まされた触感が痛々しいまでの静寂と刹那を引き摺る。
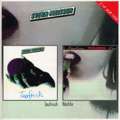
BuschFunk
8029-2
Taufrisch/Nächte/Stern Meißen
1985年の6th『Taufrisch(露に濡れた)』と87年の7th『Nächte(夜)』のカップリング。7thが実質的なラスト・アルバム。2作とも計10曲づつと短曲のみになって、時代に合わせたポップ化が図られているのは仕方ないところ。でも、手が抜けているようなところは一切なくて楽曲の出来は良いですよ。シャープなリズムと流麗なメロディ、録音やエレクトロニクスの扱いを含めてまったく遜色はない。何よりもその中欧ロマンティシズムに溢れた歌心が心に迫る。不必要な派手さも奇を衒うこともないが、何十年経っても同じように染み渡る基本的な質がきちんと確保された音楽なのだろう。300年前の古典派の音楽を今でも新たなる感慨を持って聴けるように。トータル79分59秒。
6thは分厚いストリングズ・シンセの海にたゆとう華麗なメロディが光る。ドイツ人は叙情的なメロディがお好みのようだ。リズムの切れ味が良過ぎて少し違和感があるくらい。
7thはときおり聞こえるファンクなリズムとメタルなギターにびっくり。ボーカルはロック色の強い人に代わったようだ。前作のコンパクトな凝縮感は薄れ、壮大なスケール感と小体で繊細なロマンが同居している。
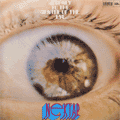
Bellaphon
289-09-007
Journey to the centre of the eye/Nektar
『Recycled』しか相手にされないネクターの1st。もちろん中期以降の明るく突き抜けた脳天気あっぱっぱぁ感は皆無で、暗くうろうろと湿った大気の底を這うような、どっぷりとヨーロッパに浸かりきったトータル・アルバム。派手ではないが、分厚いメロトロンもカッティングしないギターも全体のアレンジにきっちりと嵌っていて好感である。おまけにブリットポップに擦り寄った続く2作よりも古臭さを感じさせない。アヴァン・ガルドな展開とリリカルなフレーズのバランスがちょうど良いのだろう。歌詞は英語。 楽曲としての表現はさすがに時代を感じさせるものがあるが、アンビエントなまでの広がりと奥行き、被さるフルートが醸し出す雰囲気は1stにして既に完成の域に入っているだろう。
再発CDですがリマスターはされておらず、モノラル録音みたいな音場の広がりのなさが残念至極。
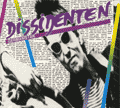
Exil Musik
EXIL 5500
Germanistan/Dissidenten & K.C.P.
新独逸波の真っ只中、オリジナルは81年、インドのナルマダ河畔バンガロールでK.C.P.(Karnataka College of Percussion:カルナタカ打楽器倶楽部)との共演で録音された。それを元に89-92に掛けてリミックスが施されたディスィデンテンの実質的1st。『ゲルマニスタン』は四次元において古代と現代をつなぐ電子の掛け橋で、新たな大陸を指し示すとライナーを書いているガンジーさんはいっておる。それなりの意気込みが伝わる内容だが、そこは90年代、言った本人はもう忘れているだろう。
電子楽器を操るドイツ人トリオ(Marlon Klein, Friedrich Josch, Uve Müllrich)が放浪の果てに現地混成録音をして、それを音源に加工を施した亜細亜阿弗利加欧羅巴電化舞踏音楽。なんとなく記憶を掠めるものがあってよくよく調べてみたら、ヨッシュ(Josch)とミュルリッヒ(Müllrich)は次項のエンブリョのメンバーでもあった。あちゃぁ。
初作は南インド、カルナタカ州の打楽器集団との混成です。比較的生音を生かした作りでベースになっているのは南インドの民族音楽。アレンジもかなり控え目。
独特のインド人男女歌手は古代サンスクリット、すなわち梵語で歌う。
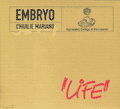
disconforme sl
DISC 1940 CD
"Life"/Embryo
2001年初リリースの蔵出し音源。正確にはチャーリィ・マリアーノに加え、同上カルナタカ打楽器倶楽部との共作で1980年のライブ録音。こちらの方が一年早いわけだ。既に前作『Embryo's reise』で西アジア音楽への傾倒を表しているが、ブルクハルトのライナーによれば、79年、カルカッタのジャズ・フェスティバルで親交を深め、翌80年、ロンドンのフェスティバルに招待出演していたK.C.Pを誘い、ドイツ国内をツアーして回った際のライブ録音らしい。
ベースは現ディスィデンテンのミュルリッヒ、フルートも同ヨッシュ。
民族音楽基調のディスィデンテンに比べ、こちらは正統でもないがジャズ・ロック基調であることは間違いない。全四曲中、三曲は南インドやモロッコのトラッドであるが、アンサンブルの重ね方やソロの入れ方、リフの決め方など、再構成された展開は西洋音楽の領域との融合を果たしている。なおかつ、その違和感のなさは特筆に価する。12人のK.C.P.団と一体化した迫力の大合奏大会である。エンブリョの場合、単なる味付けではなくて真性なのだなぁ。それが作られたブームなどどこ吹く風といわんばかりに、今でも続いている秘訣だろう。
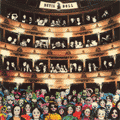
The Wild Places
RCD 1009
Eliogabalus/Devil Doll
タイトル『エリオガバルス(エラガバルス又はヘリオガバルス)』は在位218-222年、18歳で頓死したローマ皇帝。乱行と放蕩の限りを尽くし、挙句の果てには「すべての男の妻」と称された極め付きの趣味(今風にいえば性同一性障害)が嵩じて自らの肉体改造に走った稀代の変態です。グロいところでは良家の美少年・美少女を集め、親の目の前で惨殺して嘆き悲しむ様を愉しみ、きれいどころでは招待客の頭に大量の薔薇の花びらを降らせ、埋めて窒息死させたとか。
スロベニアのデヴィル・ドール二作目。B級風(敢えて茶化しているのだなぁ)怪奇劇伴音楽路線は相変わらずですが、構成、展開はかっちりとまとまってきた。もはやオラトリオと称しても良いだろう。今回も絢爛豪華バロック趣味が歪んで捻じ曲がった奇形の樹のような枝ぶりを誇っております。
前半「Mr.Doctor」はジキルとハイドらしい。語りはそれなりにシリアスに迫る。目まぐるしい展開としつこくないメタル風味は良いバランスを保っている。リリカルなフレーズの積み重ねなので劇的でありながらも美しく変態語りを引き立てている。ラスト、Mr.Doctor自身の手によるアコーディオンのうら寂しい響きが秀逸にして悲しい物語の幕引きに相応しい。
後半「エリオガバルス」は悩ましいヴィオリーノとピアノフォルテのソロで始まる。優雅な弦の響きはアルビノーニやパガニーニを髣髴とさせる。ギターレス、ティンパニの連打が悲壮感を煽る。鏡よ、鏡よ、鏡さん、とかいっているところをみると、アンドロギュヌスというか両性具有に邁進した帝の悲劇を演じているのだろう。
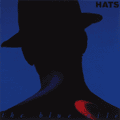
Linn Records
LKHCD2
Hats/Blue Nile
80年代の至宝、あるいはスコットランドの良心。青ナイルの2ndアルバム。1stが出たのはこの5年前。3rdが出るのは7年後という。それほど売れたという話は聞かないから本業は別なのだろう。
今作は夜を歌った曲が多い。1stよりも若干メローで刹那的。打ち込みリズムに被さるシンセとふわっと浮くような温かいボーカルの絶妙のバランスが完成された艶めかしい空気を仄めかす。夜明け前の藍色の空にほんのりピンクが差し込んできたような一瞬の芸術。
およそロック風のグルーブ感とはかけ離れたフラットで単調なリズムと、心地良いエレクトロニクスでありながら陳腐に陥らない、敬虔かつ真摯な筋の通った音作りは敬服に値する。本質的に抱え込んでいる非常に掴みどころのない分かり難さすら心地良く思えてしまうので、コメントも書き辛い。安心しきって腕の中で寝ている滑らかな白い喉にふっと目をやって、でも絶対にわかり合えない根源的な虚しさを同時に感じとるような寂寞感とでもいおうか。独特の移調と不思議なメロディの醸し出す極上の青に心惹かれる。