| |
カール・ツアイス
- 神話と歴史
「ツアイス神話」という言葉がある。
われわれは神話をささやき伝えゆく、しかし神話であるからにはその起原というものがあるはずだ。
それはぼくが知っている限りでは1908年という昔にさかのぼる。
この年に終結した日露戦争は日本が世界に飛躍する跳躍台となり近代の日本の大きな基礎となったのである。その大きな出来事はこの年に戦われた日本海海戦という日本の連合艦隊とロシアのバルチック艦隊という文字どおりの主力決戦であり、それに日本が圧倒的勝利をおさめて欧米を驚愕させ全国民を沸かせたのである。
 |
その立役者とも言える連合艦隊司令長官の東郷元帥は運命の日、旗艦三笠の指揮艦橋に立っていた。その手にはカール・ツアイス製の双眼鏡*1が握られていたのである。
もともと日本海軍は英国海軍を規範にしており艦橋の他の提督たちは英国製の双眼鏡を使用していたそうである。その中、ツアイスを手にしていた東郷元帥はみなよりもいちはやく敵艦隊を発見し戦闘指揮に大いに役立ったと言う。
そしてこの話はその後有名な司馬遼太郎の「坂の上の雲」にも記述され広く読まれた。
これが「神話の起原」ではなかろうか。 |

まずはじめに疑問があるのではないだろうか。よくコンタックスのレンズカタログにある文字、「このレンズはカールツァイス財団によって...」。
株式会社でなくカールツァイス財団というやや聞きなれない言葉。それがツァイスの歴史のとびらを開けるキーになるのである。ここには4人の名前が出てくるが、特にひとりの名前が重要だ。
カールツァイスは創業者の名前である。ツァイスは始め大学での研究を元に顕微鏡の制作を始めた。やがて彼は数学を光学レンズの世界に応用することを考え、数学者であるエルンスト・アッベに協力をもとめた。
現在でもツァイス社内で神格化され、創成期のツアイスにとって事実もっとも重要な役割を果たすのがこのアッベである。かれが数学者として残した功績は
まず独力で工学ガラス製造に取り組むオットー・ショットを励まし親交を結んだ。そして後にツアイスにとってかかせないものとなるショットガラス社を創設するのである。*2
優秀な数学者であると言うことのほかにエルンスト・アッベの先見性は二つあった。ひとつはレンズをカメラに応用することを考えたことで、このため数学者のパウル・ルドルフを雇い入れた。かれはのちにテッサーやプラナーなどを開発する。
もうひとつは人柄からか労働者の待遇を案じて汎会社的な枠組みを作り労働者の福利厚生を考えたと言うことである。アッベの尽力によりカールツァイスは財団をつくり、ショット社やツァイス社をその傘下に置くことになった。これにより会社は財団所有となり個人のものではなくなったのである。
これにより当時14時間労働であった労働者は9時間労働となりアッベは神格化されていく。

引き裂かれた家
ツァイス・オプトンとツァイス・イエナ |
アッベは先見の明にひいでていたがその彼ですら未来のことはわからなかった。
彼はツァイスの50周年式典のさいに「次の50年後の1946年、ツァイスはその100周年を誇る年になるであろう」と演説した。
しかし、その100周年式典が聖地イエナで開かれることはなかったのである。その年はツァイスにとって試練の年となった。
話を一年前にもどそう。
その年、1945年。ヒトラーのドイツ第三帝国は燃え尽きようとしていた。西からは米英連合軍が東からはソ連軍が怒涛のごとく押し寄せていた。
そして悪行の限りをつくした悪に正義の名を語る悪が鉄槌を加えた。ツァイスの工場を擁するドレスデンは連合軍により人類史上かつてない集中爆撃実験のターゲットとされ、文字どおりがれきと化したのである。*3
しかしツァイスの工場施設はいまだ6割程度の稼働率はあり、ツァイスの戦後を考えるには十分であった。戦争さえ終われば、、、
しかしその年の5月、アメリカ軍の将校がイエナを訪問した。そして彼らは英語しか話さなかった"We
take the brain!".
中枢技術者と家族約1300人はイエナを離れた。残ったものは多かった、だれもそこを離れたくなかった、だが実は去るものは幸運であったのだ。ソビエトの共産党恐怖政治を免れたのだから。
かれらははじめハイデンハイムと言うだれも聞いたことの無い町にむかった。そして新たな創業の地を探すなかでオーバーコッヘンと言う町にあまり使われていなかった戦闘機の部品工場をみつけたのである。ここに第二のメッカが建設されようとしていたが先は険しかった。
かれらはオプトン光学・オーバーコッヘンと名乗ったが、のちにツアイスを社名に付加した。しかし、はじめはツァイスの名を使用することさえイエナの重役を呼んで了承を得ねばならない始末であった。
しかしやがて本家と言えるイエナにあったというか残ったツァイス財団も転機を迎えた。「人民のために」国に没収されたのである。これでいわば分家であったオーバーコッヘンの西のツアイス・オプトンはツアイスの本流を目指すことができるようになった。真にアッベの精神を継ぐのはどちらか。
これはカイロで開かれたショウをきっかけとした西と東のツアイスの間で「名前」をめぐる戦いに発展していく。
法廷闘争の結果、結局西の財団企業ツアイスと東の国営(VEB)ツアイスの争いは戦後の現状容認の原則に従い次のように決着を見る。
1.
西ドイツ、アメリカ合衆国、日本などでは西のツアイスが「カールツアイス」と名乗ることができ、東のツアイスは名前にJenoptikを付加せねばならない。
2. 東のCOMECON諸国では西のツアイスが名前にOptonを付加せねばならない。
3.
イギリスを始めいくつかのヨーロッパなどは明確な補足をつける限り双方ともツアイスを名乗っても良い。
これは「ブランド」をめぐる戦いであった。「ブランド」に対して反発感を覚える人も居る。しかしこれが表面的なスタイルの争いであったのだろうか?その指摘が間違いであることはつづく時代にほかならぬ日本が証明するのである。
1960年代に入り日本のカメラ輸出攻勢は次第に激烈さをましていき、名門フォクトレンダーもイコンと手を組まざるを得なくなるほどであった。そうした中、ツアイスも経営に大きな打撃を受けた。
しかしそんななかでもツアイス財団はけっして労働者の権利をないがしろにすることなくアッベの精神を守ることができた。
それは銀行が「カールツアイス」という名前を信頼し資金を融通したからである。
ブランド、名前 - それは信頼の証明だったのである。
|

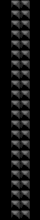
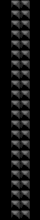
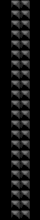
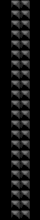
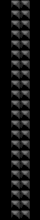
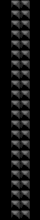
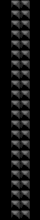
|
*1
5・10倍兼用でその形からツノガタメガネと呼ばれた。
このツアイスの双眼鏡は小西六(現コニカ)の輸入になる。
当時の海軍提督たちは自前でこうした双眼鏡を用意していたそうである。

双眼鏡実物(三笠記念館所蔵)
*2
彼らの時代すでに非球面レンズも構想されていた。
Made in Germany
いまではこの文字は絶対的な品質を所有者にもたらす。
しかし、1876年に開かれた万国博覧会のときにはまだ「ドイツ製」というのは安かろう悪かろうの代名詞であったらしい。そのためドイツ製品ということをなるべく隠すべく英国製らしく装っていたということである。その後ドイツ製品はドイツ製であることを明示するため"Made
in Germany"
と明記するよう英国から要求されたということである。
これはまったく同じことが"Made in Japan"
にもあてはまる。以前テレビで見たが、いまではアフガニスタンの銃器違法製造業者が高品質に見せかけるために銃身に"Made
in Japan"と刻印するそうである。
ツァイス・イコンとコンタックス
コンタックスの名の由来はコンテッサ、イコンタ、テナックスの合成語であるといわれている。
ツアイスイコンは独自性を重んじていてコンタックスにも特徴的な機能をもりこんだ。
ライカに無い長所でコンタックスに取り入れられて現在までも使われているのは、
バヨネット方式のレンズマウント
開閉式の裏蓋
たて走りの金属製シャッター
などである。
*ヤシカ・京セラとコンタックス
工事中
*3
ドレスデン爆撃はアメリカの現代作家カート・ヴォネガットJRの「スローターハウス5」にくわしい。
参考文献と推奨図書
ツアイス 激動の100年(原題:名前だけは残った)
アーミンヘルマン著 中野不二男訳 新潮社
ツァイスの社史をドラマチックに描いている。
カールツァイス 創業分断統合の歴史
小林貴久著 朝日新聞社
ツアイスの歴史を主にカメラファンの視点から書いている。カメラ製品の解説も多い。
|
 |