<宗谷本線・抜海>
(そうやほんせん・ばっかい)
旅行日 '95/8
<夜汽車にて>
 早朝5時半。昨晩、札幌を発った夜行列車。ようやく終着「稚内」が見える所まで来た。列車はコトコトと音を立てて小さな駅を通過するが気付く者も気にする者もいない。
早朝5時半。昨晩、札幌を発った夜行列車。ようやく終着「稚内」が見える所まで来た。列車はコトコトと音を立てて小さな駅を通過するが気付く者も気にする者もいない。
旅人はけだるそうな顔をもたげ、また伏せる。
左手車窓がバッと明るくなった。旅人はアッと驚き、目を覚ます。目前は海、そして向こうには富士と見まごう利尻(りしり)島。
次の駅は南稚内。車内はにわかに騒がしくなってきた・・・。
左写真はハメコミ合成です。
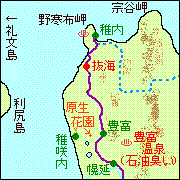
先ほど通過した駅、駅名を抜海(ばっかい)という。「バッカイ」とは小気味よい響きがするものだ。
しかしこの名前、なんとも出来過ぎである。
「この先<バッ>と<海>が見えるから<バッ海>???」とは、誰しもが思いつくところであろう。
その真相は・・、このページを最後までご覧下されば分かります・・。
稚内から1両きりの鈍行列車に乗って2つ駅を戻り、抜海駅へと向かうことにする。
<南極物語>
 さてさて、ここは昭和58年(1983)に公開された、映画『南極物語』のロケで使わた駅なのである。
さてさて、ここは昭和58年(1983)に公開された、映画『南極物語』のロケで使わた駅なのである。
メディア・ミックスとかやらで大成功を治めたこの作品。長らく日本映画の配収記録(確か59億円)の座を保持し続けたが、つい最近バケモノ映画(じゃない?)『もののけ姫』に抜かされた。
うれしいことに駅舎はそのままの姿で残っている。北海道の無人駅のほとんどは、物置小屋みたいな待合室があるだけのものに替えられてしまったが、この古びた駅舎がこうして残っているのはやはり映画のおかげなのだろうか?
 その『南極物語』について。
その『南極物語』について。
昭和33年、第一次南極越冬隊はやむを得ぬ理由で、昭和基地にタロ、ジロほか樺太犬を残したまま帰国する。しかし犬たちを置き去りにしたことに、各方面からの厳しい非難が浴びせられた。
隊員のひとり潮田(高倉健)は、樺太犬を供出してくれた人々に謝罪するため旅に出た。そうして降り立った駅がこの抜海駅だったのだ。
右は映画『南極物語』パンフレットより
 駅では一人の幼い少女が待ち受けていた。潮田は代わりの犬を差しだし謝罪するが、少女は許さない。「オジちゃんのバカバカ、キライよー」と泣きながら責める。
駅では一人の幼い少女が待ち受けていた。潮田は代わりの犬を差しだし謝罪するが、少女は許さない。「オジちゃんのバカバカ、キライよー」と泣きながら責める。
「このクソガキ! 犬助けるのと人サマの命と、どっちが大切だと思ってんだ!」とは健さんは言わない。下手な言い訳もしない。
駅のホームの上、悲しみに暮れる少女を胸に(子どもだからヘソのあたりか?)受けとめ、じっと黙って自分を責めるのであった・・・。
 格好いいゾ、健さん! (*^^*)
格好いいゾ、健さん! (*^^*)
この項は記憶を頼りに記しているので、イイカゲンなところがあるかもしれません。
<抜海岩の伝説>
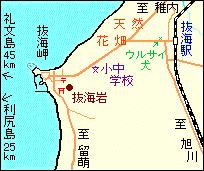 駅付近には民家が一軒あるだけである。犬が吠えることケタタマシイ限り。この犬とタロ・ジロとの関係は分からない。駅を後ろに一直線のゆるやかな坂道を10分ほど下ると、道道に出る。この付近は自然の花畑。エゾカンゾウ、エゾスカシユリなどが見られる(花の最盛期は7月)。
駅付近には民家が一軒あるだけである。犬が吠えることケタタマシイ限り。この犬とタロ・ジロとの関係は分からない。駅を後ろに一直線のゆるやかな坂道を10分ほど下ると、道道に出る。この付近は自然の花畑。エゾカンゾウ、エゾスカシユリなどが見られる(花の最盛期は7月)。
さらに道道を15分ほど南下すると、抜海岬にたどり着く。久々に人間の呼吸の音が聞こえるところに来た。岬には小さな港があり、付近に数十軒ばかりの侘びしい集落が形成されている。
集落のはずれには神社。その裏の小高い丘の頂上の辺りに、奇妙な形をした岩が頭姿をのぞかせている。
 案内板を読んでみる。
案内板を読んでみる。
この岩は抜海岩(アイヌ語で”パッカイ=ぺ”「子を背負うもの」の意)で、美しくも悲しいアイヌの伝説を今に伝えています。
宗谷アイヌとの戦いで、天塩(てしお)アイヌの応援に来ていた礼文(れぶん)アイヌの若者は、天塩アイヌの娘と恋をし、子どももできて幸せに暮らしていましたが、若者は故郷の礼文を忘れられず、ついに島へ帰ってしまいました。
 妻は礼文島を望む丘に登って夫の帰りを待ち続けました。そしていつしか子どもを背負ったまま岩になってしまいました。その岩がこの抜海岩なのです。
妻は礼文島を望む丘に登って夫の帰りを待ち続けました。そしていつしか子どもを背負ったまま岩になってしまいました。その岩がこの抜海岩なのです。
伝説の岩をめざして丘を登った。ほぼ真西に礼文(れぶん)島を望める。礼文島は起伏の乏しい島だ。海の彼方のわずかな隆起でそれと分かるのみである。
 礼文島のすぐ南側。圧倒するのは利尻(りしり)島の偉容である。大概の者はこの秀麗で屹立とした島の方に目を向ける。
礼文島のすぐ南側。圧倒するのは利尻(りしり)島の偉容である。大概の者はこの秀麗で屹立とした島の方に目を向ける。
が、礼文に去った夫を待ち続ける伝説の彼女には、おそらくこの美しい島影も目に入らなかったのでは。ふとそんなことを考えた。
<終わり>
ホームページへ | メールはこちら
 早朝5時半。昨晩、札幌を発った夜行列車。ようやく終着「稚内」が見える所まで来た。列車はコトコトと音を立てて小さな駅を通過するが気付く者も気にする者もいない。
早朝5時半。昨晩、札幌を発った夜行列車。ようやく終着「稚内」が見える所まで来た。列車はコトコトと音を立てて小さな駅を通過するが気付く者も気にする者もいない。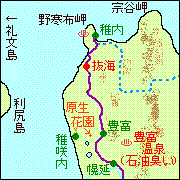
 さてさて、ここは昭和58年(1983)に公開された、映画『南極物語』のロケで使わた駅なのである。
さてさて、ここは昭和58年(1983)に公開された、映画『南極物語』のロケで使わた駅なのである。 その『南極物語』について。
その『南極物語』について。 駅では一人の幼い少女が待ち受けていた。潮田は代わりの犬を差しだし謝罪するが、少女は許さない。「オジちゃんのバカバカ、キライよー」と泣きながら責める。
駅では一人の幼い少女が待ち受けていた。潮田は代わりの犬を差しだし謝罪するが、少女は許さない。「オジちゃんのバカバカ、キライよー」と泣きながら責める。 格好いいゾ、健さん! (*^^*)
格好いいゾ、健さん! (*^^*)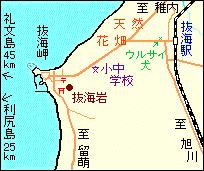 駅付近には民家が一軒あるだけである。犬が吠えることケタタマシイ限り。この犬とタロ・ジロとの関係は分からない。駅を後ろに一直線のゆるやかな坂道を10分ほど下ると、道道に出る。この付近は自然の花畑。エゾカンゾウ、エゾスカシユリなどが見られる(花の最盛期は7月)。
駅付近には民家が一軒あるだけである。犬が吠えることケタタマシイ限り。この犬とタロ・ジロとの関係は分からない。駅を後ろに一直線のゆるやかな坂道を10分ほど下ると、道道に出る。この付近は自然の花畑。エゾカンゾウ、エゾスカシユリなどが見られる(花の最盛期は7月)。 案内板を読んでみる。
案内板を読んでみる。 妻は礼文島を望む丘に登って夫の帰りを待ち続けました。そしていつしか子どもを背負ったまま岩になってしまいました。その岩がこの抜海岩なのです。
妻は礼文島を望む丘に登って夫の帰りを待ち続けました。そしていつしか子どもを背負ったまま岩になってしまいました。その岩がこの抜海岩なのです。 礼文島のすぐ南側。圧倒するのは利尻(りしり)島の偉容である。大概の者はこの秀麗で屹立とした島の方に目を向ける。
礼文島のすぐ南側。圧倒するのは利尻(りしり)島の偉容である。大概の者はこの秀麗で屹立とした島の方に目を向ける。