|
|
| �@ ���{�̐n���ƍ|�̒q�d�@ |
|
|
| �@ ���{�̐n���ƍ|�̒q�d�@ |
�y���{�̐n���̓����z�@
���{�̐n���́A
��炩���n�S��
�d���|��������킹�����̂��A
�^���ԂɏĂ��Ȃ���
�ł��č��Α���ł��n���A������b���n���ł���B
�Ȃ����̂悤�Ȏ�Ԃ̊|���邱�Ƃ����邩�Ƃ����ƁA
�ǂ����āA���̏�A
�Ȃ������茇������܂ꂽ�肵�Ȃ��悤�ɒb���グ��̂��ړI���B�܂��A
�����₷�����Ƃ������ɋ����Ă������낤�B
�ނ�����Ȃ��̂͂Ȃ��̂ŁA�����̏�����O��Ƃ��č��x�Ƀo�����X���邱�Ƃ�Nj������̂����{�̐n���Ȃ̂��B
�悭�A�E�g�h�A�V���b�v�Ŕ����Ă���m���i�C�t�́A�P�ɍ|�ނ�ł���������̂̂��M�������������̂��w�ǁB
���ނ̑f�ނ����H���������Ȃ̂ŁA�|�ɍœK�̏Ă�����Ă��߂��������s���ɂ����ׁA�ǂ��n���̏����ł����ċȂ��炸�������܂ꂸ���炸�Ƃ�������������������ɂ����B
�������A���̖������������1000�N�ȏ���̍Ό��ɂ��|��ꂽ�q�d�ƋZ�p���g���A���{�l�̎��A���́i�S�j�����v������M�ł���\�͂ō��グ���̂��A���{�̉Α���ł��n���ƌ×�����̐����@�ɂ��|�Ȃ̂ł���B
�܂��A�����A�H�|�i����킩��悤�ɁA���{�l�͒��J���Y��Ȏd��������B���ׂ̈̓���ł��邩��A�m���̐n���Ƃ͈���Ă��ē��R���B
���{�̐n���͈����Đ�B�a�̎v�z�A�����Ă���͎v�z�����ł͂Ȃ���ݍ��ޓ����I�Ȑ������������`���I���{�����̍�i���B
���̂Ƃ��Ă�������Ȃ��A�A����z���A�n�������Ƃ��Č���Ȃ��A�e���l�ԒB�Ƃ͈Ⴄ���E�������ɂ���B�`�͎��Ă��Ă��A�g�����ނƈႢ����R�Ƃ���Α���Őn���ƃ}�X�v���_�N�V�����̐n���A���̍��͂Ȃ����܂��̂��A���̖̂{�������������߂̂��Q�l�ɂȂ�K���ł���B
�܂��A���̌�̒����E�lj������́A�b���i�C�t����ȂǍ|���g������������g�ō쐬���悤�Ƃ����l�̖��ɏ����͗������m��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����ɓo�ꂷ��b�艮����͑O�ߑ�I�Ȑݔ������������ɒq�d�ƍH�v�ł���Ă����l�ł��邵�A���̂���q�̕��͐e���ɋ���������Ƃ�����Ɍ���̎�@�������č��x�ɒNj�����ƂƂ��ɁA��X�ɂ���ɓ�����铹����g���čH�v����A�ǂ��n��������\�Ȃ��Ƃ������Ă��ꂽ����ł���B���y�[�W���쐬�����l�Ԃ͂��̓��e���A���ۂɁg�����������l�h��A�������g�̎d�����̂��߂Ɏg��������g���̂Đ��i�ł͂Ȃ��A�ǂ����̂��g���g�����e�i���X���������g�ōs���l�B�h�ɁA�����₩�Ȃ���ł��𗧂Ă�ƍl����̂ŁA���㏭���Âł����e���C���A���M���Ă����A�A�A�S�ς���ł���B
�y�R�����N�z
���₶�����
��b���ł���B
���O��I�ؗ�����Ƃ����B
������߂��̌�ʗʂ̑������H�����ŋƂ��c�ށA�����n���Ō�̖�b�肾�B
���₶����́A�S��^���ԂɏĂ��A���Ƃőł��āA�`�����݂ɕς���B�����āA���̎�ł��낢��ȓ�������o���B
���́A��������Ƃ������Ƃ͑f���炵���Ǝv���B��X���ۗ��ɂȂ����Ƃ��ɁA�悸�K�v�ȓ���͉Ɛn���ł��낤�B���̐n�������g���Ď��݂ɂ���o���̂��b�艮���B
���₶����͂��̒b��̘r�ŁA���̂��ׂĂ������Ȃ�������������Ă����B
�ł��A���N�̏H�������^�C�����āA���Q�̉F�a���i������̉ł���j�ŋ��t�ɂȂ�ϔN�̖�����������̂��������B�@
�@
����Ȃ��₶����ƁA���̉Ăɂ������o�����B�̂���`�����{�̒q�d��厖�Ɏc�����Ɠw�͂��Ă��鑽���̊��ۑS�l�b�g���[�N�g�������h�̕��X�̂��A���B�R�Ɏ����Ă����荠�ȑ傫���̃i�C�t���~�����Ɗ������悾�����B
�d����ɂ��ז������āA�b��̎d���̘b���f���Ă���Ƃ��ɁA����ƂȂ��R�Ŏg���n�����~�����Ɛ�o�����B�u����Ȃ�A���������̂�����Ă��B�����A���͎����ō���Ă݂ȁB�v���̗l�Ȍo�܂ŏo�����̂���̎ʐ^�̎R�����B
����Ȋy�����������{�̓`���I�n�����o����ߒ���Web�ŊF����ɂ�������Ē�����K���ł���B�킽�����������o����܂Œm��Ȃ��������A�b�艮���ǂ̗l�Ȓq�d�������Ă���̂��A���̔N�z�҂ł��ӊO�ƒm��Ȃ����������i�����A�E�l�͎d����������Ȃ��̂����̗��R�j�B
�i�������ł́A�����j���[�^�E���̒��ŁA����I�ɒY�Ă����s���A�Y��|�Y�A�ؐ|�t������Ă���B��������X�Ŕ�������A�b�艮�̂��₶����̂Ƃ���Ŏg���Y��[�߂Ă���j
| �@�{���|�[�g��`98�N�̌㔼�̂��̂ł���܂����A���̌�V���ɒlj����邱�Ƃ��o�Ă����̂ŁA�m�F������ɐ����lj��C�������Ă����\��Ƃ��܂��B��ɂ��₶�����������Ƃ��܂Ƃ߂�
�g���N�`���h��{���ɑ��ẮA ��q�̏��R���i��q�j�̍l������Δ䂳���Ă��������܂����B���R���ɂ������������e�́A�ŋ߃i�C�t�G���ɂ悭�o�ꂷ��悤�ɂȂ����b���i�C�t���[�L���O�����ۂɂ���Ă݂悤�Ƃ������ɂ��Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��i�悸�͑��e
�g������̏��R���쏊`01/2�h�j�B �@�܂��A�ȑO���L�ڂ��Ă���{���̊ԈႢ�ɂ��ẮA������������� �@�����Ēb�艮�̐e���́A�Ȃ��Ȃ����ɋ��Ȃ����炢�̊�p�Ȑl�ł��邱�Ƃ��d�˂Đ\���グ�Ă����܂��B�̂Ȃ���̓�����ŁA��������Ƃ����F�X�ȓ�������o���Ă��܂��l�ł����i���ɂ�����܂肵�āA�̂���̒b�艮�̉c�݂��M�킹��l�͑��ɂ͋��Ȃ��Ƃ����ʂł��B���݂ɉߋ��`�Ȃ͖̂S���Ȃ����킯�ł͂Ȃ��A�b�艮��p�Ƃ����ׂȂ̂Ō���悤���肢�\�������܂��j�B�ł��A�����́i�n���j�Ɋւ��ẮA��q�̏��R���̕����A���_�A�r�Ƃ��e�����z���Ă���Ƃ����W�ґS���̔F���Ȃ̂ŁA�L�^�҂̊��Ⴂ���C������Ӗ��ƂƂ��ɁA�����ۓI�ł����ɗ����̂��A�����������X�ɂ��͂����悤�ƁA�����|�[�g�̒��������R���ɂ��肢��������ł��B �@���āA���̒b�艮�̘I����ł����A�\��ʂ�H�������Q�Ɉ��z�����܂����B�ł��A�����z�����̂�`99�N��1���̖��ł��B�I�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƒ�ς����Ƃ����l�B���A�������Ă��ꂱ�꒼���Ă���Ɨ�����A���q�悭�Ă��܂����b�艮����̌l�I�ȏ��ʂ̎���H�Ŏd���ɂ̓I�[�o�[�t���[���Ă��܂��A�d�������c���ċ����Ă����Ă��܂��܂����B �@�������A�b�艮�ɗ���q�͖ʔ����l����ŁA�݂ȉ�������E���`�N�������Ă���悤�ȘA������ł��B���z�ԍۂɂ́A�F����ւ�藧���ւ��b�艮�̎d������`���A�����Ĉ��z�̕Еt����吨�ł��܂����B�����āA�ꎞ�I�ɂ͑����b�茤����ȂǂƂ����̂������オ���ĉ��܂ō���A�܂��l��ɑg�ݗ��Ď��̉Ώ����@�n���ĉΑ�����Â��ꂽ�܂������A���̌�͉_�U�����������̔@�������͖����Ȃ��Ă��܂��܂����B�����ƁA����Ȃ��Ƃ�����l�B�͕��Ȑl����������p�b�ƉΉԂ̂悤�ɎU���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����ƒN�������v�������Ԃł��傤���A�����ł��A���������̒ʂ�Ȃ̂ł��B �@�����o�[�͒b�艮�̒�q��l�A�����ق̊w�p���A���j�����ƁA�s�k�N���R�_�@�̕S���A�A�؉����Y�Ă��l�A�\��A���Ɓ��t�A����ɗV�я������R�����Ă���i���̂�����͔p�Z�ɂȂ������w�Z��؍H�A���|�Ȃǂ̍�Ə�ɂ��Ă���j��w�����A���{���̒b���������ďC�s���̗{��w�Z�����A�Ƃ̗��ɂU�O���炢�̋������H�H��i���Ղ��n�ߑS�ă��T�C�N���i�Ő����Ă��āA�Ȃ�ł������Ă���j�����S�~�̂ďꏄ���̂�������A��Ќo�c�����Ȃ�����{�̓`�������̎ʐ^�W�s����l�A���N�O�ɋ�s�����߂ėыƂ̏C�s�ɍs���A���݃L�m�R�͔|�Ƃ𗧂��グ���̐l�ȂǂȂǂł��B���̒��ŋ����i�A���r���j�������Ă���l���V�l������̂ł�����A�b���Z�x�͂��Ȃ荂���ƌ����܂��傤�B �@����Ȑl�B�Ƃ��������i�I�ؐe���̐l���ŁA���ʕ��I�Ȓb��E�l�̏�𑽂��̐l�ɊJ�����Ē��������Ƃɂق�Ƃɓ���������܂��j�̂ŁA���̓��̈�l�A�s�k�N���R�_�@�̕S���i�Y�Ă��A�ыƉ��ł�������̕����h���j�j�̃X�_���ɗ���ŐX�ёg���̉����ŎR�̉������Ԕ�����قǂ��܂����B�n���̒b�B�̋�Ɛn�t�������̋���A���ۂ̌������g�p�ɉ����Ăǂ������Ⴂ������̂��m�肽����������ł��B������́A�}�Ζʂ̂��߂Ɋ��蕥���@���g���Ȃ��̂���Ƌ��Ƒ��ъ��Ől�͂̍�Ƃł��B���ɂR�x�����Ȃ���̎d���ł�����A�����ƌ�������肭�Ȃ�܂����B �@���̌�A��q�̏��R���i����܂����E�l�j�̂Ƃ���ɂ��V�тɍs�����ĖႢ�A��Ƃ������Ė���Ęb�����f������ƁA�b�艮�̘I����Ƃ͈Ⴄ���e�������ĖႢ�܂����B���R���́A���{�̂��������̒b�艮�����M�S�ɕ������l�ł��B�{�Ƃ͕ʂɎ����Ă���A����ȋ������H�ƂƂ��Ă��܂��B���̖T��ɍ��̂̓i�C�t�A��A��Ȃǂ̐n�������ł����A�a���̂��̂����łȂ������|�̗m���i�C�t���Α���őł��č��܂��B�I�ؐe���̂��̊�p���́A���ɂȂ��f���炵�����̂ł������A�n���Ɋւ��ẮA���̒�q�̏��R���̍����͔̂��[�Ŗ����A���i�������Ă��L�b�`�������ǂ��i�������A���̏o���͎t�����X���Đ����o�Ȃ��ʂł��B���̂悤�Ȃ킯�ł��̃m�E�n�E�����㏭���Âł��lj����Ă��������Ǝv���܂��̂ŁA���y�[�W�͐����C���Ƃ������Ƃɂ����Ă��������܂����ƈ������炸�������������i���݂ɋL�^�҂����̐l�ɕ����ƌ����邱�Ƃ�����܂���.......�����ɓo�ꂷ��F����̑����ɂ��y�Ȃ����Ɛ\���Y���Ă����܂��j�B |
| ���N�`���F�S���₷������ɂ́A�肽���Ƃ���Ƀ^�K�l�ōa��t���A�^���ԂɏĂ��B�����Ă��̍a�ɉ��𗎂Ƃ��̂��������B�����ă^�K�l�őł��Ă����Ɛ�₷���Ȃ��Ă���Ƃ̂��ƁB�܂��A�E���J����ɂ́A���l�ɂ��̂����A�g���̂͐ΒY�̕����������B���ꂼ��Z�p���Ⴄ�̂��B���̒b�艮����B���A���₶����̐n���͐��A�Ɗ��z�������Ă������Ƃ����₶����̎����� |
�y�b���n���̕ϐg�F����H���z
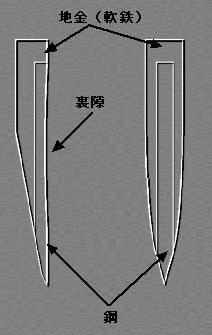
���f��
���̎ʐ^�́A�łO�̒n�S�ɍ|��\��t�����f�ނƁA�ł��Č`���Ă����ꂪ�I�������̂��̂̔�r�B
�f�ނ̒n�S�i��S�j��^���ԂɏĂ��A�S�l�i�ق����ƓS���j���܂Ԃ��ƓS�l���n����A�����ɍ|���悹��Ƃ����Ɛڍ������B�S�l�͒b��̐ڒ��܂ł���B�̂͂ق��_�ł͂Ȃ��Ęm���Ă��č�����D���g�����B
���̒n�S�ɍ|��t�����f�ނ�F�ɓ���ĐԂ��Ă��B���̐^���ԂɏĂ��ē�炩���Ȃ����Ƃ���ŋ��ƂőłƁA��S�ƍ|���e����Ŋ��S�ɐڍ����A�R���̌����o����B
�������A�n�S�ɍ|���悹����@��
�Аn�̐n���̏ꍇ�ŁA
���n�̏ꍇ�ɂ́A�n�S�̔�Ԃ��M���A�����@���Ē��Ԃ���܂�A�Ԃɐn�ƂȂ�|�����ݍ��ށB�E�͂��̒f�ʐ}�B�����Аn�A�E�����n�ł���B�Аn�͗������Ƃ����ė�������������ł���B�Аn�̏ꍇ�A�������̂��܂Ƃ����Ȃ��悤���Ԃ����̂��B
���n�S�ƍ|
���̎ʐ^�͕Аn�̎R����łO�̂��́B
������ƕ��������A�n�S�̏�ɍ|���ڂ������̂ŁA���͐ڍ��O�A�E�͓S�l�Őڍ�������B
�@
�@
|
���N�`���F���̓S�ނ��Ȃ��Ȃ����Ƃ��́A�����Ȃ�������W�߂Ă��ĕt�����킹�čޗ����������i���ˁj�A�O�L�̕��@�ŁA����Ȃ��Ȃ���������t�������āA������`������肵���������B����͓S������ڂ������Ă���r�̂����b�艮�����ł��Ȃ������Ƃ̂��Ƃł���B
�n�̕����̍|�ɈႤ��ނ̍|���Ďg���Ă��܂��ƁA��������قȂ�̂Ŏg���ɂ������̂��o���Ă��܂����A����ȑO�ɍ|�ɂ���ďĂ�����̋���Ⴄ�̂ŁA��肢�Ă����ꂪ�o���Ȃ��Ƃ̂��ƁB ���₶����ɋ���������Ƃ��L���Ă������B �C���Ɏ������܂ꂽ���̒b�艮�����������̍|�ɉ����g���Ă��邩����Ȃ��ꍇ�̂��Ƃ��B�|�̎�ނ�����Ȃ��ƁA�|�ɂ������Ă����ꂪ�o���Ȃ��̂ł���B���ׂ̈ɂ́A��x�Ă��߂������ē�炩��������A���X���ō���Ă݂�̂��������B
|
�y�|�ɂ��āz
�|�ɂ͂��낢�날��B�����Ԃ̃T�X�y���V�����Ɏg���Ă���X�v�����O���|�����A�䏊���ɂ��g���Ă���X�e�����X���|�ł���B�ł��A�����̍|�ł͗ǂ��n���͏o���Ȃ� �i���R���H���F�Ԃ̃T�X�̔o�l�́A���Ȃ�ǂ��n���ɂȂ�B����͋L�^�҂̊��Ⴂ�ŁA���S���̃X�_�����o�l�����킵�āA�A���r���Ńg���e���J��������Ȃǂ����̂����ӂ��Ƃ����j�B��ɂ��������Ƃ���A�n���͍d����悢���Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��B�d��������������A�����d�����ɓ��������Ƃ��Ɍ����Ă��܂����܂�Ă��܂��B�v����ɔS��A�x���i�����j���Ȃ��̂��B����ɍd�߂���Ɛn�������Ȃ��B�������Ƃ����ē�炩������A�����n���݂��Ă��܂�����Ȃ����Ă��܂��B�킽�����q���̎��Ɉ����̃i�C�t���g���Ă����Ƃ��⎩���œS�ނ����H���ăi�C�t��������Ƃ��ɁA����ł悭�������B�����ŏĂ�����ꂽ��߂����肵�����A�܂ꂽ���Ȃ�������őS�R�g�����̂ɂȂ�Ȃ������v���o������B�Ă������Ă��߂�����肭����Ă��A�f�̍|�̎����ǂ��Ȃ��Ă͐x�����Ȃ��B
���������{�ɂ͐��E�Ɍւ�|������B���̂Ȃ��̍ō���͋ʍ|�i���܂͂��ˁj�Ƃ�����ǎ��̍��S���×��̂����琻�S�@�ō�������̂��B���{���Ɏg���Ă��铁�g�̍|���������B�ł��A����͖w�Lj�ʎs��ɂłȂ��B���a�̏����ɍŌ�̂����琻�S�͏����Ă��܂��A���̌�A�������̋g�c���ŕ������ꌻ�݂ł͑�O�Z�N�^�[�����Őݗ����ꂽ�����́i���j�����炪����Ă�����̂�A�������̕⏕���ƂƂ��āA���������i���j�̋��͂̂��Ƃɏo�����i���j���{���p�����ۑ�����̓����ۂ����炭�炢�̂悤���B���Ƃ͓������l�I�ɂ����琻�S���s���ĕK�v��������Ă���炵���B�����܂ł͓��{�̍|�݂͂Ȃ����琻�S�������̂����A�����̓S���i�̐���Z�p�������Ă���ɂ�m���̑�ʐ��Y�̐��S�@�����߂�ꂽ�̂��B�Ȃ��Ȃ�A�����琻�S�͔��Ɏ�Ԃ̊|���邤���A�Z�p�҂̍��x�ȋZ�p�Ən���x�����߂��邩��ł���B�B
�����Ō��݁A�ʍ|�ɑ����ē��{�̐n���ɑ����g���Ă���̂́A�o�_�̐��S�̓`�����p�����������i���j�̈����H��ł���������|�i�₷���͂��ˁj�ŁA�䓁�̃W���b�g��V�b�N�A�E�B���L���\���Ȃǂ��A���̈����|���g�p���Ă��邻�����B�L���ȃi�C�t�f�U�C�i���g���Ă���f�ށA440C�Ƃ�ATS34�Ȃǂ����������i���j�̐��i���B���ɂ��X�E�F�[�f���|�Ȃǂ����|�����邪�A���{�̐n���̈ꕔ��d���Ă��邾�����B
�ŁA���̎R���͈����|�̐����g���Ă���B���̎�̐n���Ɏg����̂��A�����Ɛ��ł���B���ꂼ��P���Q���Ȃǂ̍���������A�Y�f��V���R���A�}���K���A�Ȃǂ̊ܗL�����قȂ�B�P���̕����Y�f�̊ܗL���������d���Ă����������B�������A�b������Ă�����Ă��߂��̂����ɂ���āA�b����̍|�̓������ς���Ă���̂ŁA�|�̎�ނ̎g�������͒b�艮����̃Z���X�ɂ����̂ł���炵���B���݂ɐ��̓N���[���ƃ^���O�X�e���������������|�B�P���̕����Y�f�A�N���[���A�^���O�X�e���̊ܗL�ʂ������B���₶����ɂ��Δ��������̕�����炩���i���R���H���F�d���j�Ƃ����B�Α���̎��̒b�B�̋�������̂��낤���B�{���͋ʍ|���������̂����A���₶����̎茳�ɂ́A�������ʂ����c���Ă��Ȃ��B�ނ��A����ȑO�ɉ���������Ă���Ȃ��̂ŁA�����|���Ō�̎����B����ɉ��i�̈�ԍ������̂��Ƃ������ƂȂ̂ŎR���Ɏg���Ă���|�������|���̂P���Ƃ������ƂŁA�Ζ��Ր��̍������̂�
�i���R���H���F���₶����͖ő��ɐ��͎g��Ȃ���������A����͂�����Ɖ������Ə��R���͌����A�킽�������₶����ɍ���Ė�����R����₨�瑾���Č������������ɉ��x���ł������B�����Đn�悪�������̂����ĂƂ��Ă������B���x�͎����̍����������͔��������ǂ���ȊȒP�ɂ͌����Ȃ����Ƃ���ɁA���l�ɐn����K���K���Ƒł�����B�킽������点�Ė�������m���ɏ��R������͌����Ȃ��B���ƂŌ������R��̐n���x���g�T���_�[�Œ����Ė�������A�ʂ����Ĕ�ΉԂ͐��̂��̂ł͖��������B(^^;;�@�ނ����̌�A���̐e��������Ă��ꂽ�R����ēx���������A�Y�т��y�ɒ��邭�炢�̐n�t����������ɁA�܂��܂��ēx�́A�Ō��A����`�F�b�N���J��Ԃ������A���x�͐n���ڂ�������A�܂��ꖡ�����܂藎���Ȃ������̂ŁA����͐�̐Ƃ��Ƃ��낪�����Ē��x�ǂ��Ƃ��낪�o�Ă����̂ł��낤�ƌ������ƂɂȂ����B����̐l�Ԃ������ɂ́A�̂͂��Ȃ�ǂ����̂�����Ă������A��N�A������c�Ɋ�t���肵�Ă����ׂ��A�i�����₽����肵�Ȃ������e���̐��i�Q�̒��ŁA����͗ǂ��o���Ƃ����]���ɕԂ�炢���R��ł������B�Ⴆ���łȂ��Ƃ��A�ꖡ�A�������A�n�̕ۂ����ǂ���Ύ�荇������OK�Ǝ����͔[���j�B
�@���āA���R���͍|�����낢����������邯��ǁA�Α���̋����ԑ厖�ŁA�|�ɍ������Ă�����Ă��߂������Ă�邱�Ƃ��̐S�ł���ޗ��őS�Ă̐��\�����܂�킯�ł͂Ȃ��Ƃ̂��ƁB
����͎����ł��悭����B�R�̉�����Ɏg���i�r�̑������炢�̎G�͋����Ǝ��Ԃ��|����̂���Ő�j�ׂɎR�`�̎�c�̒b�艮����ɐ}�ʂ������č���Ė�������n��800������i�Ό�����\10500�j�́A�|�ނ͂��Ȃ�������̂��g���Ă���̂Ō����Ȃ��Ƃ������Ƃł��������A�n�̕t���Ղ��A�ꖡ�A�n�ۂ��Ƃ��f���炵�����̂ŁA���܂ň���R���ł����̂��A�P��A�����Ă��Q��ōς�ł��܂����B�����̎R�ł̉�����̍�Ƃ́A���ъ�����Ɏg�p���A��ŎG�̑������̂��A������ł͐�Ȃ��X�ɑ����G����Ƃł���B�Q�O�N�ȏ�͎����������ɕ����Ă��鐙�тȂ̂ŁA���Ȃ�̉�����G�A����ӂ��ɖ��Ă���}�Ζʁi������m�ۂ��Ȃ��ƃY���Y�������Ă����B�̂Ɋ��蕥���@�Ȃǂ̋@�B���̂ł͊�Ȃ��č�Ƃ��o���Ȃ��j��S�Đl�͂ň�l�ň���Q�O�O�؈ȏ㊠���Ă�����Ƃ������B���̐ꖡ������������͎̂d�����y�ɂ��Ă����B���p�i�Ƃ͂�������ׂ����̂ŁA����łP���~�Ȃ�������̂��i�Ό��̂Ȃ����̂͂W�`�X��~��t���j�B���R���̌����Ƃ���ޗ����M�������厖�Ƃ������Ƃ������Ă����i�ł������B
|
���N�`���F���₶����͋ʍ|�ō��ꂽ���������Ă����B�ʍ|�͍|�Ƃ��Ă͓�炩���̂��������B���̋��͂Ƃɂ����悭��āA���̏�A����g���Ă��n���݂�Ȃ������B�����āA�ڗ��ĂƂ����Đn��t���邱�Ƃ��A�X�[�b�Ƃł����ƌ���Ă��ꂽ�B�n���̗ǂ������ł���悭��Ē���������A�Ƃ����̂���炩���|�ł���ɂ�������炸�������Ă����Ƃ������Ƃł���i�Ð��Ƃ����j�B
�܂��A���₶���C�s�����������ɂ́A�|��150��ވʂ��������������A�n���Ɏg���₷���|��3�A4��ނ������Ƃ̂��ƁB ��炩�����ԂŁA�ʍ|�A�����|�A�����|�Ȃǂł���B���ꂼ�ꓯ�������ŏĂ����������ꂽ���̂��A���ƂŒ@���Đ܂��Č����Ă��ꂽ�B��L�̏��ŗ��q���ׂ����Ȃ�A�܂��A�܂�Ղ��Ȃ����B���l�ɒ@�����Ƃ��̉����Ⴂ�����獂�����ɕω������B ���₶����̌��t�ł����ƁA�����|�͂��݂��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B�Α���̂Ƃ��ɒ����̋Ђ������Ƃ������Ƃ炵���B�ʍ|�́A���̂��݂̋Ђ̃����W��0����10���Ƃ���ƁA�����|�͂��̒��́A2�Ƃ�3���炢�̃����W�����Α���ł̒������o���Ȃ��������B�܂��A�Ă��Đ��ɓ��ꂽ�Ƃ��ɔ����͂���̂́A���̂��݂̋Ђ��L���|�A�����͂���̂͂��݂̋Ђ������|�Ƃ̂��ƁB�Α���őł̂ɂ����x�������āA�ł�������ƍd���Ƃ��Ȃ�̂ŁA���̂��݂̋Ђ�������̂̕��������₷���Ƃ������Ƃł���B�����|�́A�P�A�Q��̏Ă�����Ă��߂���ƂŌ��߂Ȃ���A�����g�����̂ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
|
���݂ɁA�����琻�S�́A�傫�ȘF�𑀋Ƃ̂��߂Ɉ����S�y�ō��B���̘F�����ɂ������ẮA�F�����������ۉ����邽�߂ɑ傪����Ȓn���ɍa�菄�炵���\�������K�v���B�쓁�̓`���Z�@�h�ɂ��ƁA���̒n���̍\���������Ƃ���60�A70���������Ďł�R�₵�Ċ��������A�����ɍޖ�g�荻�⍻����~���y��킹�A��C�E���J���č��B�������`���Ȃ��悤�ɁA�n���\�����̏�ɏ������A����ɂ��̏�ɘF�����Ƃ���B���̘F�̍����������Ԃ��|�����A�ŏI�I�ɂ͈��̑��ƂŔS�y�ō�����F�͉Ă��܂��B�����āA��ʂ̗ǎ��̒Y��K�v�Ƃ���B�P���̋ʍ|�����̂ɖؒY���P�T���A���S���P�T���K�v�炵���B�g���Z�p�҂́A���x�ŕ��G�ȍ�Ƃ�F�̋��ǂ݂Ȃ��璋����킸�����Ԃɂ��i���ēK�ɂ��������Ȃ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ȂǁA����ł͏����Ƃ��Đ��藧���Ȃ����̂ł���B���ׁ̈A�����͔N�Ԃɉ��U�̓�����邩���̊��蓖�Ăŋʍ|����ɓ���邱�Ƃ��ł���炵���B���ݓ��{�Ő��Y����Ă�����{���͂��Ȃ�̐��ɂȂ�炵�����A���̍ޗ��͂ǂ̗l�ɂ܂��Ȃ��Ă���̂��낤���A�Ƃ����^�₪�悭���킳���̂��B�Íނ���|����ɓ����ꂽ�ɂ��Ă����肠����̂ł��낤�B�ނ��A�Ϗܗp�ł���A�ǂ�ȍ|�ł��W�Ȃ������m��Ȃ��̂ʼn�X�ɂ͗v��ʐS�z�����m��Ȃ��B
���₶����͎����̎t��������ł������̘b�����Ă��ꂽ�B�ʍ|���Ukg���炢�d����Ă��āA�g�����̂͂Qkg���炢�����������������B�ŏ��A�ʍ|�̓{���{���Ȃ̂ŁA�ł܂���W�߂āA�������ł��āA����B���Ă����B�����āA�S�����o�đ傫�Ȍł܂�ɂȂ�����A���x�͑ł��Đ��B����B���x���L���Ă͐܂�Ԃ��č��킹�A�悭�����ĘB��B���₶����͈�����t�C�S�̉𐁂��Ă������A������ۂ̂��d�v�Ȃ��߁A�����̍�Ƃ���Ȃ������Ƃ̂��ƁB��������Ēb���邻�����B��̖{�ɂ͂P�T�炢�܂�Ԃ��Ə����Ă������B�ʍ|�͒ቷ�ŗn���������S�������Ƃ��邽�߂ɁA���̂悤�Ȑ��B���s���b�B����B�܂��A���̒b�B���s������|�̖ڂ������c���ʂ�̂ł���B�t�ɐ^���ԂɔM���ĉ��x���܂�Ԃ��ł��Ƃ��o����ʍ|�����炱���n���̍ޗ��Ƃ��čœK�Ȃ̂��B���̐܂�Ԃ��̍H������������s��Ȃ����͍̂|�̖ڂ��ꂽ�������o���Ďキ�Ȃ��Ă��܂��Ƃ����B�s��ɏo����Ă���|�̍ޗ������̂܂ܐn���̌`�Ƀv���X�Ő��āA����ɏĂ���������Đn��t���ĂĂ��邾���̂��̂́A�c���ʂ炸�|�̖ڂ���Ă��邱�Ƃ����邾�낤�Ƃ̂��ƁB
���������̂Ȃ���̃v���~�e�B�u�Ȏ�@�ƍH�����o�ďo���オ�����ʍ|���A���E�̒��ł����ɗD�G�ȍ|�ł���A�Ƃ����̂͌���̉�X�ɂ͕s�v�c�Ȋ��o�ł���B����̉�X�́g�{���h�Ƃ������̂��牓���Ƃ���ɒu����Ă���̂��悭�킩�鎖��ł͂Ȃ����B
�y�Α���ō|��b����F�b���z
�R���͈����|�Ɠ�S�̒n�������킹�����̂��A�^���ԂɏĂ��đłB��S�ƍ|���������t�����l�p���f�ނ��݂�݂�n���̌`�ɕς���Ă����B�₦�Đ��Ȃ����Ă�����A�ĂщΏ��̒��ɓ���ďĂ��B��������ďĂ��Ȃ���ł��Ƃɂ���āA�f�ނ̒��̕s������ǂ��o���B�E�̎ʐ^�ɋ����̉��̕��̒n�ʂɗ����Ă���l�Y�~�F�̂����炪���ꂾ�B�������āA�ǂ��n�̏�����b���グ�Ă����̂ł���B
�����ɂ́A�f�ނɉ������b�����A�����Ē�����̌X�̎g�p�ړI�ɍ������`��уo�����X�ɔ����ɕς��č��Ƃ����b�艮����̎v�����������Ă���̂ł���B�@�B�ɂ͂ł��Ȃ����Ɏv�������߂�Ƃ������ƁA���̎v���ɂ���ĕ�����b����Ƃ������Ƃ��B���₶����̒ȑłp�́A�|�̕��q�\���ɂ��e������̂ł͂Ȃ����ƁA�v�킸�l���Ă��܂����̏W���x�C�����̓�����ł���B�܂��A���̑łƂ������Ƃ͒P�ɋ��ƂŒ@����Ƃł͖����B���Ƃ̓��Ă�p�x��X���C�h�������������ɕς��A�|�����艄�����肵�Č`������Ă����̂��B�Ԃ���炩�������ɁA�|��b���A�����Đn���̌`��Ȉ�{�ō���Ă����B
|
���N�`���F���̕s�������o�������Ă��A�n���キ�Ȃ�Ƃ����̂����₶����̕فB�����đ厖�Ȃ̂��A���̂悤�ɑł��Č`��邱�Ƃɂ���āA�n��ɐc�������ċ����Ȃ邱�Ƃ��������B���ꂩ��A���₶���悭�����Ă����͍̂ޗ��̖ڂ�ǂނ��ƁB�ޗ����o�����Ƃ��ɍ���������������̂��������B���̖ڂ�ǂ���i���R���H���F���������A�b�������ɖڂ͉��т�j�A�����̂̌`�����߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���B
���݂ɓS��������ł��Ă��|�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�Y�f�̊ܗL�ʂ����Ȃ����߂ł���B�S�͒Y�f�̊ܗL�ʂ�0�`0.03%�̂��́A�|��0.03�`1.7%�A����ȏ�͑L�i�����j�Ƃ����A�S�͉��M���Ȃ��Ă��łƉ��т�B�|�͉��M���đł��Ƃɂ�艄�т�B�L�͉��M���Ă����т��A�Ԃ߂đłƍ���ɕ���Ă��܂����Ƃ������i�쓁�̓`���Z�@���j�B�@�Ⴆ�A���Ȃǂ̍r���g�����̂��̂ɂ́A�Ă������肷����Ɛ܂�₷���Ȃ�̂ŁA�ŏ�����Y�f�̏��Ȃ��|���g�p���ĕK�v�ȏ�ɏĂ�������Ȃ��悤�ɂ���A�Ƃ����g�����������邻�����B �܂��A�ߏ��̐l�ɕ������b�Ȃ̂Œ肩�ł͂Ȃ����A�Y�̕��ɐ_�J���������ĉ������A�����œS���Ă��đłƍ|�ɂȂ�Ƃ����B
|
�y�A�C�f�A�z
���Ƃ̕��i���ɓ�����F���q�j�������˂Ŋ����āA�w���n��ɗ���Ȃ��悤�ɂ���X�g�b�p�[�����B���̃X�g�b�p�[�͋��Ƃőł��Ē��q���璼�p�ɋȂ��Ă����̂��B����͂��₶����̃A�C�f�A���A����Ȑn���͉����ł��������Ƃ��Ȃ����B �Z�p���Ȃ��Əo���Ȃ����U�� �i���R���H���F�b�艮�Ȃ�N�ł��o���郈�j�B���ǁA�����|����́A������Ƃ������Ƒ���ɂ��g�������Ȃ����h�ȃX�g�b�p�[�i�w�~�߁j���o���Ă��܂����B
�@
�@
�@
�@
�y����z
�T���_�[�Ō��킵�`�𐮂��āA�n���`�F�b�N�B�O���C���_�[���g���B
�y�Y���g���z
�����āA�n�g���Ă��B���₶���n�ׂĂ��鉺�̎ʐ^�Ō����鉜�̍����l�p�������t�C�S���B���̐̂Ȃ���̌Â��t�C�S�̃��o�[����ʼn�������������肷��ƁA�E���̎ʐ^�̉̂Ƃ���i�Ώ��F�قǁj�ɕ����o�Ă���B�����ɂ͐��ĕ������Y���u���Ă���t�C�S�̕��ɂ���ĉ��悭������A���̂悭�R���Ă���Y�̊ԂɁA�Ă����Ƃ���n��������������Ŏ����A�������ށB
�@
�@
���₶����͕K���Y���g���������B�b�艮����̒��ɂ̓R�[�N�X���g���Ƃ��낪��������炵�����A�R�[�N�X���Ɖ��x���オ�肷���āA�|���{���{���Ɏキ�Ȃ��Ă��܂��������B��������800�x�O����|�ɂ���Ďg��������炵���B���x����������̂́A�F�����Č��߂�Ƃ̂��ƁB�i���R�[�N�X�ł����x�����͂��Ă���̂ł��邪�A�����A�Y�̉̕���
�����Ă���̂ł��낤�B�܂��A�S�Ɉ����e����^���郊���ƃC�I�E�̊ܗL�ʂ������̂����m��Ȃ��j
���{���̐���ɂ́A���Y����Ɏg�������ł���B���ɌI�Y�Ȃǂ�����Α���̗v�f�Ƃ��āA�Η͂������A���ςȔR�����Œ���������Y���ǂ��Ƃ���Ă���B�����āA�Y��Ƃ����Y�����������ω������傫���ɂ���̂��A��Ȏd���Ƃ���Ă��� �i���R���H���F�Y��O�N�ƌ����܂��j�B
�y�Ă�����Ă��߂��z
���ɁA�ł��Đn���̌`���o�������̂��A�ēx�^���ԂɏĂ�����ɁA���A���A�܂��͖��ŋ}���ɗ�₷�B������Ă�������Ƃ����B���̍H���ɂ���āA�|���d�����܂�A�c������̂��B�����A���Ⴂ���Ă͂����Ȃ��̂����A�ނ�݂ɗ�₵�Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA�|�ɍ�������₵�������Ă���̂ł���B�����āA���ɏĂ��߂��B�L�c�l�F�ɂȂ邭�炢�܂ōēx�y���Ă��A���x�͂��̂܂܋�C���ŗ�₷�B�������邱�Ƃɂ���āA�|�̑g�D�ɔS������߂��̂ł���B
���ꂩ�����悤�ɁA��炩���n�S�ƁA�d���|��b�ڂ��邱�Ƃɂ��Ă�����̎��ɁA��炩���n�S���|�̖\���}����̂ŁA�|�ɍœK�̌ł���������B�����āA�Ă��߂����Ƃɂ���āA�Ă�����ɂ���ĐƂ��Ȃ����g�D�ɔS���߂��B�������āA�悭��A�Ȃ��炸�A�������A�܂�ɂ����Ƃ����������[�������B
���₶����͈�l�ʂ̒��̖��ɓ���ďĂ���������Ă����B�b�艮���Ă�����ɐ����g���i���\�N�����ւ��Ȃ��炵���j�̂͒m���Ă��邪�A���͂��܂蕷�������Ƃ��Ȃ������B���̕�����������Ƃ��₶����͌����Ă����B�ł߂̍z���������ƂɁA�ł������Ďg���Ă���炵���B���₶����͖��ŏĂ���������邪�A�����ł����ł��Ă����������B����͒b�艮�̒��ł͒��������Ƃ̂悤���B�m�F����ƁA���̖��ŏĂ�������̂̓i�C�t�ނ����ŁA�����ނ͂����A�L�Ȃǂ͐��ŏĂ���������Ă���Ƃ���ꂽ�B�y�Ŏg�����̂͐��ŏĂ���������Ȃ��ƋȂ����Ă��܂������ł���B
���͐����}���ȗ�p���ł���Ƃ��� �i���R���H���F���͐���1/3�̗�p���x�B�܂�A�������I�j�B�l���Ă݂�A�Ԃ̃G���W���I�C���͋}���ȉ��x�ω��͂��Ȃ����A���̂悤�ɕ������Ȃ�����A������������Ȃ��B
�Ă�����̎��̍�Ƃ́A�Ă�������Ɛn�g���\���̂ŁA�n�����Ȃ��炱���ł��Ē����B
���{���̏ꍇ�͏Ă�������ƁA��̕��ɔ���̂��������B���₶�������̂ɂ́A���͍ŏ��ɐ^�������ɑł��Ă����āA���̎��ɏĂ������邱�Ƃɂ��A���̉~�ʂ����������{���Ɠ��̌`�ɂ���Ƃ̂��ƁB��S�ƍ|�̖c�����̈Ⴂ�ł��낤���B���肪���͓̂�S�̎g�p�ʂ����Ȃ����A�܂��͏Ă������܂߂ɓ���Ă���ꍇ�� �i���R���H���F�l�������̂��̂��Ⴂ�܂��I��-----����͋L�^�҂̊��Ⴂ�ł��ˁB�j�B�ʏ�A�|�����̂��̂��ۗ��̂܂ܐԂ��M����p���ďĂ������̂͂��Ȃ����炵���B�Ђъ��ꂪ�N����₷���̂��B�������ʓI�ɂ́A�|�̒P��f�ނ����̂��̂͏Ă����ꂪ�Â��Ȃ炴��Ȃ��B�Ă�������������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�d���ĐƂ��A�d�����Č����Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�����āA�ŋ߂̂s�u�ŕ��f���Ă��铁���̓��{���̏Ă�����̕��@�́A�s�u�Ŋς����蔲���̂��̂������ƌ����Ă����B
���g���Ă��̂ɁA�Ώ��ŁA�o��������ꂽ����J��Ԃ��Ă��邩��ł���B���̂悤�ȎG�Ȃ��Ƃ��o����̂́A�Ă�����̎��ɓ��g����邽�߂ɓh��y���A�S�y�����ɂ����Đn�y�łȂ��A�u�̕������炾�ƌ����B�u�̕��͏Đn�y�ɔ�ׁA���\�Ɉ����Ă����g���痎���Ȃ��炵���B���̓u�̕����g���č�������{���͐n���̂Ƃ���ɂł��镦�i�ɂ��j�������A�Đn�y���g���č�������̂͐n���̂Ƃ���ɕ��i�ɂ��j�Ƃ����v�c�v�c�Ə������E���J���Ă��邻���ł��� �i���R���H���F�E�E�E���̕����ɂ��Ă͌���C���j�B�����������͉̂��l���Ⴂ�炵���B
���̏Đn�y�́A�S�y�ɓu�̕���Y�̕��������č��̂����A���g���Ă��Ƃ��ɔ�����ė����Ȃ����Ƃ��̗v�ŁA�����͓����̔�`���B
�Ă�����̍H���ɂ����āA�^���ԂɏĂ������g�������ɓ���ċ}���ɗ�p����킯�����A�F������悭�����m�̂悤�ɍ����̂��̂𐅂̒��ɓ����ƕ��������ċC�A���o��B�}���ɉ��x���オ�邽�߂��B�������Ă���Ƃ����Ă��ǂ��̂����m��Ȃ��B�]���ď�肭��p���R���g���[���ł��Ȃ��̂œ��g�̐c�܂őS�̂ɋ�ǂ��Ă���������邽�߂ɁA���̓��g�ɓh���Ă���Đn�y�̓������d�v�ɂȂ�B�����Ă����������ɂ́A�ǂ��Đn�y���g�����Ȃ��邱�Ƃ��厖���Ƃ��₶����͌��������̂��Ɨ��������B
�܂��A���̂s�u���ςĂ�����A���悩�瓒�ɓ���Ă����������B���̏ꍇ�A�ŏ��ɓ��ɐZ������悾�����d���Ă�������A���q�̕��߂Â��ɂꓒ�̉��x���オ���Ă��邩�����قǏĂ�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B������A�����Ƃ��͓��g�S�̂�������ɓ���āA��₷���Ƃ��厖���Ƃ̂��ƁB
�܂�A������A�̂��Ƃ́A�����̊Ϗܗp�̓��{�������狖����邱�ƂŁA�̂̂悤�Ɏ���Ő܂ꂽ�肵�Ȃ����Ƃ�ϋv���y�ѐꖡ���K�{�����������Ƃ��ɂ́A������̖��Ɋւ�邱�������������͓����̐S�\���Ƃ��Ă͂Ȃ������Ƃ������Ƃ炵���B
|
���N�`���F���̖����g�����Ă�����ł́A�ʏ�Ă�����̌�ɍs���Ă��߂��̍�ƁA��������₶����͍s��Ȃ��B���N�̌o���ŁA�Ă��߂������Ȃ��Ă������悤�ɒ��߂��Ă���Ƃ̂��Ƃł��� �i���R���F�H�H�H�j�B�{�ȂǂŒ��ׂ�Ɩw�ǂ��Ă��߂������Ă���B
�܂��A���ł̏Ă�����́A���₨�����g���Ă����������Ƃ����Ă����B���₨�������ł�������Ă��Ȃ��b�艮�ɂ͖��ł̏Ă�����͂ł��Ȃ��Ƃ��B ���̕������₨�����A�Ă����n������ꂽ�Ƃ��̉��x�ω������Ȃ��̂ŁA�d���Ă������邻�����B�n���͍d���̂��悢�킯�ł͂Ȃ����A���̓������������g���Ƃ���肢���Ƃ������₶����̍l���ł��� �i���R���H���F���̕����d���Ă�������B�j�B ���̕ӂ�̂��Ƃ́A�����Ƃ��āA����A���̒b��E�l�̕��X�̍�������̂��g���Ă݂āA�o�����Ă��������肾�Ă͂Ȃ����A���₶����̐n���͍��h�̂悤�ȍd���̑�\�ł���ނ�����Ƃ����Ă��n�̕ۂ����ǂ����A���̍��h�����������肵�č���Ă��n��������Ȃǂ����Ƃ����Ȃ��A�|��ł��Đ��Ă������Ȃ��A�ܘ_�ꖡ�͔��Q�ŕАn�̂��͎̂���̒[�ɐn�āA���ɃX�[�b�ƈ����ƁA���̂悤�Ɏ������B���̏�Ԃ�����������B����ɂ��Ă��A�|�̑f���ƁA����ɉ������Ă�����Ă��߂��̋���A�g����ɍ��킹�Ē������邱�Ƃ��o���邱�Ƃ��A�b�艮�̐^�����ł��낤�B�}�X�v���_�N�V�����Ƃ͈Ⴄ���E�ł���B |
�@
�@
�@
�y�����z
�n�J�}���ł�����A���͐n�̌����B���₶����͓V�R�u�Őn��O����Ɍ����B�n�̌����͓���B�n�͂����s����悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ��A�悸�n�悪�������Đꂽ���Ƃ͐n�����ɐH������ōs���킯�����A�H�����ނɂ��Ώۂ������J���������v��B���Ƃ����āA���̂܂܂u���^�Ɍ����̂ł́A�������̂Ƃ̖��C�ŁA������܂Ƃ����ĉ��[���n�������Ă����Ȃ��B
������Ɗ�蓹���ē��{���̑�������Ă݂悤�B���{���ł��M�i���̂��������M�F�n��ƕ�̊Ԃ̈�Ԗc���ł��镔���j�̕�������ԍ����Ȃ��Ă��邪�A�M�����ɂ����ď��X�ɔ����߂��Ă���B��J������ɁA�M�����Ɋ|���Ă���R���������Ă����悤�ɂł���B�����M�������Ȃ��Ă���̂́A���g�ɋ�����^���邱�Ƃ����邪�A�����J���đ���Ƀ_���[�W��^���邽�߂̂��̂Ȃ̂��������B�P�ɐn����邾���ł͓��̖�ڂ��ʂ����Ȃ��ƁA���₶����͌����Ă����B�܂��A�{���̓��{���͐���̕������A坂̓��̂悤�Ȋ����ɏ����c���ł���Ƃ������A��������l�̗��R�ł���B���₶����̍�����e�����������Ė������m���ɂ����Ȃ��Ă����B
���̘e�����̑���͌Ó��ɂȂ���Ċ��荞�݂Ƃ������@�ō���Ă���Ƃ����B�n���̕����������āA�����ɍ|�����Ēb�ڂ�����̂̓��̍�����������
�i���R���H���F���������Ċm�肵�����͂Ȃ��j�B����炵���B���̑���͍|�̐n�����̒��S�ɂ���̂Ŋ�猤���ł��n�͎c���Ă��邪�A��S�������M���ɏo�Ă���ׂɑ���̐n�����Ƃ��ɏ����Ă߂���Ղ��A�����Ȃ�Ə�Ɏ��܂��Ȃ��Ă��܂��킯�ł���B
���ׂ̈Ɍ��̓��{���ɂ́A�Y�f�̏��Ȃ���炩���S�S��Y�f�ʂ̑����d����S�ŕ��ō��b���i�����Ԃ��j�Ƃ������荞�ݕ��@���n�߂Ƃ��āA����ނ��̒Y�f�ʂ̈Ⴄ�|��g�ݍ��킹�đ��荞�ށA���荞�݂̕��@�����ɑ����̎�ނł����B���̖ړI�͐�̗��R�ɂ��|�ł���ޕ��@���Ƃ�ꂽ���ƂƁA���̊O���̒Y�f�ʂ������d���s����邪�Ƃ��n����Ռ����A���ɓ����Ă����炩���S�S���ɏՍނƂ��ĎA�n���ڂ��܂��h�������������邽�߂��B�ɏՍނ̐S�S��������ΐ܂�ɂ����̂ł��邪�A�|�������Ȃ邽�߂ɁA�x�d�Ȃ錤���ɂ͑ς����Ȃ��Ȃ�B�H�v���ꂽ���G�ȑ���͂��Ď��킪���������̓����̃g���C�A���h�G���[�Ɉ˂��č��グ��ꂽ���̂ł��낤�B�S�S�����Ȃ����͐܂�₷���̂����A���Ȃǂ̓˂����̂�A�Z����e�����Ȃǂ̒��ɂ́A��炩���S�S���g���K�v���Ȃ����߁A�|�����ō�������C�b���Ƃ������̂�����B��������������͐�发��R�����ė~�����B�嗤����`��������S�@�ƒb���@������ɓ����B�������������̒q�d�ƋZ�p�Ɋ��Q���邱�ƂƎv���B
���݂ɁA���{���̕�͕�����̂悤�ɁA�����Ɏ߂ɐꗎ���Ă��ĕ���ł͂Ȃ��i���R���ɂ��ƕ�/���̌`�͐F�X����ƊG�Ō`�������Ă����������̂ŁA����G�ɂ��ċL�ڗ\��j�B����͑���̓����Ŏ��Ƃ��i�荇���́A�������Đn���m�ő���̓�����̂ł͂Ȃ��j�ɁA����̓��̐n����ɐH�����ނ��Ƃ�����A����Ă͂˂邱�Ƃ��o����悤�ɂ��邽�߂ł���B���ꂩ�������悤�ɁA���{���͐��E�ɗ�����Ȃ����A�킢�̂��߂ɍ��x�ɍl�������ꂽ�n���Ȃ̂ł���B���̏�A�ʍ|���g�p���Ĕ������n���������A�������t�H�����Ől���䂫����B�����̂��̂̑���͂����܂ł��Ȃ����A����ɁA�����ꂽ�����̋Z�p�����Ă̑����I�ȍ�i�Ȃ̂��B
���Č����̘b�ɖ߂邪�A�Ϗܗp�̐n���͂Ƃ������Ƃ��āA���������ۂɎg���n���́A�n�悩���M�ɂ������������Y��ɖ��������Ă���ƁA�������Đ�Ȃ��Ȃ�B������x�A�������܂܂ɂ��Ă�����̂̕������B�����āA�����̕����́A��n��ɂ����Ăł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���{���̗p��ł͂��̌��������u��v�Ƃ����B�����߂Ɍ����̂́u�؈Ⴂ�i���������j�v���B���ꂪ���������ɂ����Ă̏c�����Ɍ����Ȃ薁���Ȃ肪�����Ă���ƁA�ꖡ���i�i�ɗ�����B����͐���̂ɑ��Đ�J�������ɂȂ��Ă��Ȃ����炾�B�G���Ȃǂ���Ă݂�Ή���B�܂��A���܂�s�J�s�J�ɖ����߂��Ă���ƁA�n��͐�Ă���̂�����������悪�����Ă����Ȃ��B�z�����݂��ǂ��Ȃ��̂��B
�Ƃ���ƁA�m���i�C�t�̃V���[�v�i�[�͂u���^�̍a�ɍ��킹�Đn��O��Ɉ������̂�_��̂��̂ŃV���[�v�j���O������̂����邪�A�ʂ����Ă��̎��ɏo���鍭�͐n�ɑ��ĕ��s�ł���B����ł́A�����ꂽ�ꖡ�͖]�ނׂ����Ȃ��B�������肵���ꖡ��]�ޏꍇ�ɂ͓u�ł̂������肵���z�[�j���O���s���ׂ��ł��낤�B�܂��m���i�C�t�͐n�g�i�u���[�h�j���S���|�ŏo���Ă���̂ŁA�d���Č����̂ɘJ�͂��v��B�n�g���S���|�ŏo���Ă�����͓��{�̐n���̂悤�ɓ�S�̒n�S����|�����`�����Ă��鑢��̕����i�i�Ɍ����₷���B�|������������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B���{���̑���ł������悤�ɁA�|���炩���n�S�Ŏx���邱�Ƃɂ��Ռ����z�����Č�����܂�ɑ��ċ����Ȃ�̂ł���B���₶����͍|�������������`�����Ă��邭�炢���ǂ��Ƃ����B������|���肪�o�����Ă���Ɛ܂�₷���Ȃ�B����̕����ł��n�����n��̋߂��܂Ŕ���Ă���悤�ɍ��̂��b�艮�̘r�O���Ƃ̂��ƁB���̏ꍇ�A�f�ނ̑��莞�_�ō|�ƒn���̐n��̐n��ɂȂ����ʈ�ɍ��킹�Ēb�ڂ��A�������M�̕�������n��Ɋ|���ĉΑ���̎��_����߂ɑł��Ă����B�����łȂ������̎��_�ō���Ď߂ɐn�t������̂��ƁA�ǂ����Ă��|���\�ɏo�����邻�����B
���̂�����̂��Ƃ́A�����Ă��镶����g�����̈Ⴂ������B���{�̐n���́A�ʐ肪�����Ƃ��ɂ��̑���Ƃ��Ċʋl���J���悤�Ȃ�đ傻�ꂽ���Ƃ͂��܂�v��Ȃ������悢�����m��Ȃ��B���{�l�͌×����n���⋾�A��ΗނȂǂɂ͍�������ƍl���Ă����l�킾�B���{�̎��R������{�̐H�̒q�d�A���{�̕����ɍ������D�����n���Ȃ̂��B����͎g�p����Ă���|�̌ł��ɂ��\��Ă���B�Ⴆ�Έ����|�Ƌʍ|�ł͐n�Ɛn�����킹��A�����|�i����ނ����邪�j�̕��������������B�����|�̐n�ŋʍ|��łƂPmm�߂��H�����ނƂ̂��ƁB�����āA�����m���i�C�t�Ɏg�p����Ă��鑽���̍|�̕�������ɍd�����̂��g�p����Ă���Ǝv����B�ڂ������̓��b�N�E�F���d�x�ׂĂ݂ė~�����B�����A�Ă����ꎞ�̍d���̓����Ŏ��ۂ̍d�����قȂ��Ă���͖̂ܘ_�ł���A�����ɂ͕\�ʏ�̐��l�ł͕\��Ȃ����\������B
���������{�̋ʍ|�́A�d���Ƃ͂����Ȃ��d�x�ɂ�������炸�A�悭��A�Ȃ����A����ɐꖡ�����������A�Ђ��Ă͌����₷���̂ł���B��炩���̂ŋC��t���Ă��Ȃ��ƌ���������ʂ��������B��X�͂Ȃɂ��{���I�Ȋ��Ⴂ�����Ă��邩���m��Ȃ��A�Ǝv���͍̂l���������낤���B
�܂��A�������Ō���Ɛn��͋���ł���B����Ɠ��l�ɐn�̕��������M�ɂ����Ă��A������x�A����ł��邱�Ƃ��K�v���B���̕�����R���Ȃ����Ƃ��R���Ǝ莝���̌���Ŏ����Ŏ����Ă݂��B�����̎d�グ�u�Ō�������ƁA�y�[�p�[4000�ԂŖ�������̐ꖡ���r���Ă݂Ă��A���̈Ⴂ�����炩�ɏo���B
���āA�R���͑��l�Ȏg����������̂ŁA����̕��͒����p�Ȃǂɔ����s���n�̕t�����A�^�͖�������A�d������肷��̂ŁA�����ɐ܂�Ȃ��悤�Ɍ��߂̐n�̋N�ĕ������Ă���B�ł��A����ɋ߂������s���n�̕t���������Ă���Ƃ͂����A�Ȃǂ�������Ƃ��ɁA�؋����ۂ܂�Ȃ����Ă������炢�ɂ́A�n���N�����Ă���B�؋����ۂ܂�Ȃ��̂́A�n���Q�����߂����B�Аn�̏ꍇ�A�Q�����������Ƒ�����ł��Đ�悤�Ȏg�����̎��ɁA�̐���������J���Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��낪����t���A�n���P���₷���B�����Őn�̕t�������Q�����߂��Ŕ����ƌ����������₷���̂��B�ނ��r�̍�������̂ŁA�����̘r�ɉ����ē����̐n�̕t�������H�v���Ă݂�̂��X�����낤�B
���ꂩ��A�������Ƃ��ɐn��Ƀo�����łȂ��̂́A�Ă����ꂪ�d������Ƃ��₶����͂����B�o���Ƃ����̂́A�n��̍|�̍�������Ƃ̔����c�����ł��ꂪ�n��ɂ����t���Ďc���Ă�����̂������B�d���Ă��������Ă���ƌ����ł���Ƃ��ɂ��ꂪ�o�Ȃ��B�킽���������Ă���O�O�̕ۑ��ł��n���̌�����́A����2�����g�p���Ă���A�o�����w�Ǐo�Ȃ����炢�̍d���Ă��������Ă��邪�A���܂̂Ƃ���g�p���Ɍ���������Ȃǂ̕s���R�͂������Ƃ͂Ȃ��B�������������g�����Ȃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���Ƃ͍���̎g�����݂ʼn��邱�ƂƎv���B
�o�����o���Ƃ��̌����̕��@�����B�����ł���n��u�ɓ��Ă��܂܁A���̂܂܋N�����ċt���ɐQ�����B�����č��x�͔��Α��������̂ł���B
���ꂩ��A���n�̐n���Łg���n�h��t�������Ƃ��̌������������Ė�����B���̔��n�Ɍ��炸�A���������ɂ͐悸�u����邱�Ƃ��炾�Ƃ���ꂽ�B�R���N���[�g�̕���ȂƂ����A�u�Γ��m�Ő��荇�킹�Ďg���₷���`�ɍ��̂ł���B�^�̉���ł���u�͎g��Ȃ����ƁB���ꂪ��肭�����������������B�i�����R���ɓs���̌Ó�����A���̓u�Ή�����A�i�C�t���̍ޗ���p�[�c�A������Ă���}�g���b�N�X�E�A�C�_�i����������H�Ɓj03-3939-0052�ȂǁA�F�X�ȂƂ���ɘA��Ă����Ė�����B���̒��ŁA�ʒ����̓u�́A�����̏@���n���̍����ʒ��u��\9000�A�����r��̓u��O���C���_�[�̐���Ɉ�������u�i�d�b�ԍ����ԈႦ�Ă���A�ԈႦ�����ɂ����f�����|�����Ă���|�̂��w�E���u���E�Y���Ē���������l�̕�����A���Ղ����̂ŁA����u����Ɋm�F���Ē��������Ă��������܂����B�Ftel03-3806-4452�Afax03-3891-7383�������ł��B�ԈႦ�ċL�ڂ�������ւ͓d�b����ꂳ���Ē����܂������A���{��ł܂��Ӎ߂������Əo���Ă���܂���B�܂����߂ĘA�������Ă����������l�т������Ē��������Ǝv���Ă���܂��B���A���������X�A���肪�Ƃ��������܂��j�ł͊m��\3800�ʂŔ����Ă����B���݂Ɏ����͑��a�̃R���N���W\1280���Ă��Ďg���Ă���B����u�ł́A�l���u���e������̔����Ă��邪�A�V�R�̓u�ł����[�Y�i�u���ȉ��i�т̂��̈����Ă���A�Q���~���炢�ł��ǂ����̂���ɓ���B�n�R�l�̂킽�����͂Q��T�S�~�ő啽�u�̔��[�A����͏��R���ɂ��Ɩؒ[�E�����ςƌ��������ł����A���̖ؒ[���Ė�������A����ŏ��R���̏�������������n�䂪�����ƕ����オ���Ă����B�A���A�����ڂ͑e�߂��B���݂ɐl���u�ł͂����͂����Ȃ��B�V�R�u�̎d�グ�u�̖ʒ����ɂ̓L���O��1000�ԂŐ���悢�Ƃ̂��Ɓj
�����āA���n�̐n���Ŕ��n�A�悤����ɔ��̒f�ʐ}�̂悤�ɐn��Ɋ|���ċȐ��Ŏ������Ă���n���B����́A�u��}�̂悤�ɐ^���������B�����Đn���������ɂ��āA�u�̌����������Ō����B�Ȃ����Ƃ����ƁA����ȓu�Ō����ƁA�ǂ����Ă������Ď�O�ɗ����Ƃ��ɐn������������̂Őn�悪�ۂ܂��Ă��܂����߂��B����Ă݂�Ή���B���n������A�Аn�̂悤�ɐn�s�ɑO�サ�Č����̂ł͂Ȃ��A�Ȗʂ����悤�ɐn��P���ċN�����Ȃ��猤���킯�ł���B���ꂩ��A�n��͓u�̌������̒[�Ō����ƕ������B�v���̓��{���̌����t���ǂ̗l�ɍs���Ă��邩�����グ�Ȃ����A���n������^�̃i�C�t�i��Ȃǔ������̂͑ΏۊO�ł���j�������̂ɂ́A����Ă݂鉿�l�͂���Ǝv���B���n�������ꍇ�Ɍ��炸�A�܂���X����邱�Ƃ͓u�̌`������Ă�����A���J�Ɍ��ɖ߂����Ƃł��낤�B��̐n�ł͌����ɂ��̈Ⴂ���������B�u��^������ɂ������̂���̐n����������A�Ă��߂�ɐꖡ���ǂ��Ȃ��Ďv���ʂ����|�����o����悤�ɂȂ����B�f�l�͂���Ȃ��Ƃ��悭�����Ă��Ȃ��̂ł���B���₻��͑f�l�]�X�Ƃ��������A��ʓI�ɐn�����g�߂łȂ��Ȃ�A�����ƈ�����l�����Ȃ��Ȃ����ƌ����ׂ������m��Ȃ��B
�{��ǂ�ł�����A�u�̃����e�i���X�̂��Ƃ��g�쓁�̓`���Z�@�h�ɋL�ڂ���Ă����B
�g���āA�b���O�シ��悤�ł����A�ǂ�ȏꍇ�ł��u���g�p����O�ɂ͕K���T�\����U�i��������A�����Ă���j�����܂��B�\����Ƃ́A�g�p����u�̕\�ʂ𒆉�������⍂���A���ʂ����Ⴍ�A�X�ɐ����Ⴍ�A���傤�NJ��g�`�ɕۂ��߂ɁA���̓u�ł����Đ����邱�Ƃ������܂��B���̂悤�ȓu�ʂɂ��邱�Ƃ́A�����u�ɏ[�������邱�Ƃ��l���������̂ŁA����ɂ�����M�������₷���A���u�����̑��������̈ӂ̂܂܂Ɍ����邱�ƂƂȂ�܂��B�u������Ƃ��̌��t�̎��͂��킩��Ƃ����܂����A�Z�p�̍������t�͂��̓u�ʂ�����ʂ悤�A��ɒ��ӂ��܂��B�������u�ʂ�����邱�Ƃ�����ł��傤���A�܂���ɗǂ���Ԃɕۂ��߁A���̂Ǖ\����������܂��B�h
�y���͎���z
���̊Ԃɂ킽���͎���ł����ƕ������B�ގ��͍��h�ł���B���ꂪ�d���ނȂ̂ŘJ�͂�������B�������ŃR�c�R�c�ƍ���č�����B�Ȃ�Ƃ����Ă��n�̕�������̑ł��n��������A��������Ȃ͓̂��R���B
�莝���̌���ƁA�ے��������g���č��B���X���Ȃǂ͂������ɍ�����ؒn���̂܂܂ŁA�֖��ł����ς��ďo���オ��B���C���h�ȎR���Ɏ����������d�オ�����B�ł��A����Ă݂ĉ��������Ƃ́A���h�ނ����N�̂܂܂ŕ��Ɏg���̂́A������x�̃��X�N���o�債�Ă����������悢�����m��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B�Ȃ��Ȃ���ƐƂ��̂ŁA��������ƍׂ������Ȃǂ͂�����Ƃ����Ō��Ŕ�����Ă��܂��Ղ��A�܂��Ђт�����Ղ������m��Ȃ��B���h�ɂ����낢�날��A�̍�������̂ŁA��T�ɂ͂����Ȃ����A���h���g�p���ă��N�̂܂ܕ������̂́A������x�̎�ԂƎU���͊o������Ă����������悢��������Ȃ����A�����Ռ��ɂǂꂾ���ς����邩�͖��m�����B���A���Ȃ芣�����������́A���q���������ތ���啪�Ă�������ł���B
�@
�y�g�ݕt���z
���̕��Ƀn�J�}�����������݁A���̂̂����Ƀh�����ŏc�ɂR�{�̌��𒆎q�̌`�ɍ��킹�ĊJ���A�����ɏĂ����S�̔��������݁A���q�i�Ȃ����F���ɓ���Ƃ���B�s�Ƃ������j�̓���傫���Ɍ����Ă��Ċg����B������x�ł�����A�n�g�̍��{�̂Ƃ��뒆�q���Ă��č������݁A�Ō�͌y���ł����B�����Ƃ��A����͐n�g�ɃX�g�b�p�[���t���Ă�������o�����r�Z�Ȃ̂ŁA�ʏ�͐n����Ɍ����ĕ��̐K���d�����̂ɑł����낵�ē��邭�炢�̑傫���ɂ��Ă����ׂ��ł��낤�B���q�͐�[�̕���Ԃ��Ă��Ă���̂ŕ��̌��̉����Ă��Ȃ���g���Ă����̂��B���̑傫���͑�̍��킹�Ă���n�J�}�������������Ă��邪�A����ł����̃n�J�}�̕����ɂЂт�����ꍇ������B
�܂��A����̓��N�̂܂܂̕��Ɍ����J�����@���Ƃ������A�����f���ȖؖڂȂ�A���������Ē��q�̕������������A�ēx�ڒ�������Y��ɏo����͂����B
���̒��q��m���i�C�t�ł̓^���O�Ƃ����B�m���i�C�t�̏ꍇ�ɂ́A���̃^���O�����̐K�̂Ƃ���܂ʼn��тĂ�����̂�A���̌`���t�ɍ���Ă���A�Ō�ɕ��ƂȂ�n���h���ށi�A�p�A�v�A�S���Ȃǁj�����E�ɓ\��t����t���^���O������B���x�𑝂����߂ɂ��̂悤�Ȃ���ɂȂ��Ă���̂����A�̂���̓��{�̐n���ɂ͂��̂悤�ȑ���͌�������Ȃ��B����̂́A���m�}�^�M�̎g������Ńt�N���i�K�T���炢�ł��낤���B����͐n�g����̂̂܂܉��тĂ��ĕ��̂Ƃ���ŁA��i����j�ɂȂ肻�̂܂ܕ��Ƃ��Ďg�p������̂ł���B�́A�e�̐M�������Ⴉ�������́A���̑�̂Ƃ���ɒ����_��}�����Ƃ��Ă��g����悤�ɂ����ׂ��������B���̒��q�̌`��ɂ��ẮA�����̊ԂɏՌ��Ńn�J�}�̕����╿���ɂ�Ŋɂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��l�����邪�A�̂��炱�̕��͊e�������傪�D���Ȃ悤�ɍ���Ă�����p�ȓ��{�l������A�ɂ�ēx���悢�Ƃ����Đ��Y�I�l�����ł������̂ŁA���x�����d����o�����X���D�悳��Ă���B�܂��A���̍ގ��ƌ`��Ɉ˂��Ď�Ɏ�Ռ����z�����邱�Ƃ��l������Ă���̂ł��낤�B
| ���N�`���F��Ȃǂ́A�悭���̍��{�̕�����K�тĂ��Ă��܂��B���̒��̕����̒��q���A�������̔G�ꂽ���̂��߂ɎK�����N�̊Ԃɉ���Ă��܂����炾�B�ł��A �����n���͒��q���������ތ����Ă��Ă����B�Y�����邱�Ƃɂ���āA���̉e���������킯���B���₶����̐n���͒��q�̌����Ă��č��B�����āA��Ȃǂ͒��q�̌��݂�n����肳��ɂ��Ă���B������K�тĕ��H���Ă��A�����ɍׂ��Ȃ��Ă��܂�Ȃ��悤�ɂ��B |
�y�����z
���ƒ��q���h�����Œʂ��Č����J������ɁA���̌��ɖړB��ł��A�n�g�͕� �ƌŒ肳���B�킽���͖̂ړB���{�ł����B
�ړB�͓�炩���S�̖_����ĊJ�������ɍ�������A�����̏�ŋ��Ƃŗ������y���ׂ����B�������邱�Ƃɂ���āA���ɊO���Ƃ��́A�B�Ȃǂ̓������炢�̑����̋����̖_�Ăđł��ƂŊȒP�ɖړB��������̂��B�����āA�Ō�ɖ����Ă����ς��ďo���オ�肾�B
������A���₶���烆�[�U�Ɏ�n�������B���̎ʐ^�̎�҂͍������Ȃ̂ŁA���p�̂��̂�����Ė�����B�R���͕Аn�Ȃ̂ł���B���p�̕Аn�͎s��ɂ͖ő��ɂȂ��B
��ł��Đ�ȂǍr���g�����⍶�E�����Ƃ��g�����Ƃ������l�͗��n�̕��������Ă��邪�A��͂�Аn�̕����悭���̂͂�����܂��B���������₷�����A���������Ղ��i��̔�ނ��ɂ͌����Ȃ����j�B�����J���Ƃ����A�n���������Ɠ����Ă����B������A�z�����݂��ǂ��Ƃ���������������B
�@
| ���N�`���F���{���̖ړB�ɂ͒|���g����炵���B�Џ@�|�̐߂̕������g���Ƃ̂��ƁB���̎R���̖ړB�ɂ́A���ɓ�炩���S�̖_����đł����B�ēx�O���Ƃ��́A�B�ȂǂĂđł��o���Ύ���B���̖ړB�ɍd�����̂��g���ƁA�n�ɏՌ������Ƃ��ɒ��q�̕����ɂ�ł��܂��̂ŁA��炩���ނ��g���Ƃ��������ł���B |
| ���N�`���F�b���ɂ���Ēb�����|�͎K�тɂ����A�K�т�̂͒��ɕs��������������ł���A�Ƌ����Ė�����B �b�����|�́A�Ҍ���p�ɂ���Ĉ��肵�����K�iFe3O4�j�ɕω�����̂��낤���B |
�@
���̎ʐ^�̏�́A�����p�̍��Аn�B����3000�Ԃ̎����X���Ŗ����Ē֖���h���Ďd�グ���B�n�n���16cm�őS�̂ɂ�����Ə��U��B
�E�̎ʐ^�̉��́A���Ǘ���ł��܂������n�̂��́B�n�n���20cm��ł���قǒ����Ȃ����̂́A�n�ЁA�n���A�d�ʂ�����A���n�̎d�グ�ɂ����̂Ŗ�O�ł̃��t�ȍ�Ɨp�B�ŏ����Ƃ��ɂ́A�O���b�v�̂Ƃ����ʔ������ĎR����������Ă������A���ۂɂ͎g���ɂ����̂ŁA��N�͎R�����Ȃ����ĒႭ�ۂ����A�ł����낵���Ƃ��̑Ō��V���b�N���w�ɗ��Ȃ��悤�ɂ����B
�y�~�o�`�� �R�� �d�l�̊T�v�z
�n�g�F��S
�|�F�����|���i�P���炵���H�j�E�E�E����ς�����(^^;;
�n�ЁF35mm
�n���F5mm�i�E�p�Аn�j
�n�n��F�U���i18cm�j���킽���̂��� m(_ _)m �@���̐l�̐��@��16cm�B�ȉ��̎d�l�͐l���ꂼ��Ȃ̂ł킩��Ȃ�
�S���F��ڈꐡ�i33cm�j
���d�ʁF330g
���F���h���N
��F���i�����j�ނ̗\��
��p�F�n�g���P���Q��~�B
�ւ��ւ��� (^-^;;�@����͈�����ˁH�i���p�͍��̂�������߁A��悹�������ǁj�����̋C�ɓ������`�ɍ���Ė�������A�����Ȉ����|���P�����g���Ă��܂�����ˁB�ł��A���h�̕��̍ނ�\1300���|������������B�֖������ނ��莝���̂��́B�����A��Ɉ�ʓI�Ȃ��̂��g���Ƃ�����A�O�̃X�m�R�p�Ƃ����̂��A��^�X�̖؍H�ނ��Ă���Ƃ���Ő��S�~�Ŕ����Ă���B���Ƃ͂��₶����Ɏ����Ă������Ē���r�[����B���ꂪ���\�|�����Ă��邪�A�o���ƒm���̂��߂̎��Ɨ��Ƃ����炤��ƈ����B�ł��A�ׂɂ��ׂ̈ɂ��낢�닳���Ă��ꂽ�킯����Ȃ��āA����ς�C�����ƋC�����̖��ł��傤�ˁB
�������l���Ă݂�ƁA�����ڂɌ����Ȃ��Ƃ���̔�p�����Ȃ�|�����Ă��邩���m��Ȃ��B����̎R��������邽�߂ɁA������������A�����X�������낢��ȔԐ����ނ����B�u�͍����́A�r�A���A�d�グ�Ǝ����Ă�������ǂ�����ǁA��������U��~���炢�ɂ͂Ȃ�B�܂��A�������ꍞ��ŋÂ����Ⴄ���Ȃ̂ŁA�K�v�ȏ�ɓ���𑵂�������͖̂��x�̂��Ƃ����獡�X�ł����A�V�тƂ��čl�����猋�\�y�������[�Y�i�u���Ȃ��̂ł��B�Ȃ�Ƃ����Ă�����Ƃ��Ď��p�I�ȍ�i���茳�Ɏc��̂ł�����A����������̎�ňꐶ������������̂ł����爤��������܂��B���������V�т��Ă����ł��ˁB
���݂ɁA�r�����̒b��B�̘a���i�C�t�A�����L�x�Ɉ����Ă���@���n���̃J�^���O������ƁA�R���Ɠ��T�C�Y�̐��P�����g�p�������n�̂��̂Ńt���^���O�̑���A�C���h�Y�T���o�[�X�^�b�O���p�̃n���h���A�V�[�X�t���̂��̂�\65,000�ŁA��������Ă���ꗬ�b��̍�i�ł��B���ɗL���Ȓb��̂��̂ł��P���~��̂��̂���R���~��̂��̂܂ő�������A�݂ȏ�܂ŕt�������z�ł��B�܂����̂��͍̂��߂ł����A����̈Ⴂ������P�Ɏg�p���Ă���|�̎�ނ����ł͉��i�͌��܂�܂���B���ꂼ�ꖣ�͓I�ȍ�i����R����܂����A�|�����Ă����Ԃ≿�l����l����ƈ����Ǝv���܂��B�ł��A��͂�ʍ|�̂��̂͂O���ꌅ�Ⴄ�B��x�͎g���Ă݂�������ǎ����݂����ȕn�R�l�ɂ͂Ȃ��Ȃ��肪�o�Ȃ��ł��B�����āA�R���Ɏ����Ă����Ă������藎�Ƃ��Ă��܂������Ƃ��l����ƂˁE�E�E
���͗��n�̂��̂���{���������ǂ����v�Ē��ł��B���₶����͏H�ɂ͈��Q�ɍs���Ă��܂��Ă���̂ł�����A���ނ̂ł���Α������Ȃ��ƁE�E�E
�y�R��z
���n�̂��̂�����ĖႢ�܂����B�R���Ɠ������炢�̃T�C�Y�����肢������肾�����̂ł����A�����悤�Ȃ̂����{�������Ă��d�����Ȃ��낤�A�Ƃ������₶����̂��l���ň���傫�����̂�����ĉ������܂����B��ƌ����ɂ́A������Ə����������m��܂��A�i�C�t�ƌ����ɂ͐n�Ђ�����܂��B�|�͕�̋߂��܂œ����Ă��邻���Ȃ̂ŁA�����Ԃɂ͌��������ē��݂����Ȍ`�ɂȂ邩���m��܂���B
�O���C���_�[�ł̐n�̌���ƁA�u�ł̌����͎����ł��܂����B�b�艮�ɂȂ肽���Ƃ������Ă���̂������玩���ł���Ă݂ȂƁA���₶����͐����ς���Ă����̂ŁA�r�r���Ȃ���O���C���_�[�Őn�Ă܂����B
���ƌ����Ă����n�ł��B���\�Ƃ��Ȑ��Őn��Ɏ���������̂ł�����A�ȒP�Ƃ͌������������̂ł��B�ł����̑��肪�ǂ��̂ŁA���ƃX���[�Y�ɏo���܂����B�����͍r�����������Ėʂ�ɂ��܂����B���₶����́A�ł炸�Ɋm�F���Ȃ�����A�Ƃ̌��t�ɏ]���ď����Âo��������Ȃ���̍�Ƃł��B
�����Ƃ��́A�n���������ɂ��Ĉ����Ȃ���n��t���Ă����̂ł����A�E�͏o���Ă����͗�����łȂ��̂ŁA��肭���n�������܂���B���₶����͂����Ǝ�������ς��āA����Ŏ����Č����Ȃ��Ɛn���ۂ܂��Ă��܂��ƌ����̂ł����A���₶���Q�����Ƀ`�����{�ł��B�E��ʼn����Č����܂������A��肭�s���܂����B�����Ɛ�܂��B
�����A���R�̔����ɒʂ蓹���J���Ȃ��玎��������Ă��܂������A����ς蔸�n�͋����ł��B�o�b�`���ł��B
�ł��A������ނ͓̂��ӂ��Ⴀ��܂���B�����āA�n����7mm�����锸�n�Ȃ̂ł�����A�����Ȃ�����Ȃ��Ă��܂����̂ˁB�ɒ[�ȕ\��������Βf�ʂ͂u�̎��Ƃ������t�̎��ɋ߂��ł��B�������A�R��̖��_�̂��߂Ɍ����Ă����܂����A�Аn�̎R���Ɠ����悤�ɁA�G���̒[�̕��͎��̂��Ƃ��ׂ���邭�炢�ꖡ�͉s���ł��B�|�����炢��܂��B(^-^;;;
�y�~�o�`�� �R�� �d�l�̊T�v�z
�n�g�F��S
�|�F�����|���i�P���炵���H�j�E�E�E����ς肱��܂��Ⴂ�܂����B�ł��ǂ��n���t���܂�
�n�ЁF45mm
�n���F7mm�i���n���n�j
�n�n��F19.5cm
�S���F35.5cm
���d�ʁF510g
���F���h���N�i���ǁA��������h�ނ̃��N������܂����B����ς葽���Ђъ��ꂪ�o�Ă��܂��B���x�̍ނ͊��ƔS��̂������̂Ŋ��҂��Ă����̂ł����A�g�t���̂Ƃ��ɂǂ����Ă��o�Ă��܂��܂��B���ɂ��o���T���_�[�Ƃ����[�Y�E�b�h�Ȃlj���ނ��̗m�ނ̐F�̔Z�����̂ō���Ă݂��̂ł����A���h�ȏ�ɐƂ�������A�ڂ��f������Ȃ��̂������̂ł̂Ŏ~�߂Ă����܂����B�܂��A�Ԋ~�Ȃǂ��T�����̂ł����A�f�p�[�g�n�̑�^���X�ł͈����Ă��܂���ł����B�~�ނ����������Ƃ���ɗ���q�w�ɂ͎��v�����Ȃ��̂ƁA�����ɂ͉��i����������̂ŁA�s���̍ޗ�������ł͌����ɂ����悤�ł��B����̍����n�g�ɔ������͎�����Ȃ��̂ŁA�ÐF�n�̂��̎g�����������̂ł��j
�y�E�l�������鐢�E�z
���āA�@�����̋{��H������������ꂳ��̒����u�̂��̂� �̂�����v���v�Њ��ɁA�n���̘b����R�o�Ă��܂��̂ł��Q�l�ɁB
------�ߍ��̓���͐̂ɔ�ׂĎ��������Ă܂��B�S�̍�肪�Ⴄ��ł��傤�ȁB�S�͍d��������Ƃ��������Ȃ���ł��B�u���ܐ�v�Ƃ����܂��āA�_�炱���Ă悭����������ł��B����Ȃ���ɂ͂߂����ɁA�o��܂����ȁB�d���n���͍d�����̂ɉ�܂��ƁA�ς��Ɛ܂�܂��B���ܐ�̂��̂������A�Ȃ��邱�Ƃ͂����Ă��A�܂�܂���B����ł��Ď��Ԃ����Ɛn���߂�܂��̂�B���{����̂̏�������̓��{�䓁�Ȃɂ͂����S���g���Ă��܂����ȁB------
�b�艮�̂��₶���畷�����b�ł��B�����g������́A�Ȃ������肷�邱�Ƃ�����炵���̂ł���������̂́A���̂܂�̏�ɒu���Ă����̂������ł��B�����Ĉ�Ӓu���Ă����ƌ��ɖ߂�Ƃ������Ƃł����B����͐n�łȂ��āA���S�̘̂b�ł����B�s�v�c�ł��ˁB�ł��A�����n���͂����������̂̂悤�ł��B
�������d�`���̍�����A�ʍ|�̓��{�䓁�́A���e�t�����u�Ɋ|���������Ő玵�S�����̋q�ɂ�����A�܂��ʂ̗��e�t�͂R�N�R�����̊ԁA��x���u�Ɋ|���Ȃ������A�Ȃǂ��̐ꖡ�ƑΖ��Ր��͐M�����Ȃ��������c���Ă��邻���ł��i�a���i�C�t�̐��E���j�B
�܂��A��������͂��̂悤�ɂ������Ă��܂��B
-------�┒�P�̍H�l�ɂł������Ƃ��A���オ�i�ނɂ��������Ăł���悤�ɂȂ�Ƃ����̂́A�����r�̂���������܂����A������g���H���̐S�\��������Ă�����A�̕Ȃ����ނ��Ƃ�Y��Ă��܂����肵������ł��ȁB���������Ȃ��Ă���������ȑO�̖��ł����A���ꂪ����ɂ�������ł��B ����̎�����������Z�p���S�������܂��ȁB������������ł����B------
��������͍��̓d���H��ł́A�̖ʂ��r��Ă��܂��̂ŁA�̂Ɠ����̎����ۂĂȂ��ƌ����܂��B��Ƃ����͖̂Ɩ̍זE�̊Ԃ��A�X�J�b�Ɛ�B����ƁA�\�ʂ��Y�킾���琅�����܂�Ȃ����A�����͂�������ꀂ��͂��Ȃ��B����őϗp�N���ɑ傫�� �Ⴂ���o�Ă���ƌ����Ă��܂��B������A�̂̌����́A�����̖Ɠ�����g���q�d�ƋZ�p�Ƃ���������߂Ă��邩�牽�S�N���牽�S�N�������Ă���̂��Ƃ̂��ƁA�������Ă��܂��B
���ꂩ��A�n�����������Ƃɂ��āA����������Ă��܂��B
-------�n���������Ƃ����̂͂ǂ��������Ƃ��Ƃ����܂�����ȁA�l����͋����܂���̂�B������q�̏���ɂ������̂́A�����ō��������������܂��āA����Ȃӂ��ɂ��A���������������ł���B
�@���̂���������������ł����B��̏�����u���܂��āA��Ƃ����̂͂������������ƌ����܂��ĂȁA�L�Z���̊��i���сj��������������܂��āA�����ƈ�������܂������B������ǂ��ɂ��o�Ă��܂���̂�B����ŁA�����ӂ��Ɛ��������܂��ƁA�Ђ��Ђ��Əo�Ă��܂����B�����āA�u���Ȃ��ӂ��ɂ��̂�v�Ƃ��������ł���B------
�E���{�̒q�d�F�b�艮����ɓ��{�×��̒b���@�Ńi�C�t������Ė����
�E�y�l�@�Ƃ��肢�z�O��
�E�y�l�@�Ƃ��肢�z�㔼
�E�y�ԊO�ҁz�ɂ킩�b�胏�[�N�V���b�v
�E�y�X�ɔԊO�ҁz�t�C�S�ŒY�������A�Y�Ă��o�[�x�L���[
�E������̏��R���쏊`01/2
�E��ł��둼�A���їp�̗ǂ�����ނ���ɓ����`01/2---�n���͎g���ĂȂ�ځB�g��Ȃ���Ηǂ��͉���Ȃ�
�E�t�C�S�ɌĂ��`01/2---�b��̐_�Ɍ����܂�Ă��܂����̂��낤���B�~����������̏㕨���i���ŁI
�E���Ó���E�u�Ή�����`01/3---���Ȃ������ŏ[�������ݔ��B�V�i�H �v����낤�B�B�B�O�O�ɒT���Ώo�������邠��
�E�Α���V��`01/6---���삩��l����b���i�C�t��ɗ����B�I�C�A�~����A�A�u�˂��Ȃ��B�i�C�t�U���.....���āB(^^;;
�E�V�����o�����i�C�t�̎d�オ��ׂ邽�߂ɁA�����̎w�Ŏ������o�J�ȓz�̘b�B�p���������̂Œm�荇�������ɂƎv���Ă�������ǁA���̐����w�̏C�����@�͌��\�L���Ȃ��Ƃ��o���ω��ʼn������̂ŁA�����Ēp��E��Ō��J�B����ς�A�菝�ɂ̓A�����A���t�@�ł���I--`01/11/14
�E�����}�^�M�[���H�[���i�C�t�A�R��F�܂��ǂ����b�ɂȂ��Ă���[���Z���̃i�C�t�̏Љ�y�[�W������Ă��܂����B����ɂ̓s�b�^����B
�E���b��̂Ƃ���ɂ��ז����Ă���'02/�H
�E���ʋM�d�����F�菑�t���A�����p���{������܂��F�����ۂ̔F�菑�t���A�����كN���X�̂��́g���㚠�Z�����h�B�m�l�Ɉ˗����ꂽ���̂�Web�T�C�g�ɂ��A�b�v���܂��B�����̂�����ɁB`03/7/5
�E�Ƃɂ��铹��Ō������Α���H---�Â��g������Ń{���{���ɂȂ�����⊙���A���ƌ�����V��������Ό��ʂ�Ɋ���ł���B���̌��������ɂ́H
�E���̎�̎g���Ղ��_�H---�Ƃ̋ߏ��̋���������Ɋ��������̎�Œ|�Ƃ�ڂ�����Ă����B��o�������Ȃǂ��ӊO�Ǝg���Ղ����̎�̌`��Ƃ́H�H�H���āA�債�����Ƃł͂Ȃ��̂����ǎ�芸���������Ă݂܂����B(^-^;;--`04/12/5
�E�����}�^�M�A�i�C�t���[�L���O�����H`06/3�F�M�Y�������J�C�f�b�N�X���g�����V�[�X�i��j���&
�R�L�m�R�̂苳���̕��i
�E����������ǖ{���B�~�j���c��u�b�艮�̌ւ肪�Ă����Ă�����H�v`06/8---�g��̃~�j��h�Ƃ͏����Ă���܂������
�E�����}�^�M�[�������̒��ԂƂ̃L�m�R�������̉� `07/11/20---���X�L�m�R�����F���i�����z�̓L�m�R�̂�Ȃ��`���B�y�������ԂƂ̃L�m�R�̂�̕��i�ƁA����������������o����悤�ɂȂ��������ł��̃v�`�����B���i�����z�قǔ\�����������I�I�I���āA�A�A�N�̂��ƁH
�ECT110�n���^�[�J�u�̂��̌�---�����ƕ��i�����B������CT�A�����CT�B���i����j��m��ƌ����Ă�...
�E�V�K�i�ȑO�̎l��y�g���̂��E��---���̓� ---�X�s���`���A���y�g��-���C�t�B�ǂ��g���h����ɓ��ꂽ��---`05/1
�E�g�R�d���̓���ƋZ�p�A�q�d�́A�����Ǝ��q�̊�{�h�i�Ёj�S���ыƉ��Ǖ��y����@�X�ƕ�炷No.�Q�u�m�E�n�E�}���R�d���̓���v�i`08/6/10���s�j�̂��E��-----���������A���_���w�A�c�ɕ�炵�A�_�I�����w���̕��X�ɕK�{�H�@���R�Ƌ��ɕ�炻���Ǝv������R�ƖX�������Ă����B�{���́A�R���щƌ����̓���҂̖{�����A�R�̍�ƂƓ���Ɋւ�邱�Ƃ�����S�Ǘ��܂őS�Ă�ԗ����Ă���B���T�C�g�Ǘ��҂��A�b�艮�̒q�d��A����ނ̏C���C���A�M�Y�������J�C�f�b�N�X���g������⓹��ނ̏�i�V�[�X�j���̃y�[�W���V�O�łقǏ������Ė�����B���H�I�Ȓq�d���Ă������{�Ȃ̂ł��E�߂߂���B---`08/6/11
�ERoom full of mirrors�֖߂�
���E�߂̃T�C�g
�E�����琻�S�̏ڍׂ�a�|�̗��j�ɂ��ē��������i���j��Web
�E�t�C�S�̏C������������Web
���E�߂̖{
�g�b�艮�̋����i���R�S�O�E�l�Ȃ��j�h�����܂Ƃޒ��@���w�ٕ��Ɋ��F��Web�������Əڂ���������Ă���B����ς�ɂ߂��E�l����̘b�͖ʔ����B�����āA�r�N�b�Ƃ����̂́A�b�艮����̕��ł͋q�̘r�̒���b�̒��ŒT��Ȃ���A�q�̃��x���ɍ��킹�ďĂ�����Ă��߂��Ȃǂ��s�������̕i���d�グ�Ă���Ƃ����b�B
�G���g���s�^�h���w�فF�ŋߋC���t�����̂����A�S���̒b�艮���肪��L�̒b�艮�̋����̒��҂ł��邩���܂Ƃގ��ɂ���Ė����f�ڂ���Ă���B`98�N�łS�N�ڂɂȂ����������B�킽�����ȑO���������Ƃ����邪�A���̍��͋������Ȃ������̂Ō����Ƃ��Ă����B���s�^�̌Â�����T���A�F����̋ߏ��̒b�艮�������邩���m��Ȃ��B
�����ۂɉΑ�����s������A�n�����g�p������X�ɂƂ��Ď��p�I�ȏ��Ё�
�g�M�����̂��͂Ȃ��h��a�v�d�Y�� ���{�K�i��� \1200�i�ŕʁjISBN4-542-90108-4 �F��̒ʂ�����̔M�����ɂ��ĕ�����Ղ����ڂ���������Ă���
�g�n���̂��͂Ȃ��h����쐶�E���G ���� ���{�K�i��� \1800�i�ŕʁjISBN4-542-90202-1 �F���E�̐n���̗��j�Ɏn�܂�A�n�̌������ɂ��n��̏�Ԃ̏ڂ����ʐ^���f�ڂ���A�����̏�ԂƂ��̐��\��r�Ȃǂ̊e�������ڂ����f�[�^����Ő�������Ă���
�g��Ɠu�h�ēc�u�b�N�X�� \1800�i�ŕʁjISBN4-388-05843-2 �F��̉Α��肩�猤���A���t���܂ł̐���ߒ����ڍׂȎ� �^����ŁB�܂��v���̕�̌��������ʐ^����Ő�������Ă���B�����āA��̏C���ƕۊǂ̎d���܂ł�����B�܂��v���̗����l�B�̕�ɂ��Č����e�����ɎQ�l�ɂȂ�B�㔼�́A�u�ɂ��āB�V�R�u�A�l�H�u�̏o����܂ŁB�u�̃v������̃��b�Z�[�W�ȂǁB�n�����������X�ɂ͔��ɎQ�l�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv����B