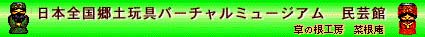
----長崎県篇・第5回----
---- NAGASAKI(5)----

|
■壱岐の八朔雛■ 壱岐の八朔雛の特色は、男女の雛に着せ替えの装束がついていることです。そして、それぞれに「おきぬ」という着せ替えの装束が付けられています。 八朔の日(旧暦8月1日)には、初めて八朔を迎えた女の子の家へ、この八朔雛におしろい花を添えて持って行きました。雛を贈られた家では表座敷の長押(なげし)にそれを貼りつけ、おしろい花は神棚へ供えました。 おしろい花は、美しい娘に育つように、また茶袋のお茶は、植え替えることができないという意味で「永遠の良縁」に恵まれることの願いからと、伝えられています。 最近では八朔の行事も知らない人が多くなり、風化していくのを惜しんで、これを後世に伝えたいと、平田増枝さんが旅館の女将をするかたわら、欲しい方に作って送られていました ◆現在(2008年)、「八朔雛ヒメゴジョサマ」を制作研究されている宮本真理子さんから、最近ご連絡いただき、その情報を次に記載しておきます。 宮本真理子さんからの情報: 『平田様のお話ですと、長女のできた家から親類に八朔雛を作り贈ったとのことで、長押にずらーと飾ってあったのを覚えているとのことでした。 「タノモ」という行事・風習だったようです。両方の場合があったのかしらと思っています。 参考までに 一番古い資料の「壱岐島年中行事」山口麻太郎氏著 には 八月に次のように書かれてます。 タノモ ― ヒメゴジョ様と云って男女一封の折雛を作り、更にオキヌと云って色紙でキヌを二枚切り、女児の初節句の家に贈る。受けた方ではこれを梁や神棚に貼って内祝ひをなし、出来たものを親戚に配る。白いかづらの花(何草か知らず)でヒメゴジョ様を作り紙の衣を着せて荒神様の下に貼るといふものもある。 他に「壱岐島玩具誌」横大路明氏著にも詳しく掲載されています。 なお製作者・平田増枝(弁天荘)、弁天荘さんは おばあちゃんはお耳が聞こえないので・・とのことでしたので何かありましたら 私、宮本のほうにご連絡下さい。 では、よろしくお願い致します。 連絡先: 壱岐市郷ノ浦町本村触631-4 宮本真理子 0920-47-1940 (記録)元、製作者:平田増枝(弁天荘):壱岐郡郷ノ浦町片原触 ■犬乗り猿■ 掲載の右の2点は長崎県篇・第2回に掲載た「長崎焼」の作品です。 左の1点は、熊本の「木の葉猿」ですが、同じ形の人形として収録しました。 ■南蛮船(唐人船)(廃絶)■ 右2点は長崎くんちに出る船を模したものです。ここに収録したものは、残念ながらいずれも廃絶しています。郷土玩具の愛好家や研究家からは、復元を望まれているもののひとつです。 |
| ▲‥[Back] 長崎県篇(4) | ---長崎県篇・終--- |
▼‥[Next] 熊本県篇(1)

|
(1999.8.22掲載)