しかし、ウィーンやベルリンといった地に彼はとどまらず、生地のフリブールに三十才で戻り、教会でオルガンを弾き、音楽学校で教える生活を始めたのでした。
この辺りは師のメシアンを思い起こさせます。一九六五年からは、フリブールのエコール・ノルマルで教えています。更に、音楽雑誌の編集、評論をする傍ら、地元の合唱団や(スイスには各地にある)アマチュアのバンドの為の小品を提供する、作曲家としては極めて地味な活動をしていたに過ぎません。
彼が、このような地味な活動に甘んじていたのは、フリブールの極めて保守的な風土があったのではないか、とCDの解説にありましたが、 カトリック教徒の州という事情が彼に前衛音楽を許さない土壌となっていたのではないかと思われます。
それと、きっかけとなったバッハの音楽への傾倒も、それにオルガニストとしての立場もそこには関わっていたのではないでしょうか?
また、その頃出始めた、極めて前衛的なブーレーズ、シュトックハウゼン、ジョン・ケージらの音楽からは、彼の音楽はまだ古典の殻を被った卵であったとことから、彼の音楽が世間に受け入れられなかったこともあると思います。
しかし、一九七〇年頃からの前衛音楽の変化、ネオ・ロマン主義や、宗教性に根ざした音楽にトレンドが変化していく中で、モレのような音楽が受け入れられる地盤が整備されて来たという事情が、彼ノルベール・モレをかくも現代スイス作曲界の最重要人物の一人に押し上げているのであると思われます。
実際この間に出てきた作曲家たち、ロシアのグバイドゥリーナやシュニトケ、あるいはエストニアのアルヴォ・ペルトといった作曲家たちの作品が、大きくクローズ・アップしてきたことと、モレの作曲活動の再開というか、その活発化は並行して起こってきたことです。
ムターがティチーノ州の魅力的な音楽祭である、アスコナ音楽祭でその初演をしたヴァイオリン協奏曲「夢の中で」(CDが出ています)やルツェルン音楽祭で初演された「ディオティーマの愛の歌」(この曲は未聴です)など、モレはスイスの音楽界でまさに重鎮としての存在感を示し始めています。
かのロストロポーヴィッチが数年にわたって懇願し、ようやく完成したチェロ協奏曲(一九八四〜五)は、モレとしては珍しく伝統的な曲名を与えられた作品であります。一九八八年にチューリッヒでロストロポーヴィッチのチェロ、パウル・ザッヒャー指揮チューリッヒ・コレギウム・ムジクムのメンバーで初演されたこの作品は、まったくそのメンバーによる録音が残っています。
三楽章制の作品で、第一楽章が「時を過ごすための歌」、第二楽章が「愛の歌」、第三楽章が「西風の歌」というタイトルを持ち、イギリス・ロマン派の抒情詩人シェリーの詩を暗示しているとも言われています。
一楽章ではチェロはやや短い楽句を並べ立て、オケがそれを拡大していくかのような作品となっています。二楽章では息の長いフレーズが歌い込まれ、三楽章では、無窮動風の目まぐるしく動く音楽となり、この面でも古典的な枠を守った、珍しい作品であると言えます。
但し、語法は明らかに前衛的というか、現代的でオーケストラの機能をよく生かした作品であると考えます。
このCDにはザッヒャー指揮バーゼル交響楽団による一九七七年の作品「沈黙への讃歌」もおさめられています。
スイス音楽界の大立者、パウル・ザッヒャーの委嘱による作品で、大変雄弁で静かな音楽であり、七〇年代の作品であることを強く思い起こさせる作品となっています。
沈黙に対する捉え方は、東洋人たる私たちとは随分違って居るように思えますが、一種の瞑想的な世界観の中にコミュニケーションの手段を見いだそうとでもしているかのようなこの作品は、私には大変面白い音楽でありました。
調性の無い、一般的には難解な部類に入る音楽ですので、誰も彼もに薦めるのはどうかと思いますが、ムターが言うように、こういった新作を聞いていくことが、次の文化を生むのだということ。古典作品だけで事足りるとしたら、それは音楽文化の自殺行為に他ならないと私は考えます。
二十世紀最後の年となりましたが、今世紀の作曲界が決して不毛ではなかった、あえて言うならば、大変技法的にも発展をし、豊壌な世紀であったと私は考えています。
ドビュッシー、ラベル、オネゲル、、マルティヌー、ショスタコーヴィッチ、ブリテン、武満、ストラビンスキー、ウェーベルン、ベルク、シュトックハウゼン、ルトスワフスキー、メシアンと思いつくままに今世紀活躍した作曲家たちの名前を書き連ねながら、その中にモレも入れるべきだと、私は考えています。
ただ、その作品に触れる機会があまりにないのが残念です。
一九九一年のこれらのCDが発売されて、カタログ上はまだ生きていますが、とっくに製造中止で、いまは手に入れるのは難しいのではないでしょうか。
モレの音楽の普及の道はまだまだ遠いのでしょうか。
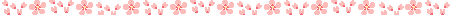
|
|