2001年2月中国貴州省の旅
2月11日(土) -3-
凱里(かいり)博物館 (1)
この博物館は、普通には、開館していないとのこと。
連絡して、開けてもらうらしい。私達が行った時も、
ガランとした館内は、私達だけだった。係員もいない。
同じフロアの反対側は、家具屋さんになっているという不思議な
博物館だった。
画像の撮影ももちろん自由だった。
ここでは、これから先、全ての画像がクリックして
大きい画像を見られるようになっています。
あまり、興味のない方は、
眺めて通りすぎて下さい。
説明が不充分なこと、あらかじめご容赦下さい。
説明書きは全部中国語でした。出来るだけ説明の
プレートも入れて撮影するようには、しましたが、
フィルム不足の不安もあったため、
そのためだけには、撮影しませんでした。
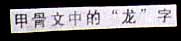
(左)甲骨文字の中の「龍」という文字
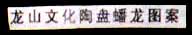
(右)龍山文化時代の陶器に描かれていた「龍」の図案
「龍」は、吉祥のシンボルとのこと。
刺繍や銀冠に多く使われている。

龍模様のミャオ族の現代刺繍の作品
あまりにも見事なデザインと色彩に目を
奪われて完全に説明を見忘れていたらしい。

角がある龍の図案
本によると、
この刺繍とデザインは、貴州省の剣河県と
台江県施洞に見られるものとなっている。
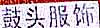
音楽隊のリーダーの服装
ミャオ族男子の服装と説明が
あったかと・・・
ろうけつ染の上に美しい
アップリケ風の刺繍をほどこしたもの。
なんてかわいい模様を思いつけるんだろう
という感じだ。

祭りの時の男子の服装
↑撮影に失敗し、一部分だけスキャンしたもの
この刺繍のステッチが刺繍の手法の一つ
「べんしゅう」ということ。

「刺繍」に「刺繍」の説明で、あれ?という感じだけれど、
これも手法の一つの名称なのかもしれない??

本に刺繍の手法として載ってはいるけれど
これだけ読み方が載っていない。
この刺繍の精緻さとバリエーションの
豊かさのため特にミャオ族に
心引かれ、それが私をこの旅へ誘った。
刺繍のひとつひとつを見ながら、
「これ、これこれなんだよねぇ。」と
心の中の興奮を押さえきれない。すこ゜い。
暮らしの中で母から娘へ脈々と
受け継がれてきたこういう見事な手仕事は、
もうそれだけで、感動に値する。
それが、しかも千年単位の長い苦難の時代をのり越えて
今に至っていると思うとなおさらなのだ。
山深い、大変な場所で、外に向けてではなく、
自分達のためにひっそりと一針一針刺し続けられてきて、
こんな素晴らしい
文化が守られてきたのが何とも嬉しい。
先にも引用している鳥丸貞恵さんの「布の風に誘われて」に
こんな一節があった。
「町から来た人は、織物を芸術みたいに言います。
だったら、この村の人、皆アーチストです。」
この感慨は、刺繍についても当てはまると思う。
なんていい色合いなのだろう
実物を幾ら覗き込んでも
どう刺しているのかわからないステッチがあったり、
見ればもう限りというものがない。
写真も撮りつつ、ガラスに顔をくっつけて、覗き込んだり
しているうちに時間は、あっという間に過ぎていった。
フィルムにゆとりがあれば、一作品ずつ、アップの写真を
撮りたかったところだった。
結果、普通の写真からスキャナーして、アップに
したため、出来あがってみると、肝心の縫い目までは
見えず、自分でも期待はずれで、残念。
細かい確認が抜けていたりしますが、
まずは、アップしました。
ただ刺繍を見ることと刺繍をするのが好きだというだけの
素人が、見て来たこと、聞いて来たことを調べながら、
書いています。間違いもあるかと思います。何か、ありましたら、
教えていただければ、と思います。
*中国語の説明部分は、友人を通して、
北海道大学の中国人留学生の方にお手伝い
頂きました。















