98.10.09
貫一さん!
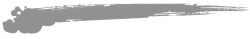
前回に登場した「金色夜叉」の、有名な熱海の海岸の場面。富山唯継に心を傾けたお宮を振り払って、間貫一(はざま・かんいち)は去って行きます。
やがてその黒き影の岡の頂に立てるは、此方を目戍(まも)れるならんと、宮は声の限に呼べば、男の声も遙に来りぬ。
「宮(みい)さん!」
「あ、あ、あ、貫一(かんいつ)さん!」
(新潮文庫 p.78 ルビ一部省略)
「貫一(かんいつ)さん!」のカッコは、新潮文庫ではルビ(振り仮名)になっています。僕は新潮文庫しか見たことはありませんが、たぶん発表当時も「貫一(かんいつ)さん」だったのでしょう。
これを何と読むかがちょっと問題です。まさか「カンイツサン」ではないだろうから、「カンイッサン」なのだろうか。しかし、こう発音してみると、どうも間が抜けています。
「カンイッツァン」と読んではいけないでしょうか。つまり、ここの「さん」は、現代の「つぁん」という表記に当たると考えるわけです。
「ツァン」と読ませたいなら「つぁん」と書くだろうというのは今の発想で、昔は「ツァ」と読ませるために、どう表記したらいいか悩んだようですね。有名な例ではありますが、文化年間(19世紀初め)に刊行された式亭三馬の「浮世風呂」には
兄「おとつさ゜んまだ熱(あつ)いものを(「浮世風呂」前編 巻之上 新日本古典文学大系版 p.22)
甘「イヤ\/飛八(とびはつ)さ゜んの話(はなし)はいつも鉄炮(てつぽう)だテ(同 四編 巻之上 同書 p.230)
のように、「さ゜」で「ツァ」を表す例が見られます。しかし、この表記は明治時代には受け継がれなかったようです。
『日本国語大辞典』の「おとっつぁん」の項では、明治以降の例として上司小剣「父の婚礼」(1915)、および、谷崎潤一郎「異端者の悲しみ」(1917)が挙がっています。
「〔前略〕内ぢやあお富より外に、お父つあんだつて私だつて、その機械に手もつけた事はありやしないんだよ。」(『谷崎潤一郎全集』4 p.392 による)
これらを最古例とすれば、「つあん」の表記は大正時代から出てきたものかとも思われます。
「ツあん」という表記もあり、やはり大正期に高浜虚子が「染吉ツあん」(「杏の落ちる音」)、昭和戦前に新美南吉が「太一ツあん」(「耳」)などと用いています。ひらがなの「つ」とせず「ツ」としているのは、〔tsu〕ではなく〔ts〕を表すのだと強調する意味があるのかな。
明治期に「つぁ」の表記が確立していなかったとすると、「貫一(かんいっ)さん」も「カンイッツァン」だった可能性は十分考えられるでしょう。「カンイチサン」からの変化の仕方としては、むしろ「カンイッサン」よりも自然だと思います。
「オトッツァン」とともに「オトッサン」はあり得たらしいです。漱石も1915年の「硝子戸の中」で、下女から聞かされた話として次のように書いています。
「貴方が御爺さん御婆さんだと思つてゐらつしやる方は、本当はあなたの御父(おとつ)さんと御母(おつか)さんなのですよ。先刻ね、大方その所為であんなに此方の宅が好なんだらう、妙なものだな、と云つて二人で話してゐらしつたのを私が聞いたから、そつと貴方に教へて上げるんですよ。誰にも話しちや不可せんよ。よござんすか」(『漱石全集』12 p.589 ルビ一部省略)
しかしこの「おとっさん」も、中には、筆者が「オトッツァン」のつもりで書いたものもあったのではないでしょうか。
|