

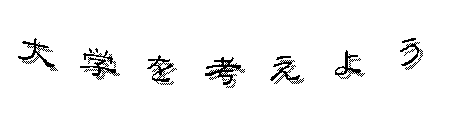
番外
おいおい!(自己流「ルール」と「試験」)
今年度も大学はいよいよ大詰め。(これは1998年春のことです)
この時期、学生諸君にとっては「一大事」である、「定期試験」をはじめとする一連の行事があって、成績評価と単位認定が下されるわけです。
「大学」に、「評価」などふさわしいのか、という素朴な疑問もあり得ますが、世界広しといえども、「成績評価」をやらない大学なんていうのはどこにもないので、やはり意味のあることでしょう。「卒業」も、一つのことを成し遂げるという意味で、大事なステップでしょう。まあ、きれいごと抜きでも、年に一回くらいは本気で頑張ってみるのもいいじゃありませんか。
確かに学生諸君にとっては、一生の運命を左右されかねない、大きなハードルでもあるのは事実です。ここで単位が取れないと、「卒業」ができない、そう悩む気持ちはよくわかります。
でも、ちょっと考えてほしい。人間のやることですから、成功も失敗もあります。努力不足を後悔することもしばしばです。それが人生というものでしょう。
ところが、こと大学に関しては、実はいっこうに悩みもせず、何かひとごとのような顔をして、試験(それも卒業年次生の特権である「再試験」)が終わるやいなや、教師をつかまえて、「あのーいまの試験できなかったんで、卒業したいんで、『救済措置』がないですか?」とか、「ちょっと点が足りなさそうですから、レポートでも出したいんですが?」などと言ってきます。今年なんか、まだその「再試」のある前にやってきて、「自信がないもんで、何か救済措置があるでしょうか?」とのたまわった猛者さえいました。
こうした諸君は、自分たちが「救われる」のが当たり前だと、はなから信じ込んでいるようです。教師は「試験」なんていうチンケなことはこだわらず、気前よく我々を救ってくれて当然、という考えのようです。
なるほど、大学の教師は、学生に単位を乱発しようが、「鬼」になろうが、自分の損得には縁がなく、どうせなら「恨みっこなし」で単位を恵む「仏」になれば気楽なことこの上なしでしょう。単位をやたら出すのでけしからんと「譴責」を受けるとか、給料を減らされるなんていう心配はまるでないのです。
しかし、これはやはりおかしいのではないでしょうか。大学教師の良心と使命と社会的責任にかかわるのはもちろんです。また少なくとも、小難しいことを言わずとも、他の履修者諸君は与えられた条件下で、きちんと試験を受け、成果を出しているのです。それを、努力の有無をおよそ省みもせず(そうした諸君に限って、全然授業になんか来ていないのです)、「救済措置を」とみずから求めてくるに至っては、自分の意思で「ルール」はどうになるとでも言っているのと同じではないでしょうか?そういうのは「不公平」じゃないんでしょうか?
野球の試合で言えば、9回ウラを迎えて依然「3対ゼロ」で負けているので、この際、急遽ルールを改正し、試合は10回まで、しかも10回ウラには、先方はピッチャーとキャッチャー以外はフィールドから引っ込めることにする、と一方的に宣言するようなものです。「試験」もやっていないうちから、「自信がないので救済措置」などと言ってくるに至っては、試合開始前から、+10点ハンディをつけてくれ、あるいは、「我が方が勝ちこすまで」どこまでも試合は続けてくれ、と言ってくるようなものでしょうが。
このようにたとえてみると、自分たちの言っていることがいかに道理がなく、非常識きわまりないことがわかってくるはずです。そんなふざけたルールの「試合」はどこにもありはしません。
それにも少しも気づかないほど、こうした諸君は、大学というのは「単位」ないし「卒業証書」自動販売機と心得ているようです。授業料さえ払えば、教師は単位を出してくれて当然じゃないか、意地の悪いことしないで、「救って」下さいよ、その「アリバイづくり」くらいはつきあいますから、というわけなのでしょう。
こんなずーずーしい、失礼千万、もちろん「大学卒業生」=「学士」にはとうていふさわしくない諸君がみんなだとは思いたくはありませんが、残念ながら、「大学改革」進展の成果はこのくらいの状況のようです。少なくとも、自分の方から「救済措置を」なんて言い出してくる心臓きわまりない諸君は、以前は、まずいなかったように思います。これが「改革」の成果として、大学が誇りを持ち、その責任のもとに社会に送り出せる人材なのでしょうか。
せめて、自分が卒業できそうもない、困っている、悩んでいる、ここに至ってしまった経緯に大いに反省している、自分の学生生活は何だったのか、自分は大学で何を得られたのか、自分にとって「学問」はどういう意味を持っていたのか、心底いま思い返し、頭を垂れ、今後どう生きるべきか考えている、そんな立場で、教師に率直に相談をし、思いのほどを、苦しみを語ってくれるのなら、こっちも当然いろいろと感じるところがあります。こっちも人間であり、なによりも、学生諸君の成長と将来に大きな期待を持ち、また責任を感じているんです。「学問」以上に、その人間性と生き方を気にしているんです。「教育」ってそんなものでしょう。
そういうのを、まだ「かわいげがある」と言います。当たり前のような顔をして、「救済措置は?」なんて言ってこられて、「はいはい、当方は単位自動販売機ですから、足りない分あと○○を入れて下さい」なんて平然と応えてくれると思っているんでしょうか?言われた当方、正直申して「切れたく」なりますよ。「おいおい、それはこっちの決めることだろう。自分の努力不足はどうでもよくって、『救ってもらって当然』はないだろう」って。
だいぶ前ですが、「なんとかしてくれ」とまとわりついてきたあげく、「先生、頑張って下さい」とのたまわった超大物もいました。大学卒業できるように「頑張る」のは、教師のつとめらしいのです。
大学の授業のすすめ方、成績評価のあり方に疑問や意見があるのなら、それは大いに歓迎します。お互い「大人同士」でつきあうのが大学です。そこにこそ「学問」があり、「進歩」があります。
以前にも、そうした疑問を呈し、意見を手紙で寄せてきた人がいました。その人の言い分は、「自分はこの講義ほとんど出て、ノートもきちんと取っていたつもりなのに、単位がとれず、ところがその自分のノートを写していった某君は、ろくに出席もしていないにもかかわらず合格、これは不公平だ」というのです。まあ、気持ちは分かりますが、私の意見としては、「大学の授業は『オリンピック』じゃないので、『出席することに意義がある』とは思わない、『出席』してなくても単位が取れてしまうくらいに易しい問題に、なぜ君はちゃんと答えられなかったのか、それはまずいのではないか。そして、私の考えでは、『出席』は決して単位取得の十分条件ではないはず」ということでした。そうした返事も出しました。
ただ、その彼の言っていることに一理もありますから、私として、「出席を取る」というむなしい、形式的な作業をすることなく、そのかわり「出席状況も評価に加味する」という方針に致しました。「出席」は「必要条件」でも「十分条件」でもなく、むしろ「プラス」に加算するのですから、これは誰にも不公平はないと言えるのではないでしょうか。
このように、理のある議論をする、批判に答えるのはいっこうやぶさかではありません。学生諸君にはそうした「権利」が当然あります。でも、「単位自動販売機」や、「我が方ルールの試合」はやめましょう。そんなことやっていたら、日本の大学はいよいよおしまいです。そして、そんなことが当然と思いこんでいる諸君は、自分自身を辱め、世の中をなめ、どこでも通用しない自分をいつしか作り上げてしまっているのです。
自分の学生時代には、学部にも5年間も滞在した、「大学劣等生」としての私の言い分です。
◎おどかしますと、間もなく、「再試」は受験可能単位数が大幅に規制されます。「試験」を甘く見ちゃいけません。
 (「大学を考えよう 最終篇」へ)
(「大学を考えよう 最終篇」へ)