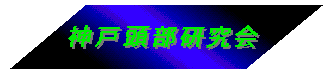
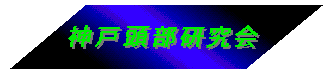
![]()
予防医学における病院情報システム
カルテにおける、One patient One codeの概念により より良い患者看護のためには1人の患者に関わる全ての情報が統一される必要がある。 つまり 患者の病歴等が、短時間の内に利用できるシステムで保管、蓄積、管理されていなければならない。
今まで、独立して活動していた外来医療、放射線科検査、検体検査、処方(薬剤)、給食、理学療法、において どの部署からも患者データーの保管、管理、活用ができれば患者にとっては時間(外来診察等)の時間短縮 それにもまして当病院において全てのデーターが安全に管理されている安心を提供することができる。当病院においても、人員削減、時間短縮、コスト削減等が見込まれる。
そこで、当院外来診察部に伴う充実した健診センターに着目すると 外来診察に来る患者が来院することを待つ 待ちの姿勢だけでよいか? と、いう疑問から健康人として来院し 実施した健診項目のデーターが外来診察部の疾病患者のデーターとリンクされていることにより予防医学が始まるのではないか!? 実際データーの一元化がなされていないのが実状である。
病院は、本来疾病を持つ人に対処する公共の場所であるので 健康人のデーター蓄積は馴染みが薄く それが外来データーとリンクすることにより何を生み出すのか疑問であるかもしれない。疾病患者を診療することが病院という機能分担があったとしても データーの一元化は、当然有益であり それが医療の質を高める事になると考える。これから放射線科としまして、予防医学の観点より 疾病患者のみに高額医療器機を使用するのではなく疾病になる前に予防、治療できるための検査を増やしていきたいと考える。その為に、Personal Computerによる患者データー管理を押し進めたい。
個人の健康管理に関わることから収集され一元化され、今まで会計中心としてSuper Computerからの端末による活用ではこれらのシステムの活用には 無駄と限界が来るのではないかと考え、医療情報を複数のデーターベースを複数のPersonal Computer持たせて Networkし footworkの軽い分散型データーシステムLANを構築し Cliantを複数台しよう可能とする。
基本原理としまして、病院機能を有効に活用するには医師、看護婦、技師等の緊密な連帯が大前提となる。その為には、業務(雑務)の効率化を図り 各業務間の独立性を尊重しながらも情報の管理の一元化をなし 病院全体があたかも単一の機能体のような軽いfootworkで動くことができるようなシステムとマネージメントが必要となってくる。Network構築は、単に病院の電算化を図るのではなく病院の重要なデーターシステム一元化することである。
この機能の、最たるものがオーダーリングシステムというものである。
オーダーリングシステムは、正確な情報を各部門に伝えることから それぞれの診療現場での発生源が必要になってくる。これが、1人の患者に対する各部門へのオーダーとなってくる。発生源(Cliant)で正しく入力された情報は、各検査で必要な情報が得られることや 看護婦の看護計画にもスムーズに反映されることにより病院全体の高率化が図れる。Cliantにおける、情報活用には入力・出力も可能なのでカルテの受け渡しその他の患者のオーダーの効率化も図れる。これら全てのことが行われることにより 患者の病院での滞在時間の短縮が見込まれる。それが口コミという広報活動となり外来患者の増加が見込まれる。近年問題となっています、駐車場の問題の解決策にもなると考えます。
もちろん、これらのCliant情報は正確な医事会計(Receipt)時における保健請求漏れの最小化に格段の威力があります。正確な実施情報は物品消費管理、病棟別原価管理&消費管理など要用にリンクされていき活用されていく。
何人もの手による入力では、その間に必ずミスが生じる。入力者が1人なのですから、その人が間違わない限りは・・・。
しかし、各部門の単独では保健請求漏れの防止にはつながらず 本当に中途半端なシステムでは採算を無視してものであり処方、検査等の全てのオーダーシステムの構築が 又、情報センターという情報部門という組織を中心とした強力なサポート体制維持が必要不可欠である。中途半端な支援では必要がないと行っても過言ではない。
1) 病院全体の無駄を無くし、事務効率を上げる。
2) 情報の依頼姓の向上
3) 患者の待ち時間の軽減
最大の効能は、このシステムにより医師、看護婦、技師、医療事務員など全ての職員の意志疎通を図り 1人患者を中心とした医療情報の提供と支援によるTeam医療の現実化である。
導入にあたり、問題が山積していることも事実である。
1) 検査オーダーの入力を誰が行うのか?
2) 管理は誰がするのか?
3) 購入機器の種類
4) システムパッケイジ
5) 情報処理部門の開設
6) 人員の確保
etc・・・
経済性を病院運営のパーセンテイジに置き換えていかなければならない。
今回放射線科では、当病院の将来的Network構築時にスムーズな運用となるべくPioneerになるべくComputer Networkに着手したい。
放射線科検査全般の患者情報入力を、Apple社 Macintosh LG475の3台によりLANを形成し 各Computerに独自性を持たせる。
所見入力に関しましては、医師中心として技師のサポートとして医療行為に対してのFeed backを潤滑に行うためにコード化とする。
放射線科の総意として、Personal ComputerによるLAN形成について御検討下さい。
尚、詳細については別紙 もしくは口頭により御説明申しあげます。
1993年7月25日
放射線科医 上野敬司
放射線科課長 桑原英樹
古谷義明
島田 隆正
上記内容は、私が1993年 今から5年前に蘇生会総合病院に在職中にMacintoshによるRIS形成をするべくPersonal Computer導入時に経営者 side への倫理書に塗布した物です。
Datebase構築に関しましては、3嵂月もしない内に簡単に出来るが その後の運用・管理などのたくさんの門題に対処して行くには 構築以前にしっかりとRIS構築の意志を持っておくべきと考えます。
これから、RIS構築時にはご参考に成れば幸いです。
∞ 大阪医科大学
http://www.asaka-med.ac.jp/indexj.html
∞ 京都大学医学部附属病院
http://bigblue.hyg.kyoto-ac.jp/index.html
∞ 京都大学大学院医学研究科社会医学系
http://minko.hyp.med.kyoto-u.ac.jp/
∞ 大阪大学医学部
http://www.med.osaka-u.ac.jp/index-jp.html
∞ 滋賀医科大学
http://www.shiga-med.ac.jp/
∞ 京都府立医科大学
http://www.kpu-m.ac.jp/
∞ 京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/
HOME/X-RAY TOPICS/CIPHER/PAPANICOLAOU