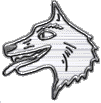 「小説部屋」 へ戻る |
 「泡沫の世界」 トップへ戻る |
 「新月の遠吠え」 メニューへ戻る |
手のひら 1・2・3・4 |
| 呂蒙と初めてキスをしたのは、初めて会ったその日だった。甘寧が黄祖の元から東呉に降りたい旨を打診した時、その仲介に来たのが呂蒙だった。 呂蒙は甘寧を見ると同時に顔を赤らめ、ほんの少しの会見の後、いきなり「好きだ」と言った。 初めは相手にしなかった甘寧だが(だいたい、「好き」という言葉は甘寧にとって禁句だったはずだ)、気がつくと月明かりの川辺、柳の木に背を預けながら、甘寧は呂蒙とキスをしていた。 それは、生まれて初めてのキスだった……。 「頭ぁ、本当にここで暮らすんですか?」 呂蒙が主公に命じられて用意した屋敷はとても趣味の良い物で、しかも錦帆時代の手下八〇〇人が一緒に暮らしてもやっていけるほど広い物だった。だが、いつも粗末な家に住み慣れている身には、そこからは居心地の悪い匂いがした。 新しい木の香りがする部屋の中で、甘寧は窓の外を眺めていた。大きな柳の木の枝が、さらさらと涼しそうな木陰を作っている。 『俺を好きになってね』 あの時、呂蒙はまじめにそう言った。自分を好きだと言ったあの男は、気持ちを変えさせてやろうと語った甘寧の過去を聞くと、考えを改めるどころか逆に甘寧を抱きしめて唇を重ねてきた……。 好きになる……? 優しい顔をしている男だった。戦の合間に見た時はもっと大柄な威丈夫だと思っていたが、実際には驚くほどの優男だった。 『俺、もっと早く興覇に会いたかった……』 「頭? 頭!」 「ん?」 甘寧が目を上げると、後ろに副頭の利斉が立っていた。屋敷の中を直している最中らしい手下共の監督をしていたはずだが、どうやら一区切りついたようだ。 「何だ?」 「いや、下の奴らがこんな屋敷より、船で暮らした方が気が楽だって言ってますがね。本当にここで暮らすんですか?」 「しょうがねぇだろ。で、みんな入りそうか?」 「まぁ一部屋に人数詰め込みゃ何とかなるでしょう。……どうかしましたか?」 「別に……」 『俺を好きになってね』 あの男は、まずお互いを知るために話をしたり花を眺めながら歩いたりしよう、と言った。俺があいつを好きになったら、それからキスを沢山しよう、と。 好きになるって、どういうことだろう……。 だいたい、話をするって何を話すんだ? 花を眺めながら歩くと何か変わった事でも起こるのか? キスを沢山……? 甘寧は期せずして結んだ唇の感触を思い出そうと、そっと唇に手を当ててみた。 あの時は頭がどうかしていた。 今まで誰にも許したことのなかった唇を、あんな簡単に、しかも初めて会った男に許してしまうなんて……。 月明かりが辺りを青く照らしていた。そこに現実の匂いはなく、そう、きっと俺は夢の中にいたのだ……。 『俺を好きになってね』 ……あんな事をまさか俺に向かって言う奴がいるなんて……。 体を合わせる時、まるでそう言うのが義務であるかのように「好き」とか「愛」とかいう言葉を紡ごうとした奴は何人かいた。薄っぺらい、見せかけの言葉。それは甘寧が大嫌いな言葉の一つだった。 お前達が好きなのは「甘寧」というよくできた玩具であって、俺じゃない。体は物だ。触りたければ触ればいいし、抱きたければ抱けばいい。なぜそんな下らない言葉を口にしなければならないと、どいつもこいつも信じているのか。 まだ故郷で役人をしていた頃、甘寧はただの玩具だった。玩具だった甘寧に、そんな言葉を吐く人間はただの一人もいなかったし、勿論キスを求められることはなかった。そこにあるのはただ純粋な力関係で、切り札を握られていた甘寧に、そこから逃れるすべはなかった。 いっそその方が楽だと知ったのは、水賊として名を馳せてからだ。 「好き」とか「愛」とか、そんな言葉を用いなければ、「皆殺しの甘寧」を抱く勇気もない奴らばかり。何という茶番だろう。おかしすぎて吐き気がする。 だから、そんなばかばかしいことを言う奴は皆、血に飢えた手下共に投げ与えることにした。それは思ったより楽しいことだった。 俺は血に飢えている。俺が求めているのは人のぬくもりなどではなく、ただ、その皮膚の下を流れている血液なのだ。俺を唯一慰め、俺を鎮めることが出来るのは、ぬるぬると肌にからみつく、あの赤黒い液体だけなのだ。 それなのに……。 『俺を好きになってね』 あの男。何であんな無邪気なことが言えるんだ。好きになるなんて。俺を好きだなんて。そんな事を何で簡単に言えるんだ。 甘寧が語ってみせた過去に、呂蒙は傷ついた顔をした。傷ついて、甘寧をきつく抱きしめた。 『興覇は本当は、泣きたかったんだね』 『これは、興覇が流すはずだった涙だよ』 俺は泣きたいなんて思わなかった。涙は屈服の証だ。俺は決してあいつらに負けたりなんかしなかった。あいつは俺のことなんか何も知らないくせに、勝手なことを言って勝手に俺にキスなんかして、勝手に俺を好きだとか勝手に自分を好きになれとか、勝手に……勝手に……。 なのに、どうしてあの男の腕は心地良かったんだろう……。 「頭」 「あ?」 背後からまた利斉の声がして、甘寧は少し驚いた。 「なんだ……。まだいたのか?」 「何言ってんですか。さっきちゃんと出てったでしょう」 「……あぁ、そうだったっか? で? 飯でも出来たか?」 「さっき食ったばっかりですよ。頭ぁ、大丈夫ですか? 何があったんです?」 「……何でもねぇよ」 いくら相手が利斉とはいえ、人のいる気配にまるで気づかないなんて……。甘寧はあまりのらしくなさにカツを入れようと、自分の両頬を音の出るほど叩いてみた。 「で、何の用だ?」 「頭に客です」 コトン。 自分の心臓の音が聞こえる。何か言おうとしたのだが、出かかった言葉を出したものか、飲み込んだものか悩んで、甘寧は自分の唇を舌で濡らした。 「……客?」 「はい。いつもの呂の旦那ですよ」 入ってもらいますか?という問いに、甘寧はすぐには返事が出来なかった。 呂蒙は忙しい仕事の合間を縫って、時間を見つけては甘寧の屋敷を訪れた。城に行けばいくらでも顔を合わせるというのに、毎日毎日訪れた。 そして、呂蒙はただ甘寧の元を訪れて、何もしないで帰っていった。たまに思い出したようにキスをする。たったそれだけの為に、呂蒙はバカみたいに甘寧を訪ない続けた。 「頭?」 ……会いたくないような気がする。会えば、必ず混乱する。胸がザワザワして、落ち着かなくなる……。 お前は何を考えているのか、と。 お前の目的は何なんだ、と。 そんな言葉が胸に詰まって、いつも息が苦しくなる。 黙り込んでしまった甘寧の顎を掬い上げる様にして、利斉は甘寧の顔を覗き込んだ。 「あ?」 「頭、あんまり顔色が良くねぇ。帰ってもらいやしょうか?」 「あ、いや、大丈夫だ」 心配顔の利斉を安心させようと、甘寧はいつものように唇の端で笑って見せてから、呂蒙のいる客間に向かった。 「興覇!」 呂蒙は今日も笑顔を見せている。だが甘寧には、その笑顔が分からなかった。 「よぉ…」 「どう? 家の中、片づいた?」 「あぁ、まぁな…」 「住み心地、どう?」 「お前、それ昨日も訊いただろう?」 甘寧が呆れたように言い返すと、「だって気になるんだもん」と呂蒙はやはり笑顔で答えた。 「興覇、今時間、ある?」 「あぁ」 「じゃあ、少し散歩でもしようよ」 甘寧は辺りを見回した。確かにこう手下共が睨みつけていたのでは、呂蒙もさぞ居心地が悪いだろう。かといって昨日みたいに部屋に引きこもると、また帰りしに何を言われるか分かったものではないし……。 「あぁ、じゃあ少し出るか」 「うん」 嬉しそうに頷いて、呂蒙は甘寧をリードするように部屋を出た。 手のひら 1・2・3・4 |
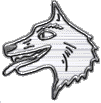 「小説部屋」 へ戻る |
 「泡沫の世界」 トップへ戻る |
 「新月の遠吠え」 メニューへ戻る |